週刊こぐま通信
「代表のコラム」合格者からのアドバイス(3)
第896号 2024年6月7日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

前回、前々回に引き続き、合格者の皆さまからのアンケートをご紹介します。
今回は、私(久野)からは「家庭での学習の仕方」、特に入試で大事な夏以降の学習の仕方・過ごし方についてのアドバイスをご紹介し、「入試を子どもにどう伝えたか」を島津から、「学校情報の集め方」を齋藤からご紹介します。ぜひ秋の受験に向けて参考にしてください。
今回も私から始めます。夏以降の過ごし方について次の質問にお答えいただきました。
- 夏季講習会では何を受講されましたか?(複数回答可)
- 総合力完成講座 / 志望校別対策講座 / 行動観察対策講座 / 手先の巧緻性講座 / その他
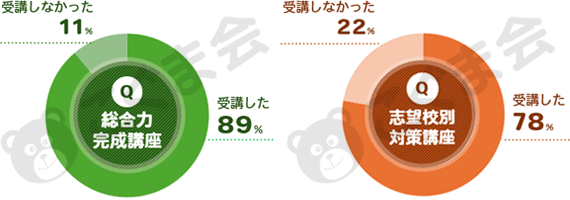
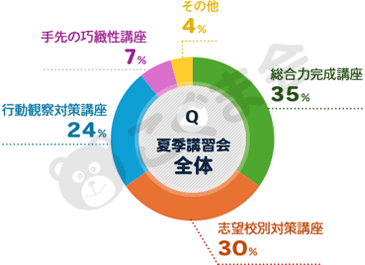
- 夏季講習会のない日は、平均どの程度家庭学習をされましたか?
- 30分~1時間 / 約1時間 / 約2時間 / 約3時間 / それ以上
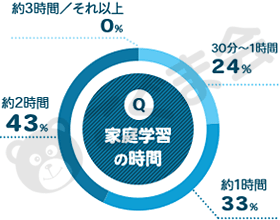
- 夏休みの学習や過ごし方について、工夫された点や気をつけた点がありましたらお聞かせください。
- 夏休み前と比べて生活リズムを大きく変えることは無かったですが、課題(問題集)の目次で、終わった問題には本人にマルをつけさせて、ワクワクしながら攻略する気持ちを盛り立てようとしていました。
- 夏(もしくは夏休み)にしか体験できないこと(海水浴・プール・バーベキュー・旅行・花火など)に積極的に時間を割いて、本人の心身が健康でいられること(楽しみと毎日机に向かうという頑張りのバランス)を心掛けました。
- 夫婦ともにフルタイム勤務のため夏休みは特になかったですが、夏のイベント(盆踊りやお祭りなど)には積極的に参加するようにしました。何とか家族で休みを合わせて2泊3日のキャンプへも行きました。
- 規則正しい生活をもとに、子どもが興味ある場所に一緒に計画を立てて旅行をし、いただいた絵日記帳で思い出を振り返り会話をたくさんし、面接のときの質問に答えが浮かびやすいようにしておきました。
- 過去問を2回解きました。
- 旅行でたくさん思い出を作り、教会学校にも行き、毎週末のように公園などで自然に触れました。そのため願書の内容が濃くなったと思っています。
- こぐま会で配布された教材には全て手をつけました。テストで間違えてしまった苦手分野のみ、別途ショップこぐまで教材を購入して繰り返しやりました。
- 基礎問題を年中レベルに戻ってやりました。手先の巧緻性は毎日やりました。
- 夏季講習に行く日が多かったのですが、夏の思い出もたくさん作れるようにグランピングや祖父母の家に数日間のお泊りで、花火・バーベキュー・プール等、遊ぶ時間もしっかり確保しました。祖父母と一緒に毎日絵日記を描いたり、人生ゲーム(すごろく)やトランプで遊んだり、家族を巻き込んで受験に取り組みました。
- セブンステップスカリキュラムの学習内容の中でも、まだ理解の浅い単元や苦手分野がありましたので、家庭で基礎に立ち戻ってしっかり復習することと、夏季講習での課題は必ず家庭で復習して取りこぼしのないことを留意しました。子どもの場合、そのような基礎固めがまだ必要だったので焦って難問に取り組まないようにしました。ただ、志望校の傾向はよく把握するようにし、その傾向にあった基礎を固めるようにしました。
- 決して学習だけにならないよう、毎日身体や五感を使って遊ばせることに最も労力を使いました。講習で時間のない日や猛暑で外遊びができない日も、家でちょっとした料理やお手伝いを遊び感覚で行ったり、さまざまな子ども向け体験イベントの活用や家族旅行など、バランスよく活動できるように予定を組みました。
夏休み中の学習や過ごし方については、それぞれのご家庭の生活スタイルに合わせて、いろいろ工夫されていることがよくわかります。特に夏の学習については、毎年次のようなことをお願いしています。
- 基本がしっかり身についているかもう一度確認すること
- そのうえで、難しい過去問についてはこの夏に繰り返しチャレンジすること
- 答えがあっているか間違っているかをチェックするだけでなく、どのように考えたかをしっかり説明できるようにすること
- 机に向かう勉強だけでなく、時間にゆとりがある夏休みにしかできない体験をいろいろ工夫し、家族とともに過ごした夏を印象深く記憶しておくために、「絵日記」などをつけること
次は、恵比寿本校室長の島津から「入試を子どもにどう伝えたか」です。
- 「入試」についてお子さまにどのように説明されていましたか
- 普段のこぐま会のテストと同じように楽しんでやってくるように伝えました。
- 必要以上に構えてしまう性格だったので、緊張させないように「楽しんできてね」と声かけをしました。
- テストを受けることや結果があることなどは理解していたので、どんな子も小学校前は試験をするけれど、特別に試験をするところ(学校)もいろいろやってみようねと前向きに伝えるようにしました。その上で、先生たちとパパやママで一番いいところを決めようねと話しました。
- 「今日は、小学校の先生が来年一緒にお勉強したり、遊んだりしたいなぁと思う子を選んでくれる日だよ。本当はみんな選びたいけれど人数が決まっているの。あなたならお話をきちんと静かに聞ける子と、そうでない子のどっちと一緒になりたい?先生も同じだから、一緒に勉強したいなと思ってもらえるように頑張ろうね」と伝えました。
- 小学校に入るための試験を受けないといけない。素敵な学校に入りたい子がたくさんいるので、その学校で「私がんばれますよ!」というのを先生に見せて選んでもらう必要があるというような説明をしました。その学校に合う子が選ばれるが、もしダメでもたくさん学校はあるから小学生には必ずなれることも伝えて安心させました。
- 学校は「神様が決めてくださるが、先生にご挨拶してどんな子かお知らせしないと決められないから、頑張ろうね」と伝えていました。
「入試」をどう伝えるかのスタンスはご家庭によってさまざまです。「はっきりと伝えた方が良い」場合も「あまり言いすぎない方が良い」場合もありますので、どちらが正解ということはないと思います。ご家庭の考え方はそれぞれですし、お子さまが持っている力を一番引き出せる方向性も各々の性格によって異なるからです。私たちもよく面談で「どう伝えたらよいでしょうか?」とご相談いただくことがありますが、それぞれのご家庭に合う方法と程度を一緒に考えています。大切にしていただきたいのは、本人にプレッシャーをかけすぎないこと、「あなたは~だから」と決めつけないことです。「入試がゴールではない」とこぐま会ではお伝えしていますが、子どもたちは必ず小学生になることが出来ますし、またどの学校に入学するとしてもその先の人生は開けていきます。
普段の生活においても、「これが出来なかった」「行儀が崩れる」など、ついできないことばかりが気になってしまいがちですが、見方を変えると、お子さまの僅かな成長や変化に気づくことがたくさんあるかと思います。ぜひそうした時に認める言葉がけをしてあげてください。頑張りを認められて嬉しくない子どもはいません。そしてその子の良さを一番知っているのはご両親です。言葉にして伝えることで子どもの自己肯定感が上がったり、安心感やモチベーションに繋がったりします。それが成功体験として、のちに間接的に出来ないことにトライしてみる活力になることも少なくありません。
せっかく頑張ってきたのですから、どのように伝え、どんな言葉をかけて送り出してあげるかを意識して、この年齢に、そしてその子に合った伝え方をしていただけたらと思います。
最後は、進路相談室長の齋藤から「学校情報の集め方」についてです。
- 学校情報をどのように収集されましたか。(学校説明会以外の方法)
- 各学校のWEBサイト / こぐまクラブ / 小学校受験情報サイト / 情報誌 / 在校生を通じて / その他
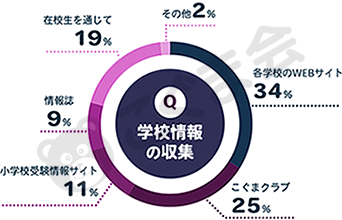
- 学校説明会は何校訪問されましたか
- 1~5校 / 6~10校 / それ以上
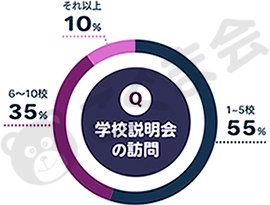
- バザーとオープンスクールに伺いました。先生方がとても熱心で、たくさんお話ししてくださり、自校を良くしていこうと誇りに思う様子がわかりました。バザーでたくさんのお姉さま方が声を掛けてくださりして、子どもが一番自然に楽しんでいました。
- 「学校ではその子の良い面を見つけるので、子どもに合った学校であるかまずは親御さんで吟味してほしい」とおっしゃる学校があり、心に響きました。また、入試前に「テストの模試」をしてくださる学校もあり、ありがたかったです。
- 説明会・運動会・公開授業に伺いました。説明会では、カリキュラムについて、またどんなお子さんを求めているか明確な説明がありわかりやすかったです。運動会では、とても活発に体を動かすことが好きなお嬢さんが多い印象でした。リトミックの演目は圧巻でした。授業公開は積極的に手を挙げるお嬢さんが多く感じました。
- 学園祭と校内見学に伺いました。実験を近くで見たり、お姉さま方と一緒に体験をすることが出来て、楽しい学校というイメージが膨らんでおりました。体験後は“あの学校へ行きたいから勉強頑張るね”と話し、意欲が伸びてくれました。
学校選びは本当に大変なことと思います。感想でいただいているように学校説明会や学校見学で実際の生徒さんを拝見することで、わが子と保護者さまの考え方の親和性を推し量ることができます。しかし、それでも足りない何かがあるとき、私たちはこぐま会卒業生の保護者の方にお話をしていただく機会を設けています。保護者さまも学校の今の様子のみならず、苦境を乗り越えたお話や勉強で工夫した点等惜しみなくお話をしてくださいます。
そのような情報の中で、学校に対する憧れや一般的評価からではなく、実際の学校理解へつながっていきます。その上で願書の作成や面接練習にも生かされていくことを毎年感じています。
今年も願書添削講座・面接練習講座が始まります。ご両親の子育ての総決算です。今までの子育てがどんなだったか、大切にしてきたことは何だったのか、文字や言葉にまとめるのは大変な作業です。全力でサポートしたいと考えております。
- 読み・書き・計算はまだ早い!
こぐま会代表 久野泰可 著「子どもが賢くなる75の方法」(幻冬舎)
 家庭でできる教育法を一挙公開
家庭でできる教育法を一挙公開
子どもを机に向かわせる前に実際の物に触れ、考えることで差がつく。- 食事の支度を手伝いながら「数」を学ぶ
- 飲みかけのジュースから「量」を学ぶ
- 折り紙で遊びながら「図形」を学ぶ
- 読み聞かせや対話から「言語」を学ぶ

KUNOメソッド こどもがかしこくなる絵カード(幻冬舎)
幼児の日常生活の中にある学びをカード化!
おうちで体験できるKUNOメソッド子どもたちの生活の中でできる学習経験を、ご家庭でより実践しやすいようにカード化いたしました。お求めは、SHOPこぐま・こぐま会ネットショップ ・全国の書店・各書籍ECサイトにて