週刊こぐま通信
「代表のコラム」ステップ6の学習が始まりました
第897号 2024年6月14日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

昨年、ゆりクラス(年中)で9月から開始したセブンステップスカリキュラムの授業は、ばらクラス(年長)に進級して半年がたち、先週から「ステップ6」の学習に入りました。ステップ1~4が基礎段階、ステップ5~6が応用段階、ステップ7は総まとめですので、新しい課題の学習は今回のステップ6が最後です。ステップ5と6は、入試に絡む課題が多く入っています。ちなみに、ステップ6は以下のような内容になります。
| セブンステップスカリキュラム step6 | |
|---|---|
| 未測量 | 重さのつりあい |
| 位置表象 | 地図上の移動、飛び石移動 |
| 数 | 数の増減、数のやりとり |
| 図形 | 重ね図形、回転図形 |
| 言語 | 話の内容理解、お話づくり |
| 生活 他 | 社会的常識 |
このステップの学習内容に関して出される入試問題の中で、特に子どもたちにとって難しい課題は
- つりあい
- 飛び石移動
- 数のやりとり
- 重ね図形
- 回転図形
授業では、どんな問題にも対応できるように基本を繰り返し指導し、決して最初から過去問を解かせるようなことはしていません。自分で解くことが大事であるし、それだけではなく「どのように解いたか」を説明させて、理解を確実なものにしていきます。5つの課題の典型的な問題を、授業で使うペーパーの中から紹介し、身につけるべきポイントを解説します。
- 1. つりあい
-
- 上のお部屋のシーソーはつりあっています。では、下にあるシーソーをつりあわせるには、?のついた形をいくつのせたらよいですか。その数だけ、○や△や●を反対側のシーソーの上にエンピツでかいてください。
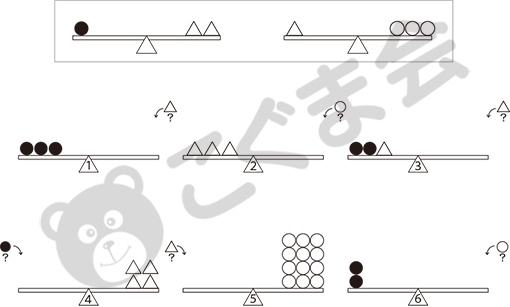
この問題はつりあいの基本ですが、右下の問題がポイントです。●と○の重さの関係を△を仲立ちに考えられるかどうかが問われます。同じように、○6個は●何個とつりあうかも考えさせてください。△を仲立ちとする「置き換え」の発想ができるかどうかがポイントです。
- 2. 飛び石移動
- 今いるところから、カメは1つずつ、ウサギは1つ飛ばしで、サルは2つ飛ばしで進みます。3匹は同時に動きはじめます。
- カメとウサギが出会う場所に、赤い○をつけてください。
- サルがカメに追いつく場所に、赤い△をつけてください。
- サルは何回跳ぶと向こう岸に着きますか。その数だけ下のお部屋に赤い○をかいてください。
- ウサギは何回跳ぶと向こう岸に着きますか。その数だけ下のお部屋に赤い△をかいてください。
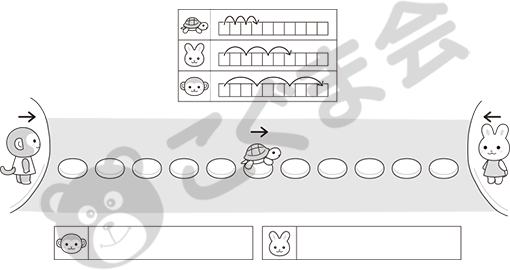
跳び方の違う3匹がそれぞれ何回跳べば向こう岸につくか、どこで追いつくか、どこで出会うかを、作業を通して見つけ出す問題です。最近重視され始めている「作業能力」を見る大事な問題です。約束を理解し、手を動かし、解答にたどり着く、そうした経験をたくさん持たせることが大事です。
- 3. 数のやりとり
- 太郎君と花子さんは5個ずつアメを持っています。
- ここから太郎君が1個花子さんにあげると、2人が持っているアメの数の違いはいくつですか。その数だけ、下のリンゴのお部屋に青い○をかいてください。
- もとの5個ずつにもどって考えます。今度は花子さんが太郎君に2個あげると、持っているアメの数の違いは、いくつになりますか。その数だけ、下のミカンのお部屋に青い○をかいてください。
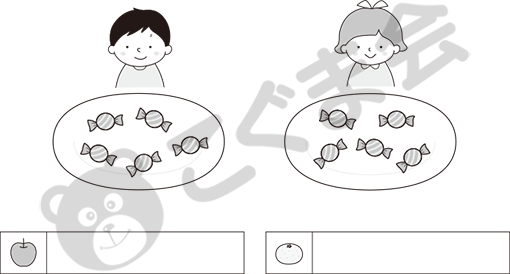
数のやりとりには、2つのタイプがあります。
- 違う数を同数にする
- 同じ数ずつ持っているときに、相手に1個あげたら違いは1ではなく2になることの理解
- 4. 重ね図形
- ア)上の形と下の形を重ねると、どんな形になりますか。下の□の点をつないでエンピツでかいてください。 イ)上の形を太い線のところで矢印の方に折って重ねると、どんな形になりますか。下の□の点をつないでエンピツでかいてください。
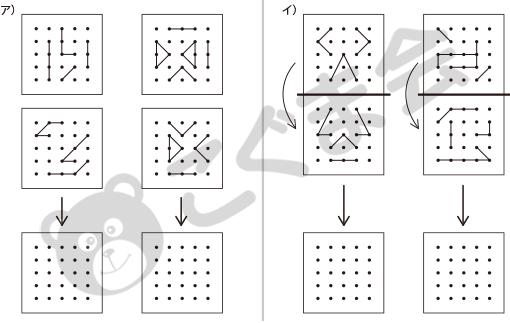
重ね図形には、基本的には2つの重ね方があります。そのまま上に重ねる場合と、半分に折って重ねる場合です。半分折りでは位置や方向に変化が出ますので、より難しくなります。選択肢から選ぶだけでなく、みずから描き表すことができるように練習することが大事です。ここに紹介したのは点図形を使った重ね図形です。特に半分折りの問題に注目してください。
- 5. 回転図形
- 上の形が、●は右に、○は左に、かいてある数だけ回転します。下の□に回転した形をエンピツでかいてください。
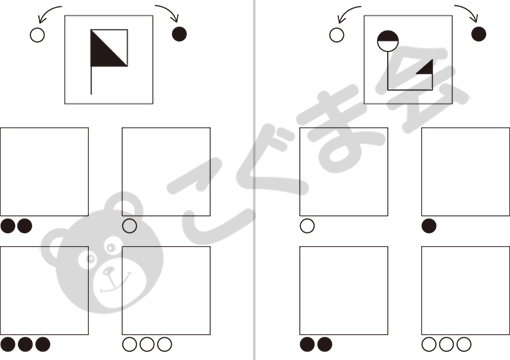
回転図形の場合、右に3回や左に3回回した時の問題に間違いが目立ちます。何回か練習していくうちに、右に3回は左に1回と同じ、左に3回は右に1回と同じということに気づけるとよいでしょう。
ここに紹介した以外に、「数の増減」は他の数の操作と絡むことが多く、数の増減部分は暗算で答えが出せることが大事です。特に数の増減と一対多対応の複合問題がよく出されます。また「話の内容理解」にはいろいろな問いかけの仕方があること、「お話づくり」は表現力・発表力を見る意味で、これから出題されるケースが増えていくことが予想されます。また、社会常識における「標識の理解」は、普段の生活の中でその標識の意味を捉えさせてください。図鑑的な知識の理解だけでは身につきません。夏休みを利用して標識調べのような経験を持たせると効果的です。
※次回コラムの更新は6月28日(金)です
- 読み・書き・計算はまだ早い!
こぐま会代表 久野泰可 著「子どもが賢くなる75の方法」(幻冬舎)
 家庭でできる教育法を一挙公開
家庭でできる教育法を一挙公開
子どもを机に向かわせる前に実際の物に触れ、考えることで差がつく。- 食事の支度を手伝いながら「数」を学ぶ
- 飲みかけのジュースから「量」を学ぶ
- 折り紙で遊びながら「図形」を学ぶ
- 読み聞かせや対話から「言語」を学ぶ

KUNOメソッド こどもがかしこくなる絵カード(幻冬舎)
幼児の日常生活の中にある学びをカード化!
おうちで体験できるKUNOメソッド子どもたちの生活の中でできる学習経験を、ご家庭でより実践しやすいようにカード化いたしました。お求めは、SHOPこぐま・こぐま会ネットショップ ・全国の書店・各書籍ECサイトにて