週刊こぐま通信
「代表のコラム」合格者からのアドバイス(2)
第895号 2024年5月31日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

前回に引き続き、合格者のみなさまからお答えいただいたアンケートをご紹介いたします。今回は、久野からは「仕事と学習の両立」について、島津からは「面接試験の準備」について、齋藤からは「学習時間の作り方」についてです。
まずは私から、「仕事と学習の両立」についてです。
いま、こぐま会では7割程度のお母さまが仕事を持ちながら小学校受験準備に取り組んでいます。私がこの仕事にかかわり始めた50年前はまだ仕事を持つ母親は少なく、大多数の方が家庭内でお子さまの受験準備に時間を使えていました。その後、女性の社会進出に伴い、働きながら小学校受験を目指す方が増えてきました。一方で、女子校を受験するにあたっては、共働き家庭は不利であるという噂もありました。実際、東日本大震災後の学校説明会では「緊急時にすぐ学校にお子さまを迎えに来られますか?」という学校側の発言があったため、そうしたご家庭がその学校を敬遠してしまうケースもいくつかありました。しかし、今はどの学校でもアフタースクールの制度を持ち、お母さまの立場に寄り添って子どもを守る応援体制が出来上がっていますので、仕事を持つ-持たないが合否に関係することはありません。それどころか、それが当たり前の時代になってきました。
共働き家庭の課題は、「家庭学習の時間の確保」と「限られた時間内での効果的な学習」です。合格された皆さまがどのような工夫をされたかをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
- 問1. お母さまは仕事をされていましたか(受験時)
- フルタイム(24%) / 時短勤務(24%) / 在宅勤務中心(19%) / 休職中(0%) / していない(33%)
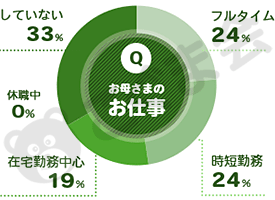
このグラフをご覧いただくと、全体の約3分の2のお母さまが仕事と受験を両立させていることがわかります。しかし、働き方もいろいろ工夫され、時短や在宅中心の勤務にしたり、一時的に休職して子どもに向き合ってきたご家庭もあります。ただ、働きながらもその約3分の1の方がフルタイムで受験に臨んでいますので、その努力は相当なものだったと想像できます。
- 問2. 問1で「はい」とお答えされた方にお聞きします。仕事とお子さまの学習を家庭内でどのように両立されていましたか?
-
- 曜日に関わらず、寝る前の30分間は、上の子(小学2年)と本人の2人ともが勉強する時間だと決め、夫婦で分担してそれぞれを見ていました。帰宅するのが19時頃になってしまうため、30分確保できなくても15分でもできれば「がんばったね」と褒め、決まった時間に寝かせることを優先していました。
- 具体物も用意して事前準備は済ませておき、すぐに取り掛かれるようにしておきました。
- プリントだけではなく家庭学習用ビデオを活用したり、ゲームなどをおりまぜていました。
- 父親の在宅が多かったのでメインは父親でしたが、子どもの様子を聞いて予定を組み立てるのは母親が行っていました。朝の学習を母親が担当する時は、巧緻性も組合わせていました。
- 朝、早起きして勉強や運動の時間を作るようにした他、夕方の時間帯は連絡が取れないことを職場に伝え、業務を調整していました。
- 仕事の帰宅後~夕飯までの時間が我が家の勉強タイムでした。小学生の上の子と同じようにリビングに向かい合い、私は食事の支度をしながら2人の勉強を見て毎日バタバタな時間帯でしたが、1人でやるより誰かと一緒に勉強するほうが集中出来たようです。
- フレックス制度を利用して、8時~15時30分を勤務時間にして、帰宅後の16時から夕食までの時間(約1.5時間)を子どもとの学習の時間に充てました。
- 年中の夏休み頃から仕事を大幅に減らし、在宅勤務で可能な範囲にとどめました。学校の情報収集や説明会等で時間がとられたのと、子どもの帰宅後はさまざまな遊びを一緒に行いたいと考えたため、仕事は午前中のみに絞りました。
私たちも、授業で行った内容をしっかり身につけていただくために、家庭学習の進め方について、効果的な方法を提案してきました。
- できれば朝早く起きて学習する習慣をつけていただきたい。そして、ラジオ(テレビ)体操をぜひ行っていただきたい
- 勉強時間は30分でも構わないので継続して行うこと。そしてペーパーだけの学習にならないよう、具体物やカードを使った学習も取り入れる
- ペーパーは枚数ではなく、1枚の内容を大事にし、自分で考えて解く習慣をつける。また、どのように解いたかを説明させる
- 夏休みには、夏にしかできないいろいろな体験をさせる。特に自然に接する機会が少ない都会の子どもたちには、時間を作って海・山・川での自然体験を多く持たせていただきたい
- 難しい過去問に挑戦する前に、基礎学力を徹底して身につける
- お手伝いをたくさんさせ、料理の際にはレシピなどを書かせることも大事
次は、恵比寿本校室長の島津から「面接試験の準備」についてです。
- 面接試験に向けて準備するうえでアドバイスはありますか?
-
- 婦でよく話し、お互いに学校のどういった点が優れていると思うのか、子どもについてどのように見えているのか、家族で大切にしたいものは何か、言葉に出す機会を多く持っていればどのような角度から質問されても答えられると思います。ただ、「これだけは、この思いは、学校側に伝えたい」ということは明確にしておき、いただいた質問の中で話せなかった場合に、織り込んで伝えられるようにできると良いかと思いました。
- 志望校の過去数年分の質問内容の把握と、夫婦の目線合わせを実施しました。お話しする内容を丸暗記はせずに、キーワードはおさえて自分の言葉で話せるようにしました。
- 子どもは自信がないとはぐらかすことがあったので「思った通り答えて大丈夫」という自信や安心感を持たせようと心掛けました。それには本人の心の成長が必要だったので、夏休み前半は焦らずにさまざまな体験から自信をつけることを大切にしました。徐々に大人からの質問にも自分らしく答えるようになり、本番では良さを発揮して本当によく受け答えをしたと親ながら感心するまでになりました。型にはまった応答練習はせず、本人が不安な気持ちを乗り越えるために何が必要かと親が考え努力したことが良い結果になりました。
- 子どもに対して面接練習も必要ではありますが、それよりも子ども自身に自信を持たせてあげる方が大事だと思いました。それは、どの学校も目上の人である面接官の先生と話すときのマナーを守りながらも、物おじせずにコミュニケーションを図れる力を見られていると感じたからです。
- こぐま会の面接練習がありがたかったです。緊張感に慣れること、場数を踏んで自信をつけることが大切だと実感しました。
- 我が家の志望校はとにかく父親を重要視されていることが知られていましたが、まさにその通りでした。面接中に父親から子どもへ話す機会や、子どもが父親の答えについてどう思うか答える機会があり、子どもが父親に対して委縮していないか、日常的に会話できているかがポイントなのかなと感じました。母親が子どもとの生活についての質問に答えている際も、答えの内容よりも子どもの表情をご覧になっており、日常生活について嘘偽りなく話せているかどうかご覧になっていたのかもしれないと感じました。
願書がご家庭の良さをアピールする最初の機会であるのに対し、面接は実際に顔を合わせ、お話を通してご家庭をより深く知っていただく第2の機会といえます。緊張感のある中ですが、学校への理解と想い、ご家庭の考えを後悔のないようにしっかり伝えましょう。とはいえ緊張すると覚えたことを忘れてしまったり、中には想定していない質問をされる場合もありえます。一つひとつの質問に対して答えを丸暗記するよりも、要点をまとめておいてそれを伝えられるようにすると、さまざまな質問に対応しやすいでしょう。また面接は相手との対話の場でもあります。コミュニケーションの基本としての受け答えがきちんと成り立っているかということも心に留めておいてください。お子さまは「思ったことを自分の言葉にできる」「会話を楽しめる」こと、保護者さまは「認識を夫婦で共有する」「飾らず具体的に伝える」ことを意識すると相手に伝えやすいかもしれません。面接では、親子の雰囲気も重視されていると感じます。学校側が、嘘のないご家庭の“らしさ”を知る時間だと捉えているからでしょう。ですから、家族間の信頼関係や普段からの距離の近さは大切です。それは受け答えの内容だけではなく、面接の場での家族の空気感や選ぶエピソードからも伝わるものです。もしハプニングが起こってしまったとしても、お互いに表情が固くなってしまうよりも思わず笑みが零れてしまう方が、好印象に捉えらえる可能性が高いと思います。自分の番だけに集中しすぎず、ぜひ他のご家族の方が頑張っている時にも耳を傾け、見守る心を持っていただきたいと思います。
最後は、進路相談室長の齋藤から「学習時間の作り方」についてです。
- 兄弟姉妹のいる中で、どのように学習時間を作りましたか
-
- 仕事の帰宅後~夕飯の間の時間が我が家の勉強タイムでした。小学生の上の子と同じようにリビングに向かい合い、私は食事の支度をしながら2人の勉強を見て毎日バタバタな時間帯でしたが、1人でやるより誰かと一緒に勉強するほうが集中出来たようです。
- 上の子がテレビを見たいと言えば、必ず本人(受験生)も一緒に見るので、勉強する時間も一緒に決めて、時間を合わせて行動していました。
- どうしても上の子が邪魔してきて集中が途切れてしまうため、上の子は夫が、下の子(受験生)は私がという分担を決めて、部屋や場所を分けて勉強していました。
- 上の子が同じ部屋にいると学習がはかどらないので、上の子は上の子で習い事を増やしたり学童を活用したりと、下の子(受験生)と離れる時間を作りました。しかし、上の子にも家庭学習の時間は確保したかったし、下の子(受験生)中心ばかりではよくないので、上の子の時間、下の子の時間、家族で過ごす時間のバランスを考えました。
- 下の子(3歳)がおりますが、どうしても下の子がテレビや本を見ていると上の子(受験生)も気が散ってしまい、兄弟喧嘩になっておりました。夏以降は、私が録音した問題を子供部屋で一人で20分~30分で解くようにしたら朝がスムーズになりました。
- 2学年下の子がおりますが、上の子(受験生)が勉強している間、どう過ごしてもらうのかが一番の課題でした。(本人の勉強より大変でした・・・)
音無しのTV、別部屋での動画鑑賞、一緒にペーパーワークするなど、あの手この手を使いましたがあまり効果なく、ただ2~3カ月続けると下の子も分かってきたらしく、あまり無理を言わずにおとなしく一人遊びをしてくれるようになってくれました。(母としてはそれも胸が痛んだのですが・・・)
お母さまが仕事をお持ちで「時間が思うように取れない」というご相談と同じように、兄弟姉妹関係のご相談を頂くことも多くあります。卒業生保護者の方々の体験談の中から、それぞれのご家庭に合う方法を探せるとよいと思います。まずは部屋を分けるなど、物理的に離すことが可能であればそれに越したことはありませんが、私の一番のおすすめは、早朝、兄弟姉妹がまだ寝ている間に学習に取り組むことです。朝、脳がクリアな状態での1時間の学習は、夜の3時間に匹敵します。いろいろな意味で貴重な時間になることをお伝えしています。早起きは始めこそ辛いですが、習慣にしてしまうと何倍にも利点があります。
入試はもちろん、小学校入学後も活動は午前中がメインです。先日ある学校の先生から、新入学早々に遅刻したり朝から居眠りするお子さまがいるというお話を伺いました。意欲的に周りに興味関心を持ちながら貴重な小学校6年間を過ごせるよう、それぞれのご家庭で時間の工夫が必要なのだと感じます。
- 読み・書き・計算はまだ早い!
こぐま会代表 久野泰可 著「子どもが賢くなる75の方法」(幻冬舎)
 家庭でできる教育法を一挙公開
家庭でできる教育法を一挙公開
子どもを机に向かわせる前に実際の物に触れ、考えることで差がつく。- 食事の支度を手伝いながら「数」を学ぶ
- 飲みかけのジュースから「量」を学ぶ
- 折り紙で遊びながら「図形」を学ぶ
- 読み聞かせや対話から「言語」を学ぶ

KUNOメソッド こどもがかしこくなる絵カード(幻冬舎)
幼児の日常生活の中にある学びをカード化!
おうちで体験できるKUNOメソッド子どもたちの生活の中でできる学習経験を、ご家庭でより実践しやすいようにカード化いたしました。お求めは、SHOPこぐま・こぐま会ネットショップ ・全国の書店・各書籍ECサイトにて