週刊こぐま通信
「室長のコラム」2021年度私立小学校入試総括(4)
行動観察はどう変わったか
第754号 2021年1月22日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

昨年10月の740号のコラムで、11月に行われる入試を次のように予想しました。
11月に入ってから行われるペーパー試験や行動観察試験がどのように変わるのか、あるいは変わらないのか・・・注目しています。コラム735号(「今年の入試はどのように行われるのか」)で予測したように、ペーパー試験は基本的にはそれほど大きな変化はなく行われると思いますが、行動観察についてはその形式に大きな変化があるのではないかと考えています。密を作らないように配慮するはずですから、相談を長時間させるような行動観察はないと思いますが、学校側もいろいろ工夫して、これまでの行動観察で見ようとしていた観点は外さないで活動させるのではないでしょうか。前にもお伝えしたように、その形式のヒントは過去問の中にあるはずです。30年近くさかのぼれば必ず何かヒントが見つかるはずです。
こうした私たちの予想が適切だったかどうか検証が必要です。いま実際に行動観察がどのように行われたかを学校別に分析していますが、やはり私たちの予想通りの試験だったといえるでしょう。そこで、主要女子校の2021年度入試で行われた行動観察について具体的に見てみましょう。箇条書きにしてみると以下のようになります。
- A校
- 【集団テスト】
1. 手先の巧緻性「箸つかみ」 / 2. 準備運動 / 3. 指示行動 / 4. 言葉遊び「しりとり・3音のもの」 / 5. おり紙を使った制作 / 6. 形を使った制作 - B校
- 【行動観察・個別テスト】
1. 身体を使ったジャンケン / 2. 塗り絵 / 3. 口頭試問(個別) - C校
- 【行動観察・個別テスト】
1. ひも通し / 2.音の理解 / 3. 魚釣りゲーム - D校
- 【集団テスト・行動観察】
1. 制作「マラカス作り」 / 2. 行動観察「指示行動」 / 3. 行動観察「ボール送り」 / 4. 行動観察「動物模倣」 / 5. 校内見学 / 6. みんなでお話 - E校
- 【集団テスト・行動観察】
1. 準備運動 / 2. 運動 / 3. 手先の巧緻性「おり紙」 - F校
- 【集団テスト・行動観察】
1. 制作「絵画」 / 2. 制作「指示の聞き取り」 / 3. 行動観察「運動」 / 4. 親子活動「手遊び」 / 5. 親子活動「ジャスチャーゲーム」 / 6. カードゲーム - G校
- 【集団テスト・行動観察】
1. ジャンケンゲーム / 2. 指示運動 / 3. 指示行動 / 4. 手先の巧緻性「おり紙」 / 5. 行動観察 - H校
- 【個別テスト・行動観察】
1. 制作「けん玉作り」 / 2. 個別テスト / 3. 手先の巧緻性 - I校
- 【個別テスト】
1. 手先の巧緻性「エプロン結び」 / 2. 手先の巧緻性「箸つまみ」 / 3. 手先の巧緻性「色ぬり」 / 4. 手先の巧緻性「はさみ切り」
【集団テスト】
1. 連続運動 / 2. 縄跳び
【行動観察】
1. 絵本・紙芝居読み聞かせ / 2. パターンブロック / 3. 自由遊び / 4. 八百屋の店先 - J校
- 【個別テスト】
1. 手先の巧緻性「箸つまみ」 / 2. 絵画
【運動】
1. 運動「身体バランス」 / 2. 指示行動
【行動観察】
1. ジャンケンゲーム / 2. 挨拶ゲーム / 3. 創作ダンスと発表 - K校
- 【運動】
1. 連続運動
【制作】
1. バッグ作り
学校ごとにいろいろ工夫して行っていることがわかります。それをまとめてみると次にように総括できると思います。
- 密を作って集団活動をするようなこれまでのやり方はほとんど見られない。相談する機会を設けている学校もあるが、これまでのようにそれぞれの課題をグループに与え、何を作るのか、どう作るのか、それを使ってどう活動するのか・・・といったような、相談することに重きを置いた内容ではなかった
- 手先の巧緻性や、ぬり絵・絵画といったように、個別の取り組みを中心とした課題が多かった
- かつてよく行われていた、身体を使った指示行動やゲームなどを復活させて取り上げる学校が増えた。その中でも、じゃんけんゲームが数校で出されている
- 集団で相談し、協力して何かを完成させるという課題よりも、個人の取り組みを見ようとする課題が多かった。その課題は、運動的な指示行動と絵画制作的な課題の2つに分けられる
では、ある学校でどのように行われたかを2つほど紹介しましょう。
【D校】
- 1. 制作「マラカス作り」
-
※材料:ビーズの入ったプラ容器(半透明のプラビーズ・・・緑・黄・ピンク)・プラスチックスプーン・紙皿・ペットボトル・金と銀のシール5枚位ずつ(の半分の形)
※机は低いので、床に靴を脱いで座って行う
- ビーズをスプーンで3杯すくって紙皿に移す。
- 紙皿に移したビーズのうち、黄とピンクのビーズだけ1つずつ手でペットボトルに移す。
- 美女と野獣のゆっくりした曲が止まったら、止める。
- 金銀のシールをペットボトルの半分より下に好きなように貼る。
- 2. 行動観察「指示行動」
-
※作ったマラカスを使って、靴は履かずにその場に立って行う。
- 先生が持っている傘の状態によって、マラカスを振ったり止めたりする。
・体の前にさす(台風)→マラカスを強く振る
・普通にさす(雨)→マラカスを普通に振る
・傘を閉じる(やむ)→マラカスを振らない
- 先生が持っている傘の状態によって、マラカスを振ったり止めたりする。
- 3. 行動観察「ボール送り」
- 真中に穴が開いた布を4人で持ち、顔がついた軽いボールを落とさないように、みんなで協力して、布の上を転がしたり、おうちまで運んだりする。 ※ボールには泣いた顔がついていて先生は「まるちゃん」と呼んでいた。
- まるちゃんを右回りに転がして、タイコの音で反対まわりにする。(何度か繰り返す)
- 最後に、まるちゃんのおうち(段ボールで作ったお家)まで運び、布を傾けておうちの中に入れてあげる。
- 4. 行動観察「動物模倣」
- ひもを床に置いて、先生と同じ形を作る。その形の中で動物模倣をする。
丸い形 →「池だからカエルになりましょう」
四角い形 →「氷だと思ってペンギンになりましょう」
長四角の形 →「木だと思ってヘビになりましょう」
渦巻 → ? - 最後に自分の好きな形を作る → 先生が何を作ったか聞きに来る
- ひもを床に置いて、先生と同じ形を作る。その形の中で動物模倣をする。
- 5. 校内見学
-
※先生1人+4人の子ども。みんなで1列になって、プールや音楽室を見学する。
- 音楽室でいろいろな楽器の音を聞く(木琴・鉄琴など数種類)
「どれが好きか?」「なぜ好きか?」を聞かれる。※先生が木琴で「さんぽ」を演奏してくれた。「触れなくてごめんね。今度やろうね」
- プールでは、「プールに入りたい?」「ハロウィンはどうだった?」などのお話もした。※高さを変えられる仕組みの説明をしてくれる。折り紙でカボチャが折ってあり「1年生はカボチャ1つ分の水の深さで怖くないよ」
- 音楽室でいろいろな楽器の音を聞く(木琴・鉄琴など数種類)
- 6. みんなでお話
- お友だち同士、好きなお話をしてくださいと言われ、お話をする。
「この学校に来たことある人」
「魚釣りゲームをやったことある人」
「1人ずつ何が楽しかったかお話ししてくださいね」
校内見学を含めて6つの課題が課せられました。制作課題にしても運動課題にしても、自分たちでやるべきことを話し合って決めるのではなく、すべて教師側から決められて課題をこなす形になっています。個人の取り組みが観察されていたのだと思います。3のボール送りは4人でやっていますので、協力関係が求められます。6.の「みんなでお話しをする」課題は会話能力を見る問題だと思いますが、「好きなお話をしてください」ということで、ある目的を持ってみんなで意見を出し合う相談ごととは違いますので、コロナ禍以前の行動観察における話し合いとは趣が異なります。
別の学校ではこのような課題になっています。
【G校】
- 1. ジャンケンゲーム
- 先生と子どもで、一斉にじゃんけんをする。先生は手だが、子どもは足で行う。「最初はグー」はなし。勝ちとあいこは立って、負けたら体操すわり。途中でルールが変わる場合もあり。全部で3回くらい行う。

- 2. 指示運動
-

- 青いラインが引いてあり、行きは手を肩→バンザイを繰り返しながらスキップ
- 向こうの青いラインを越えたら方向転換して帰りは普通のスキップで戻る
- 終わったら列の最後に並ぶ。 ※先生は見本で1周見せてくれるが、子どもは2周続けて行う。(忘れたら先生が教えてくれる)先頭以外は後ろ向き体操すわりで待ち、自分の番が来たら先生が声をかけてくれる。前の子が戻ってきたからといってすぐ行かず、先生に言われてから出発しないといけない。4人グループ。 ※この後、一斉のスキップも行った。
- 3. 指示行動
- 色がついたリボンを渡されておなかの前で蝶結び。
(できなければ先生が手伝う。リボンは赤・ピンク・緑・黄・白でつるつるした触感) - 先生が言ったものの色が、リボンと一緒なら立って、手たたきジャンプ
(先生が「止めてください」と言うまで。5回くらい。それ以外の時は体操座り)
 ※さくら(ピンク)・桃(ピンク)・牛乳(白)・雪(白)・イチゴ(白)・ブロッコリー(白)・きゅうり(緑)・バナナ(黄色)など。終わったら先生がリボンを回収する。
※さくら(ピンク)・桃(ピンク)・牛乳(白)・雪(白)・イチゴ(白)・ブロッコリー(白)・きゅうり(緑)・バナナ(黄色)など。終わったら先生がリボンを回収する。
- 色がついたリボンを渡されておなかの前で蝶結び。
- 4. 手先の巧緻性「おり紙」
-
※おり紙を配られる。ペーパーは机の端に置く。
- テレビを見ながらテレビの先生と同じ色(赤)でおり紙を折る。
(家の半分が裏にある形)
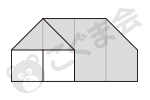 ※手元だけ映っていて、説明付き。同時進行で一緒に折る。「右側を折って・・・」などの左右の指示もあった。
※出来たら机に置いたままにする。その後青い折り紙で好きなものを折る。時間が短く終わった子はいない。(おそらく次の課題の準備時間として行っている)これも机に置いたままにする。
※手元だけ映っていて、説明付き。同時進行で一緒に折る。「右側を折って・・・」などの左右の指示もあった。
※出来たら机に置いたままにする。その後青い折り紙で好きなものを折る。時間が短く終わった子はいない。(おそらく次の課題の準備時間として行っている)これも机に置いたままにする。
- テレビを見ながらテレビの先生と同じ色(赤)でおり紙を折る。
- 5. 行動観察
-
※四角のジョイントマットの上に、3.で使ったリボンが置いてあり、自分の色のところに行き、ジョイントマット1つに1人が立つ。
- みんなで相談して「森のクマさん」の振り付けを考える。
- はじめ(前奏部分)は膝の屈伸の振り付けにする
- お友だちに聞こえる声で話すが、大きすぎる声で話さないこと
- お友だちと近づいたり手をつないではいけない

5つある課題のうち、1~3.までが運動課題、4.は折り紙を指示通りに折る課題、最後の5.の課題がみんなで相談して「森のくまさん」の振り付けを考える課題で、これだけは話し合いが必要ですが、約束にあるように「大きすぎる声は出さない」「お友だちと近づいたり、手をつないだりしてはいけない」など、密を作らない状況の中で行われました。
このように学校側もいろいろ工夫をして、学力以外の子どもの様子を観察しようとしたのが2021年度の行動観察の流れであったように思います。指示をしっかり聞き、最後まで頑張りぬく、ひとりひとりの物事への取り組みが評価されたのは間違いありません。
今年秋の入試を予想するためにも、2021年度の各学校の出題内容を正確に分析しておかなければなりません。
※次回の更新は2月5日(金)です