週刊こぐま通信
「室長のコラム」予想される入試問題
第740号 2020年10月9日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

首都圏の私立小学校の願書受付が終了し、面接も始まりました。これから「withコロナ」時代の初めての入試が行われます。今年の入試に関しては学校ごとに詳しく情報を集め、来年以降受験される皆さまに正確な情報をお伝えしなければなりません。何が変わって何が変わらなかったのか・・・その上でこれからの入試のあり方を予想しなくてはなりません。面接試験が終わった神奈川県の学校の様子を聞き取り調査してみると、それほど大きな変化は見られませんが、やはり2カ月以上に及ぶ休園期間中の家庭生活のありように関する質問が多い傾向が見られます。
11月に入ってから行われるペーパー試験や行動観察試験がどのように変わるのか、あるいは変わらないのか・・・注目しています。コラム735号(「今年の入試はどのように行われるのか」)で予測したように、ペーパー試験は基本的にはそれほど大きな変化はなく行われると思いますが、行動観察についてはその形式に大きな変化があるのではないかと考えています。密を作らないように配慮するはずですから、相談を長時間させるような行動観察はないと思いますが、学校側もいろいろ工夫して、これまでの行動観察で見ようとしていた観点は外さないで活動させるのではないでしょうか。前にもお伝えしたように、その形式のヒントは過去問の中にあるはずです。30年近くさかのぼれば必ず何かヒントが見つかるはずです。ある学校の過去問を見てみましょう。
<A校 過去問>
- 行動観察「猛獣狩りごっこ」(出題年度多数)
- 先生の指示通りの振り付けで、音楽に合わせて踊りながら歌う。
「♪猛獣狩りに行こうよ!猛獣狩りに行こうよ!(手を膝にポン)鉄砲だって持ってるもん!(片手を前に伸ばし、片手は腰に)槍だって持ってるもん!(投げる真似)あ!ゴリラだ!」
動物の名前を言われたら、その名前の音の数のお友だちで集まりグループを作る。
トラ→2人 / ゴリラ→3人 / ライオン・オオカミ→4人 / マントヒヒ→5人 / フタコブラクダ→7人 など
- 先生の指示通りの振り付けで、音楽に合わせて踊りながら歌う。
- 行動観察「集団制作」(2008年度入試)
- 5人ほどのグループで、協力して街を作る。
材料:紙テープ(赤・緑・白)、コピー用紙、セロハンテープ、段、ボール、ウレタンのつみ木
1. 細くちぎった紙を床の上でつなげて道を作る。どんどんつなげて道が広がってきたら、ほかのグループとつなげる。 2. 段ボールやつみ木を使ってトンネルや家を作り大きな街にする。 3. 一定時間遊んだ後、みんなできれいに後片付けをする。
- 5人ほどのグループで、協力して街を作る。
- 行動観察「リズム遊び」(2011年度入試)
- 先生のタンバリンの音に合わせて行進しながら輪になる。
1. 「大きなタイコ小さなタイコ」の歌を歌いながら、「ドーン、ドーン」や「トントントン」のところで、音にあわせて足を踏み鳴らしたり、手を叩いたりする。 2. 回数が進むにつれて、自分の手を叩く、お友だちと手を合わせて叩く、1人でジャンプするなど、振り付けが変わっていく。
- 先生のタンバリンの音に合わせて行進しながら輪になる。
- 行動観察「忍者ごっこ・自由遊び」(2015年度入試)
- 最初に、抜き足・差し足・忍び足の歩き方と、頭を上下させずに歩くすり足の歩き方を教わる。課題の間、その歩き方を使い分けて指示通りに行動する。
1. 川渡り
床に置かれた飛び石を跳んで、向こう岸まで渡る。川に落ちたり、ワニに食べられたりしないように気をつける。※飛び石は、滑り止めのついた薄いマットで、直径30㎝ほどのもの。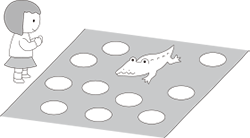 2. 的当て
2. 的当て
けむり玉(マジックテープがついたボール)を的に当てる。当たると忍者の先生から「当たりましたね」と言われる。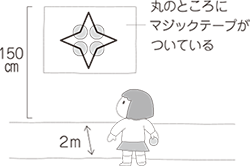 3. 忍者屋敷作り
3. 忍者屋敷作り
大きめの柔らかいつみ木、布、気泡入り緩衝剤、段ボールを使って、みんなで忍者屋敷を作る。 4. 自由遊び
1~3の課題をそれぞれ4~5分行い、終わったら自由遊びをする。
太鼓の合図で自由遊びをやめ、お片付けをして整列・退室する。
- 最初に、抜き足・差し足・忍び足の歩き方と、頭を上下させずに歩くすり足の歩き方を教わる。課題の間、その歩き方を使い分けて指示通りに行動する。
1. 川渡り
<A校 過去36年間の出題一覧>
| 1985 | 模倣(指の屈伸) 運動(音に合わせスキップ) 指示行動(音の数だけ集まる) |
|---|---|
| 1986 | 運動(ケンケン、行進、音に合わせてスキップ、平均台) 行動観察(玉入れゲーム、おやつ) |
| 1987 | 行動観察(劇遊び、おやつ、自由遊び) |
| 1988 | 運動(ケンパー、スキップ) 指示行動(音による指示行動) 行動観察(ハンカチ落とし、おやつ、模倣ダンス、自由遊び) |
| 1989 | 運動(アザラシの真似、平均台、リトミック) 行動観察(歌を歌う、ハンカチ・ちり紙の検査、ハンカチ落とし、おやつ、グループ遊び) |
| 1990 | 行動観察(インディアンごっこ:迷路・ボール投げ・箱の積み上げ・大きなパズル作り、歌と踊り、集団制作) |
| 1991 | 行動観察(発表、しっぽ取りゲーム、集団制作、協調性、自由遊び) |
| 1992 | 行動観察(集団制作、協調性、ジャンケンゲーム) |
| 1993 | --- |
| 1994 | 行動観察(忍者ごっこ:忍者歩き・手裏剣投げ・城遊び・フープ渡り・大きなパズル作り・お片付け) |
| 1995 | 行動観察(背の順に並ぶ、自由遊び、着せ替え、お片付け、ゲーム、協調性) |
| 1996 | 行動観察(ジャンケンゲーム、集団制作、おままごと、お片付け) |
| 1997 | 行動観察(自由遊び) |
| 1998 | 行動観察(同頭音のものをみんなで言う、集団絵画、的当て、ドミノ倒し) |
| 1999 | 運動(リズム行進) 行動観察(つみ木遊び、輪投げ) |
| 2000 | 行動観察(猛獣狩りごっこ、集団制作、自由遊び) |
| 2001 | 運動(ヘビ縄跳び) 行動観察(電車ごっこ、自由遊び) |
| 2002 | 指示行動(楽器の音を聞いて動く) 行動観察(ゲーム、自由遊び、風船遊び) |
| 2003 | 運動(平均台、フープ渡り、ボール投げ) 行動観察(猛獣狩りごっこ、自由遊び) |
| 2004 | 行動観察(テーマ遊び、お片付け、集団制作、つみ木遊び) |
| 2005 | 行動観察(動物模倣、集団制作、ごっこ遊び) |
| 2006 | 行動観察(自由遊び、模倣ダンス) |
| 2007 | 行動観察(自由遊び) 指示行動(先生について移動する、ケンケン等) |
| 2008 | 行動観察(集団制作、集団遊び) |
| 2009 | 行動観察(猛獣狩りごっこ、自由遊び) |
| 2010 | 運動(行進、動物模倣) 行動観察(自由遊び) |
| 2011 | 行動観察(リズム遊び、自由遊び) |
| 2012 | 行動観察(リズム遊び、お弁当作りやハイキングごっこなどの課題遊び) |
| 2013 | 行動観察(動物園ごっこ、お家作り、課題遊び) |
| 2014 | 行動観察(グループ作り、電車作り、自由遊び) |
| 2015 | 行動観察(忍者ごっこ:川渡り・的当て・忍者屋敷作り、自由遊び) |
| 2016 | 行動観察(模倣体操、レストラン) |
| 2017 | 行動観察(指示行動、ランド) |
| 2018 | 行動観察(グループ作り、お店屋さんごっこ) |
| 2019 | 行動観察(ジャングルごっこ:動物模倣・猛獣狩りごっこ、お家作り) |
| 2020 | 運動(ケンパー) 行動観察(おみこし作り、自由遊び) |
時代を反映し、また学校側が蓄積したテスト結果の分析を踏まえて、出題内容や方法も変化してきています。この中に、今年行われる行動観察のヒントになるものがあるはずです。
ところで、ペーパー試験はどうなるでしょうか。これについては密を作らずできるため、従来通り行われるはずですが、2カ月間の休園措置を学校側がどう捉えるかによって、出題の内容や方法に変化がみられることも予想できます。休園期間とそれに続く分散登園のことをどう受け止めるかということですが、活動を通して学んでいく経験が今年の子どもたちは少なかったのではないかと、多くの学校が考えていますから、年々難しくなっていくペーパー問題を基本問題に戻すことは十分考えられます。「withコロナ」の時代の子どもの成長をどう受け止めるかということですが、一般的に考えて、今まで以上に難しい問題が出される状況にはないと思います。その意味で、本当に身についた基礎学力を見る問題が増えていくのではないかと思います。ただ、この10年間の問題の流れは引き継がれていくはずですので、どんな傾向にあるのかをしっかり踏まえた最後のまとめをしていかなければなりません。多くの学校の入試問題を分析してみると、最近の傾向がわかります。以下にまとめましたので、これを参考に最後の点検をしっかり行ってください。学習ポイントも明記します。
| 未測量 | 1. シーソー | 四者関係が基本です |
|---|---|---|
| 2. 単位の考え方 | 広さくらべ、長さくらべが基本。あるものを1と考えた場合の比較の方法が問われます | |
| 3. つりあい | 仲立ちを媒介としたつり合いが基本です | |
| 位置表象 | 1. 右手・左手 | 自分以外の視点から見た左右関係が理解できるかどうか |
| 2. 四方からの観察 | つみ木を使った四方からの観察が主流です | |
| 3. 地図上の移動 | 3つの質問形式に慣れてください | |
| 4. 飛び石移動 | 追いついたり出会ったりする問題もありますが、出来具合はコマの動かし方にかかっています。その基本を繰り返し練習してください | |
| 数 | 1. 数の総合問題 | さまざまな種類の質問に答えるために、聞き取りがしっかりできるかどうかがポイントです |
| 2. 一対多対応 | 他の数の操作と複合することが多い課題です。特に数の増減と複合する場合が多いです | |
| 3. 交換 | 交換の約束で使う「=」の意味には「重さが同じ」「交換」「値段が同じ」がありますが、「重さが同じ」から始めるのがよいと思います | |
| 4. 数のやり取り | 数の違いを同じにする方法と、同じ数からやり取りした結果の違いを求める2つのタイプがあります | |
| 図形 | 1. 図形構成・分割 | センスを育てるためには実物を使うことが大事です |
| 2. 対称図形 | 折り紙を使った課題を中心に、線対称・鏡映像の課題があります | |
| 3. 重ね図形 | 2つの重なり方をしっかり学んでください | |
| 4. 回転図形 | 「回転」は現在の入試の一つのテーマです。いろいろな回転問題と関連させて学習してください | |
| 言語 | 1. 一音一文字 | しりとりをはじめ、言葉つなぎ、言葉づくりなどの一番の基礎です |
| 2. しりとり | 毎年多くの学校で出されます。いろいろなタイプの問題がありますが、逆しりとりができるかどうかで解決します | |
| 3. 話の内容理解 | どの学校でも必ず1題は出されます。質問の形式に慣れてください。今やどんな内容が出されてもおかしくありません | |
| 4. お話づくり | ペーパーを使わない学校では必ず出されます。4枚の絵から始め、最後は1枚の絵でもまとまったお話ができるようにしてください | |
| 生活 他 | 1. 図形系列 | 2つの解き方をしっかり身につけてください |
| 2. 魔法の箱 | 出てくる数だけでなく、入れた数、通った箱など、違う視点からの問いかけにもしっかり答えられるようにしてください | |
| 3. 観覧車 | 回転テーブルなどの応用問題もしっかりやってください | |
| 4. 理科的常識 | 今年は増えると思いますので、理解度をもう一度確認してください |
以上、最近よく出されている問題を領域別にまとめてみました。これからは難しい問題よりも、こうした問題の基礎が何であるかを考えて最後のまとめをしてください。同じ問題は出ませんから、パターンで教え込んでも無駄です。どんな形で問われても対応できるように、考え方の基礎ができているかどうかを確認してください。