週刊こぐま通信
「室長のコラム」「こぐま会Webレッスン」の配信を開始しました
第737号 2020年9月18日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

新型コロナウイルス対策で休校措置をとらざるを得なかった4月から、教育を止めないために映像配信でのオンライン授業を実施してきました。授業再開後は、同じ手法で授業説明や入試情報をお伝えするセミナーなどを行ってきました。もともと「事物教育」と「対話教育」を実践してきたこぐま会ですから、オンライン授業はあくまで補助的な手段として考えています。休校期間中の映像配信の経験を生かし、この流れを何とか活用できないかと現場スタッフと議論を重ねた結果、対面授業をより強化する形でのオンライン授業を推し進める方向を確認しました。つまり、教室での対面授業を受けた子どもたちが復習として使うツールとして位置づけ、教育効果を上げる方法を編み出しました。これまで家庭学習用としてお渡ししていたペーパー教材「こぐまのおけいこ」に加え、毎週の授業のテーマに沿った単元別の指導動画「こぐま会Webレッスン」を配信することにしました。それを、9月から始まったゆりクラス(年中児)ステップ1の学習に沿って、ご家庭にお届けしています。オンライン学習を目的とするのではなく、オンライン学習をこれまでの対面学習に付け加えることを通して深い学びができればと考えています。この「こぐま会Webレッスン」を開始するにあたり、制作から配信までをこぐま会のスタッフでこなすために、いくつかの原則を確認しあっています。
- 目的を明確にすること
- 1年間の授業内容に連動させること
- 年間42週の内容をさらに細分化し、年間96のテーマで学習内容を考える
- 子どもたちの集中力を考慮し、1つのテーマをさらに細かく2~3の単元に分ける
その結果、200程度の小単元での学習になる - 集中力を持続させるために、家庭用の教具を作成して毎回お届けし、その具体物を使った楽しい授業を展開する
それでは「こぐま会Webレッスン」の授業内容をどのように考え決めているか、その流れを具体的にお伝えしましょう。
まず、教室で使用している42週のカリキュラムを年間96の単元に分けます。それを映像配信用にさらに細分化し、カリキュラムを作成します。例えば、教室におけるステップ1の位置表象の対面学習は次のような内容です。
- step1-2 位置表象「上下・前後関係」
-
(1) 電車遊び
- 6人1グループでそれぞれ違ったお面をもらい、1人ずつかぶる。イスを座席に見立て、指示されたところに座る。
- 「~より前の人、立ってください」
「~より後ろの人、立ってください」という指示にすばやく応じる。 - 自分の座っているところを「前から~番目」「後ろから~番目」と発表する。
- 5色のつみ木を見本と同じように積む。
- 5色のつみ木を指示された通りに積む。
- 積んだつみ木を見て、
「~より上には何個ありますか」
「~より下には何個ありますか。それは何色ですか」
「~より上には何個ありますか」などの質問に答える。
- お手本と同じ場所をクーピーペンで塗り、同じ模様を作る。
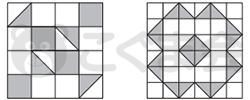
- 5色のつみ木を積んだ見本を20秒見せて見本をかくしたあと、同じように積む。
- 2×2方眼上の4つの果物カードの位置を記憶して、どこに何があったかを再現する。
ここにある (1)電車遊び(前後関係) (2)つみ木を使って(上下関係) (3)模様づくり (4)位置の記憶 の4つの学習を映像学習用に3つの単元にまとめます。
- 位置表象 1 「前後関係」
- 【学習内容】
- ~は前(後ろ)から何番目にいるか?
- 前(後ろ)から~番目にいるのは誰か?
- ~より前(後ろ)にいるのは誰か?
- ~より前で、~より後ろにいるのは誰か?
- 位置表象 2 「上下関係」
- 【学習内容】
- ~は上(下)から何番目にあるか?
- 上(下)から~番目にあるのはどれか?
- ~より上(下)にあるのはどれか?
- ~より上で、~より下にあるのはどれか?
- 位置表象 3 「位置の対応と記憶」
- 【学習内容】
- 方眼上に描かれた模様の見本を見ながら、同じ模様を作る。
- 方眼上に描かれた模様の位置を記憶して、同じ模様を作る。
そのうちの一つ「前後関係」を撮影する際には、次のような進行表を作って授業の撮影を行います。
- 位置表象 1 「前後関係」
- 【撮影順序】
- 6つの模型動物を並べ、前から~番目(後ろから~番目)を探す
- 並んだ位置を言語化する
- あるものを指定し、それより後ろ、(前)を探す
- 並んだ動物を見て、「~より前で~より後ろ」のものを探す
- ペーパー学習
これだけの準備をして撮影に臨みます。複数台のカメラを操作し、子どもたちにとって分かりやすい映像を撮ります。実際の映像をご紹介しましょう。
教室での対面授業では4つの課題を1時間半で行っていますが、映像学習ではそれを3つの小単元に分け、一つが30分以内で終わるように工夫しました。子どもの集中力の持続を考えると、それくらいの時間がちょうどよいかもしれません。ですから、年間の授業単元を96に絞っていますが、その一つ一つが2~3の小単元になっているため、全体では200程度の小単元になっています。
70歳を越えた私が登場するのもあまり格好のよいものではありませんが、メソッドの開発者であり、日々子どもを指導する立場の人間が登場した方が脚本を書く手間も省けていいのではないかと覚悟し、私自身が子どもたちに声掛けをしています。いずれこれを教室に通えない子どもたちに使ってもらう商品として仕上げるためには、若い教師に登場してもらった方がいいかもしれませんが、このプランを言い出した私がやるしかないと心に決めて子どものいない授業を実践しています。すでに96単元のうち12単元の撮影は終了していますが、実際にやってみて難しいのは、
- 準備段階
どんな教材を準備するかに相当時間を割かなければならない - 撮影時
子どもの反応を想定しながらの声掛けや間の取り方などを考えなければならない - 編集時
子どもが興味を持続できるようにどう編集するかの工夫が必要