週刊こぐま通信
「室長のコラム」幼稚園で知育の取り組みが始まりつつあります
第590号 2017年9月1日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

この4月から大阪市特別参与を拝命し、アドバイザーとして保育・幼児教育センターの仕事に参加させていただくことになりました。保育・幼児教育センターで行われた講演会でお会いした、大阪市私立幼稚園連合会の理事の方から、「8月の地域別研修会に講師として登壇していただきたい」という要請を受け、8月28日にモデル授業の実施とともに「大切な幼児期に何をどう学ぶか」というテーマでお話をさせていただきました。セミナー終了後の懇親会では、園長先生方から「幼児教室と違い、今幼稚園で何が問題になっているか」といった貴重なお話やご意見を伺うことができ、私にとってとてもよい勉強の機会になりました。
新しい教育要領では、小学校とのつながりを意識した教育活動を幼稚園にも要請しています。これまでの「遊び保育」の良さを生かしつつ、小学校以降の学習活動の基礎として何をどう学んだらよいのか、教育現場では模索が続きます。「読み・書き・計算」を徹底して行おうという幼稚園もあるようですが、全体としてその前に何をすべきか、いろいろな試みがなされているようです。そうした中で、私が開発した「KUNOメソッド」が注目され、いろいろなところから声をかけていただいています。今回の地域別研修会も、そうした流れの中で行われたものでした。
昨年もちょうどこの日、神戸で行われた「学研全国集会」の分科会の講師として呼ばれ、KUNOメソッドの教育内容と方法についてお話しさせていただきました。今回は、幼稚園の園長先生や現場の先生方が50名ほど集まるということで、理論研修だけでなく、実際の授業も見ていただいたほうがよいと考え、年長児を対象とした授業を50分ほど行いました。研修会が行われた幼稚園に通う年長児14名を対象に、図形学習の基礎である「秘密袋」の授業を行いました。その授業内容は以下のとおりです。
(1) 秘密袋の中に入っている、特徴的な具体物(毛糸玉、タワシ、スプーン、ゴルフボール、ゴーヤなど)が1つ入っている。手探り(触索)をして、どんな感じがするか言葉で表現をする。教師は発言をうながしながら、正解の具体物を示し答えあわせをする。
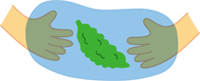
(2) 秘密袋の中に、いくつかの立体つみ木が入っている。教師が「蛇にかまれた!」など形の特徴を示す言葉がけをして、つみ木(下絵:一番右)を見せる。子どもは手探り(触索)をして、同じつみ木を探し、取り出す。
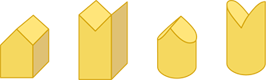
(3) 秘密袋の中に入っている、特徴的な形の色板を手探り(触索)をして、どんな形なのかを調べる。調べた形を紙に描いて表現する。

この授業は、立体学習のひとつとして毎年行っている内容ですが、子どもたちが大変集中して取り組む課題のひとつです。平面や立体の特徴を、視覚的な情報を遮断して触策だけで判別する課題です。言葉で表現したり、同じものを取り出したり、触った形を紙に描いたり・・・と表現方法はいろいろありますが、今回は、触ったものの属性を言葉で表現する最初の内容に、参観者の皆さまが大変興味を持たれたようです。
子どもたちの前に置かれた袋には、いろいろなものが1つずつ入っています。スプーン・歯ブラシ・たわし・テニスボール・ゴルフボール・ビー玉・木製の球・木製の球に毛糸を巻いたもの・立方体つみ木・立方体つみ木の6面に紙やすりを張ったもの・立方体つみ木を毛糸で巻いたもの・ゴーヤなどです。
最初に子どもたちとは、「中を覗かない」「中のものを取り出さない」「右手と左手を入れて触るだけで考えること」を約束して、授業が始まります。
「みんなの袋に入っているものと同じものが、先生の前の箱の中に入っています」
「みんなの袋に入っているものを、先生が箱の中から探すので教えてください」
「でも、名前を言ってしまうと簡単なので、名前は言わないで、どんな形か触った時どんな感じがするか、大きさや重さはどうか・・・そんなことを教えてね」
こうして一人ひとりに、触ったものがどんなものか、クイズ風にヒントを出してもらいました。
子どもたちの中には、すぐにものの名前が分かった子もいるでしょう。でも、名前は言わないでと約束していますので、みんなどう表現したらよいか、最初は戸惑っていたようです。類似したものがいくつかありますので、例えば「丸いもの」だけでは判別できません。「丸いものだけでは分からないからもっと教えて」と問いかけると、「ざらざらしている」「すべすべしている」「軽い」「何か段がついている」(毛糸で巻いてあるのでそう表現したのでしょう)・・・、ゴーヤにいたっては、「きゅうりに似ている、くさい」など、子どもが持っている言語を最大限駆使して表現しようとしていました。
こうした子どもたちの考え抜いた表現を、参観者の皆さまは関心を持って聞いていました。難しくてできないと思っていたことを、不十分ながらも何とか表現しようとがんばっている子どもの姿に、皆さん笑いを伴いながら、感心していたように思います。私も予想以上の反応に、図形の授業でありながら、言語教育の側面も十分にあることを改めて実感しました。
これまでも海外で講演会を行うときは、メソッドの良さを感じていただくために、子どもたちを対象とした授業も行ってきました。理論研修も大事ですが、実際に授業を見ていただくことのほうが、私たちの考えている教育を理解していただくための一番よい方法だと考えています。「事物教育」や「対話教育」の実際を伝える方法として、「モデル授業とセミナー」をセットにした講演会が一番有効だと思います。
この授業の後、園長先生や現場の先生方を対象に「大切な幼児期に何をどう学ぶか」というテーマでお話をさせていただきました。その内容は以下の通りです。
- 1. はじめに - 幼児教育をめぐる現状
- ジェームズ・ヘックマン氏の主張
- 小学校へのつながりを考えた幼児教育のあり方
- 知・徳・体の中でも、知の部分が一番遅れている
- アクティブ・ラーニングの実践要請
- 2. 久野泰可45年間の実践 - KUNOメソッドをどう構築してきたか
- 小学校に入ってからの学力差の問題は、幼児期の課題
- 幼稚園では、伝統的に知育を避ける傾向
- 教科前の基礎教育のあり方が明確でない
- 遠山啓氏の「歩きはじめの算数」から学んだこと ・・・原教科の発想
- ピアジェ,ワロン,ヴィゴツキー,ブルーナーから学んだこと
- 実践の現場から指導方法を構築する
- 授業意図に合わせたオリジナル教具・教材作り
- 3. KUNOメソッドについて
- 3つの教育理念
- 6領域指導 (カリキュラム例)
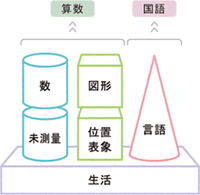
未測量 「重さくらべ」 位置表象 「四方からの観察」 数 「一対一対応」 図形 「立体構成」 言語 「同頭音・同尾音、しりとり」 生活 他 「分類(1) (仲間あつめ)」 - 3段階学習法
- 対話教育の実践
(1) 子どもたち同士の関わりを大事に
(2) 自分の考えていること、感じていることを言葉で表現させる
(3) ある課題をめぐって話し合わせる
- 4. おわりに - 幼児期の基礎教育にとって大事なこと
- 教科学習の内容を薄めてやさしくして下ろさない
- 読み・書き・計算の前にすべきことがたくさんある
- 教え込みの教育は極力避ける
- 事物教育に徹すること
- 対話教育の実践で、言語による「考える力」を育てる
現在私のところに、こうした講演の依頼がたくさん来ています。世の中全体として幼児教育に対する関心の高まりがあるだけでなく、これまで「遊び保育」でよいとしてきた現場の先生方が、やはりきちんとした知育をしなければならないと考え、しかも遊びを土台とした知育の必要性を感じてきているからだと思います。幼児教育に関する理論書はたくさんあります。しかし、実際どのような内容をどのような方法で行うかということになると、実践例が少ないのが現状です。その上、意図的な幼児教育はみな小学校受験対策であり、その対策は詰め込み式のペーパー教育だという偏見に満ちています。こぐま会は受験教育だから私たちには関係ない・・・そうした人たちが大勢いるのが現実です。こぐま会は「小学校受験」にも真剣に対応していますが、しかしそこでの指導は、受験があろうとなかろうと同じ方法で行う、「幼児期の基礎教育」です。その点をしっかり見ていただいている方々から、より具体的な教育の中身を知りたいという要請につながっているのでしょう。
教育改革は具体的でなければなりません。その意味で、3年間の幼児教育を具体的に構成した「KUNOメソッド」は、分かりやすいのかもしれません。「知・徳・体」といわれる幼児教育の三本柱のうち「知」の部分が一番遅れていると感じるのは、私だけでしょうか。その意味でも、「KUNOメソッド」の普及に力を入れなければ・・・と考えています。全国200店を超える書店にオリジナル教材を置いていただいているのは、普及活動にとってとても有効だと思います。幼稚園の現場に「考える力」教育が普及することを願って、今後も活動を続けていきたいと思います。