週刊こぐま通信
「室長のコラム」KUNOメソッド家庭学習の方法
第842号 2023年1月20日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

小学校受験の情報が開示されていないため、何をどう学べばいいのかが、幼児教室に通わないとわからないという現状を学校側はどう考えているのでしょうか。「難しいことを訓練によって身につけなければ受験は無理だ」という雰囲気を作り出しているのは、小学校受験をビジネスと割り切ってとらえる最近の傾向です。受験対策を特別な訓練と捉えた、幼児期の基礎教育とはなじまない方法の指導は、子どもの主体性を育てる教育になっていません。仮にそんなやり方で合格できたとしても、将来必ず大きな壁に直面します。
幼児期の基礎教育を充実させ、その延長上に受験があると捉える対策が望まれますが、現実はそれとは反対の方向に動いていることに深い懸念を持っています。学校側からは入試に関する情報が公開されず、塾側からは難しい課題を行うことが受験対策であり、厳しい指導環境の中に置かなければ合格できないと宣伝されて、それをうのみにしている保護者が多いことに驚いています。
厳しいスパルタ教育で思考力が育つというエビデンスはどこにもありません。まともな幼児教育を守るためには、実績を出さなければなりませんが、「基礎教育を充実させることこそが正しい受験教育である」ことを実証するためには、私たちなりの指導方針を明確にしておかなければなりません。難しいことに取り組む前に基礎をしっかり身につけることが大事だということを実践するために、こぐま会では今年度これまでの家庭学習の方法を見直し、より徹底したシステムとしました。それは、教室での授業の効果を最大限引き出すための家庭学習の方法です。
11月から始まった新年度の学習において、以下の方法を徹底することをばらクラス生の皆さまに要請し、動き出しました。
KUNOメソッドによる家庭学習の手引き
こぐま会での授業とあわせて、ご家庭で復習や理解度のチェックを行うことはとても大切なステップです。ぜひお子さまと一緒に確認してみてください。
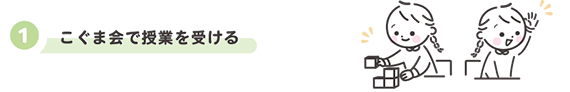
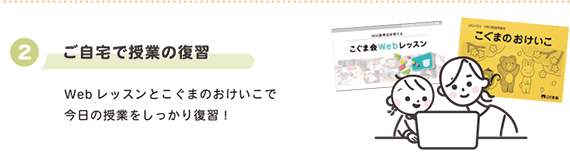
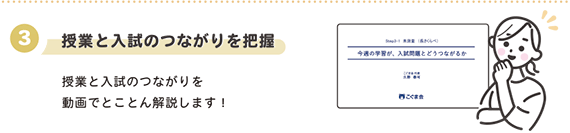
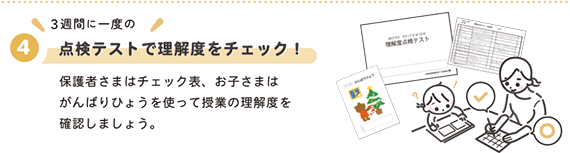
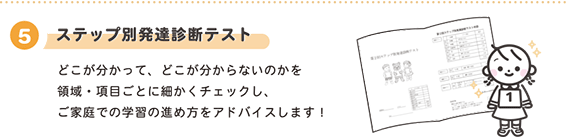
コロナ禍以前は、
- 週1回の授業を受ける
- 「こぐまのおけいこ」で復習する
- ステップごとに行われる「発達診断テスト」を受ける
今年から取り組み始めた新しい試みですが、修正を加えながら最善の家庭学習システムを構築し、どんな形で問われても応用が効く学力を身につけてほしいと願っています。
教科書のない入試ですから、何が基礎で何が応用かがわからない現状がありますが、具体から抽象へといった学びの順序性を踏まえれば、基礎が何であるかは明確です。ラセン型の指導法で、無理なく難問解決に到達できる方法を指導者は明確にすべきです。100ある課題を100通りの方法で解くのではなく、基本となる10の見方を身につければ残りの90の課題は解決できるといった効果的な学習をすべきです。そのためにも「基礎とは何か」を指導者はよく把握すべきです。
- 重版決定!! こぐま会代表 久野泰可 著「子どもが賢くなる75の方法」(幻冬舎)
読み・書き・計算はまだ早い!
 家庭でできる教育法を一挙公開
家庭でできる教育法を一挙公開
子どもを机に向かわせる前に実際の物に触れ、考えることで差がつく。- 食事の支度を手伝いながら「数」を学ぶ
- 飲みかけのジュースから「量」を学ぶ
- 折り紙で遊びながら「図形」を学ぶ
- 読み聞かせや対話から「言語」を学ぶ