週刊こぐま通信
「室長のコラム」応用段階の学習が進行中です
第771号 2021年6月11日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

5月の連休前から始まった応用段階の学習(ステップ5・6)もすでにステップ6に入り、夏休み前までにすべての学習が終わる予定です。応用段階の学習は入試問題に良く出されるテーマが多いので、ぜひ復習をしっかり行ってください。ステップ5・6の内容は以下の通りですが、6月10日現在、ステップ6-2まで進んでいます。
- ステップ5
5-1 未測量 逆対応 5-2 位置表象 四方からの観察(2) 5-3 数 10の構成、交換 5-4 図形 展開図、線対称 5-5 言語 言葉あそび、短文づくり 5-6 生活 他 法則性の理解(2)(推理)
- ステップ6
6-1 未測量 重さのつりあい 6-2 位置表象 地図上の移動、飛び石移動 6-3 数 数の増減、数のやり取り 6-4 図形 重ね図形、回転図形 6-5 言語 話の内容理解、お話づくり 6-6 生活 他 社会的常識(常識)
7月10日までにステップ6-6までを終え、夏季講習会を含めそれ以降の学習では総合問題に取り組み、受験対応のトレーニングに入ります。週1回の学習は、教科前基礎教育(原教科)の内容で構成されています。受験に出る - 出ないに関係なく基礎教育の内容として学習を進めていますが、受験問題は一つの課題が単純に出されるわけではなく、いろいろな領域の課題が複合されて出されますので、1度取り組んだからもう大丈夫ということにはなりません。同じテーマの問題でも問いかけの方法によって難易度が変わってきますし、どんな形で問われても答えていけるような「考える力」を身につけなくてはなりません。その意味で、過去問の中でも難しい問題の集中トレーニングは、子どもの理解度を考えると、この7月から入試までの3~4カ月で行うのが時期として最適です。特に最近の入試傾向を踏まえ、この応用段階の学習に関して10のテーマを上げるとしたら次のようになります。
- 四方からの観察
- 交換
- 線対称
- 観覧車
- 魔法の箱
- つりあい
- 飛び石移動
- 数のやり取り
- 重ね図形
- 回転図形
問題は、この応用段階の学習に進んだ時に「できない」「わからない」と壁にぶつかってしまう場合は、どうしたら良いかということです。できない問題をいくら繰り返し教え込んでも、理解する力が本当に身につくはずはありません。積み上げ学習であれば、どこまで戻ればいいかということが考えられますから、セブンステップスカリキュラムのように「らせん型カリキュラム」であればこそ可能な学習になります。こぐま会のセブンステップスカリキュラムでは、ステップ1から4までの基礎段階の学習の中に躓いた時に戻るべき内容がたくさん含まれています。子ども自身の遊び体験も含め、次のように考えてください。
- 四方からの観察の基礎は、左右関係の理解にあります
- 交換の基礎は、一対多対応の理解が前提になります
- 線対称の基礎は、鏡映像や折り紙を使った紙切りの経験です
- 観覧車の基礎は、自身の経験と法則性の理解が基本です
- 魔法の箱は、数の構成・数の多少の課題が理解できているかどうかです
- つりあいは、交換と同様に一対多対応の考え方が基礎になります
- 飛び石移動は、すごろく遊びの経験が生きてきます
- 数のやり取りは、視点を変えて比較することができるかどうかです
- 重ね図形は、観察力と図形模写が基礎になります
- 回転図形は、立方体の回転の理解が基礎になります
このように壁にぶつかったとき、それを乗り越える手立てを与えてあげなくてはなりません。解き方を教え込んでわかったつもりになっても、その解き方は身につきませんし応用できません。自分で試行錯誤し獲得した力こそ、いろいろな場面で活用できるのです。そう考えて、戻る勇気を持ってください。「難しい問題をやるべき時期に基礎を?」と疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、基礎ができていないところで飛躍はありません。この壁にぶつかる経験こそ、子どもの発達には貴重な経験で、それを教育の力で乗り越えることができたとき、一歩前進し、子どもに自信と主体性が生まれるのです。
- こぐま会代表 久野泰可 オンライン講演会のご案内
「 幼児期の基礎教育と小学校受験 」 - 2021年6月27日(日) 10:00~11:00 LIVE配信!(無料)
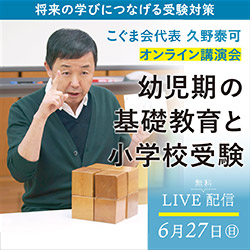 【講演内容】
【講演内容】
1. 最近の小学校受験の傾向
2. コロナ禍の入試で変化したこと・しなかったこと
3. なぜ、ペーパートレーニングだけではだめなのか
4. 受験のための学びが、将来の学習の基礎づくりになるように
※ご視聴にはお申し込みが必要です
※後日録画配信はありません