週刊こぐま通信
「室長のコラム」「入試問題はどのように難しくなっていくのか」
第739号 2020年10月2日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

入試問題を作成する学校の先生方は、さぞかし問題づくりに苦労されているのではないかといつも思います。入試問題の分析を始めてすでに39年が経ちますが、問題づくりの変遷や問題が難問化していくプロセスは、その学校の問題を10年以上分析していくと工夫がよく分かります。学校の先生方が何を根拠に問題を作成しているのかを分析することは、予想問題を考える際には大変大事な作業です。そしてはっきりしていることは、難問奇問を出して子どもたちをふるいにかけようという考え方で問題づくりはしていないということです。子どもの思考力を育てる意味でも、就学前の子どもたちにとって大変良い問題をつくっているように思います。では一体、学校の先生方が問題をつくる際に何を参考にしているのでしょうか。これまでに伺った多くの現場の先生方のお話と実際の問題を分析してみると分かってくることがあります。
- 知能検査の問題
- 小学校低学年で学ぶ内容を念頭に置き、その基礎は何かを考えて問題をつくっている
- 自校で出題した問題の正解率を検証し、難易度を徐々に高めようとしている
- 他校で出された問題を分析し、良いものは取り入れようとしている
- こぐま会発行の「ひとりでとっくん100冊」を教科書代わりに考え、実際の問題づくりの参考にしている
- できるだけパターン化しない問題、他校で一度も出していないオリジナルな問題を出したいと考えている
- 考える力が本当に身についているかを見るため、作業させて答えを導き出す問題づくりを目指している
- 逆から問いかける
- 回転の要素を入れる
- 作業して答えを導き出す問題に変える
- 約束事が理解できるかどうかを通して聞き取り能力を見ようとしている
具体的にお伝えしましょう。法則性の理解の中に「魔法の箱」という課題があります。箱を通過する数の変化を見て、その箱の魔法がなんであるかを導き出し、最後に入れる数が魔法の箱を通過することによってどう変化するかを考える問題です。
- 魔法の箱 (1)
- 真ん中の魔法の箱を通ると数が変わって出てきます。どんなお約束で変わっているかよく考えて、最後に出てくる数だけ「?」のお部屋にをかいてください。
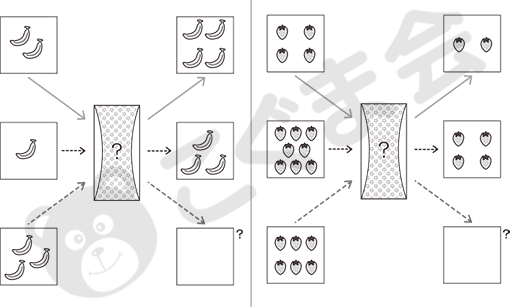
魔法の箱という課題はこれが基本です。
その上で、今度は数の変化の問題として魔法の箱が使われると、変化の法則性はあらかじめ提示され、いくつになって出てくるかを考えさせます。
- 魔法の箱 (2)
- 上のお部屋を見てください。
リンゴがの箱を通ると数が1つ増え、の箱を通ると数が2つ減ります。- 上のお約束で、左にあるリンゴが箱の中を通ると、最後はいくつになって出てきますか。その数だけ右のお部屋にをかいてください。
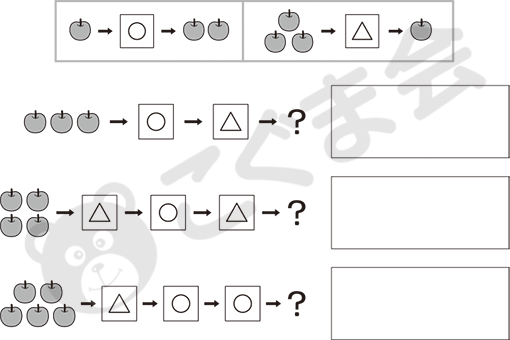
以上2問が魔法の箱の基本ですが、この問題がさらに変化して次のような問題に進化します。それは出てくる数だけを答えるのだけでなく、入れた数を答えるものです。つまり、魔法の箱の逆思考ということになります。
- 魔法の箱 (3)
- 上のお部屋を見てください。
ハートの箱を通ると、数が2個増えます。ダイヤの箱を通ると、数が1個増えます。クローバーの箱を通ると、数が半分になります。- このお約束で箱を通ると、空いている「?」のお部屋にはどんな数が入りますか。その数だけお部屋の中にをかいてください。
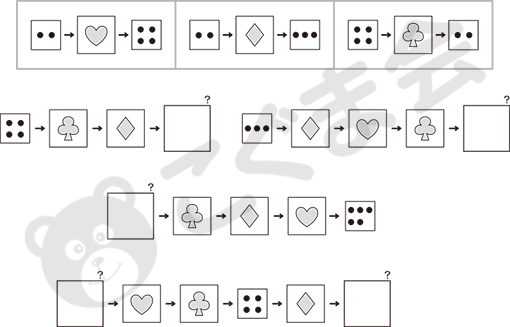
さらに問題が変化すると、今度は出てくる数・入れる数だけでなく、どんな魔法の箱を通過したのか、その箱を問う問題がつくられます。
- 魔法の箱 (4)
- 上のお部屋を見てください。
箱を通ると数や色や形が変わって出てきます。
を通ると数が2増えます。を通ると数が1減ります。×を通ると数が2減ります。カエルを通ると色が黒なら白に、白なら黒に変わります。チョウチョを通るとはに、はに変わります。- 下のように箱を通るとき、空いている「?」のお部屋にはどんな数や色や形が入りますか。鉛筆でかいてください。まず上の段と真ん中の段をやってください。1番下の問題はまだやらなくていいです。
- 1番下の問題を見てください。今度は、どんな形の箱を通るか考えて、かか×をかいてください。
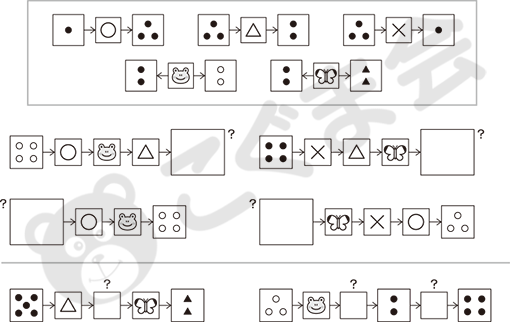
ここには魔法の箱のすべての問題が入っていますが、その中で最後の問題が、数の変化をみてどの魔法の箱を通過したかを問いかける問題です。これも逆思考の問題といえます。ここまで説明すればもうお分かりでしょう。1枚のペーパーを使ってさまざまな角度から質問が可能になり、そうしたことを通して、本当に「魔法の箱」の意味がつかめたかどうかを問いかけているのです。
1日何十枚とペーパーをこなす練習法では問題がパターン化してしまい、ペーパーを見た瞬間に質問の意図を先読みしてしまいます。多くの場合それで解決できますが、同じぺーパーを使って違った角度から質問されるとお手上げになるケースがよくみられます。自分が予想した問題と違った趣旨の問題が出されると、見込み違いで大混乱を起こします。だからこそ1枚のペーパーにこだわり、いろいろな質問を想定した深い学びをしなければいけないのです。
同じように、逆から問いかけている問題は入試問題を探すといろいろあります。
数における逆思考、しりとりにおける逆思考、鏡映像における逆思考、方眼上の移動における逆思考・・・とたくさんあります。それらすべてが、その課題を本当に理解できているかどうかを視点を変えて問いかけようとしているのです。こうした問題が生まれてくるのは、学校側が出題した試験問題の結果を相当詳しく分析しているからだと思います。ある学校の入試問題を10年近くさかのぼってみると、同じ単元の問題が形を変えて出てきます。その流れを見ていくと、問題を難しくしていく方法の一つに「逆」からの問いかけをしていることがわかります。ご家庭で学習する1枚1枚のペーパーを用意された質問だけでなく、どんな質問が可能かを考えてみてください。必ず逆からの問いかけができることに気づくはずです。そうした学習がこれからの受験対策にはとても大事になっていくと思います。論理を鍛えるために必要な「可逆的な思考」は、そうした逆思考の問題によって鍛えられていくはずです。