週刊こぐま通信
「室長のコラム」セブンステップスカリキュラムの授業が始まります
第733号 2020年8月14日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可
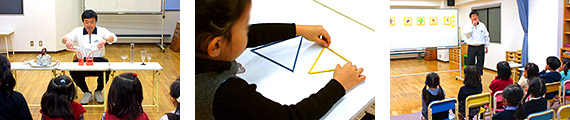
こぐま会では、受験1年前の年中9月からセブンステップスカリキュラムによる週1回の日常授業が始まります。教科前基礎教育の内容として、1年間の指導を6領域・7段階に分け、基礎から応用へと学びの系統性を重視したカリキュラムで指導しています。6つの領域は下図のような関係性を持ちながら小学校で学ぶ教科学習の基礎を身につけるように工夫しています。
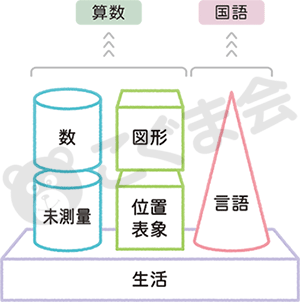
「生活」をすべての基本にしているのは、子どもたちの学びの基礎は生活や遊びにあると考えているからです。「未測量」は「数」の基礎、「位置表象」は空間認識として「図形」の基礎を学びます。また、「言語」は、将来の国語の基礎づくりとして、聞く・話すを基本に、日本語の基礎である一音一文字を中心とした言葉の学習もします。将来の教科学習の基礎として設けた6つの領域はこぐま会独自のカテゴリーですが、この学習内容が小学校入試で問われる「考える力」の育成にも大いに役立っています。それは、知能検査が問題づくりの根拠だった時代から、将来の教科学習の基礎としての問題づくりに変化したことを示しています。学校が出題する問題をどのように分析できるかは、幼児教室で何を学ばせるかということと深く関係しており、このセブンステップスカリキュラムの内容構成が、すべての過去問を分析する方法として間違いなく有効な視点です。過去問を並列して学ばせるやり方では、子どもの「考える力」は育ちません。基礎から応用へときちんとしたカリキュラムで学びの方向性を示すことが、指導者に求められる最低限の専門性でしょう。入試対策は特別な訓練だから過去問だけ取り組ませれば良いと考えるのは間違いです。入試対策だからこそ、幼児期の基礎教育としてしっかりしたカリキュラムで取り組む必要があります。
1年間の学習内容を示した「セブンステップスカリキュラム」は、年中9月から始まり年長10月で終了するようになっていますが、年間の学習計画は以下の通りです。
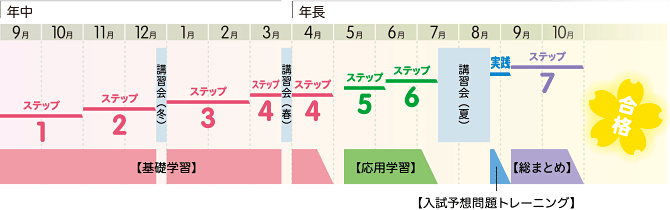
ステップ4までの基礎段階の学習は、年長5月の連休前までに終了するよう組まれています。またステップ5と6の応用段階の学習は夏休み前までにすべて終了します。そのうえで、夏休みの2カ月間と入試直前の2カ月間の合計4カ月間をかけて、総合問題とステップ7の各領域の総まとめを行って入試を迎えます。この、基礎段階の学習・応用段階の学習・総合問題の学習の3段階が、子どもの学びの発達に見合った学習方法であることは、38年間の実践で証明されています。
9月から始まるステップ1の授業は、以下のような内容で行います。
| 領域 | 学習内容 | |
|---|---|---|
| step1-1 | 未測量 | 「大きさ・多さくらべ」 多さの相対化 / 大きさの相対化 |
| step1-2 | 位置表象 | 「前後・上下関係」 前後関係の相対化・系列化 / 上下関係の相対化・系列化 / 方眼上の位置の対応 / 位置の記憶(つみ木・方眼) |
| step1-3 | 数 | 「計数、同数発見、5の構成」 買いものごっこ(命令行動) / 5の構成 / おはじきを数える / カードを使った同数発見 |
| step1-4 | 図形 | 「基本図形とその構成」 基本図形の理解 / 基本図形の構成 / 基本図形の模写 |
| step1-5 | 言語 | 「同頭音・同尾音、しりとり」 一音一文字 / 同頭音・同尾音 / しりとり / 聞き取り練習 |
| step1-6 | 生活 他 | 「分類 (1)」 観点を変えた分類 / わたしは誰でしょう |
入試で出される過去問ほど難しくはありませんが、過去問を自らの力で解くために必要な基本的な事項を、このステップでたくさん学びます。例えば、次の内容は過去問トレーニングにとってもとても大事です。
| 未測量 | 量の相対化・系列化 |
|---|---|
| 位置表象 | 位置の系列化・相対化、位置の対応 |
| 数 | 数の構成 |
| 図形 | 基本図形の構成、図形模写 |
| 言語 | 一音一文字、同頭音・同尾音、しりとり |
| 生活 他 | 生活用品の分類 |
基礎学習ですから、当然事物教育が中心となります。事物を使った試行錯誤の過程で、考える力・学ぶ力を身につけてもらいます。それがのちの応用学習で生きてくるのです。1年以上前の今から、ペーパーだけで過去問に取り組むような対策だけは絶対に行わないようしてください。子どもの考える力を育てる成長の芽を摘み取ってしまうばかりか、学ぶ楽しさを奪ってしまう間違った方法だと思います。
※次回の更新は8月28日(金)です