週刊こぐま通信
「室長のコラム」ステップ4の学習
第664号 2019年3月8日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

先週お伝えしたとおり、今週から始まった「ステップ4」の学習は、入試問題に絡む課題が多く出てきます。これから毎週の授業進度に沿って、どんな内容か、また子どもはどこでつまづくか、そして、それを解決するためにどんな学習をしたらよいか・・・などをお伝えしていきたいと思います。今週は、ステップ4-1「シーソー」の課題です。
- step4-1 未測量「シーソー」
-
2つの場面から3つのものの関係を推理する
(1) 三者関係の理解- じゃんけんゲーム
3人1組になり、総当たり方式でじゃんけんをし、誰が1番勝ったか、2番目は誰か、1番負けたのは誰かを考える。 - 競争
AとBが競争したらBが勝った。
BとCが競争したらCが勝った。
では、AとCが競争するとどちらが勝つか。以上のことを人や車を使って考える。 - すもう
2.と同様、3人の中で1番勝った人をさがす。
- シーソーのカードを使って、シーソーの2つの場面から、3つのものの重さの関係を推理する。
- シーソーのカードを使って、シーソーの3つの場面から、4つのものの重さの関係を推理する。
- 言葉による関係推理(例)「太郎君と花子さんと次郎君の3人が、シーソーで重さくらべをしました。太郎君と花子さんでは、太郎君の方が重かったです。花子さんと次郎君では、次郎君の方が軽かったです。では、2番目に重い人は誰ですか」
- じゃんけんゲーム
テーマは「シーソー」となっていますが、授業内容は「関係推理」の課題です。シーソーはすでにステップ2「重さくらべ」の授業で、実物を使って学習しています。シーソーは関係推理の代表的な課題ですが、その他にも多くの課題があり、入試でもいろいろなかたちで出されています。
カリキュラム(1)の「三者関係の理解」は、じゃんけんや自動車レース、相撲のように、勝ち負けの順位を決めるものです。例えばじゃんけんの場合、普通は3人一緒にじゃんけんをして、最後に勝ち残ったものが一番・・・でよいわけですが、授業では2人ずつ総当り形式で行い、その結果を見て順位を考えます。もちろん引き分けもありますが、2回勝った者、1回勝って1回負けた者、2回とも負けた者となれば順位は決まります。1回だけの結果で判断してしまわないで、全体をよく見て順位の関係付けができるかどうか・・・これが入試でよく言われる「言葉による関係推理」の基礎になります。実際の場面で考えることができなければ、話を聞いただけで判断することは当然できませんから、こうした事物を使った経験を持たせるのです。そうすれば、次のような「言葉による関係推理」の問題も理解できていくはずです。
- 言葉による関係推理
-
太郎君と花子さんとメガネをかけた次郎君が、イチゴ狩りに行ってたくさんイチゴを食べました。
太郎君より花子さんの方がたくさん食べましたが、次郎君は花子さんよりたくさん食べました。- 食べたイチゴが少ない順に×をつけてください。
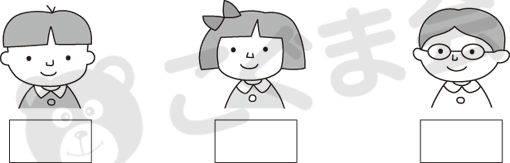
この問題の場合、難易度を変える方法がいくつかあります。例えば、質問の仕方を次のようにすることです。
- 多い順に×をつけてください。
- 2番目に多く食べた人は誰ですか?
- 次郎君より花子さんのほうが少なく食べ、花子さんより太郎さん方が少なく食べた。
- 花子さんは太郎君より多く食べたけど、次郎君より少なく食べた。
「~より多い、~より多い」と説明された場合、多い順は答えやすいですが、少ない順に答えるのは若干難しくなります。同じ状況でも、それがどのように説明されているか、またそれに対する質問の仕方もさまざまですので、いろいろな組み合わせをやってみる必要があります。ところで、関係推理の課題は次のような入試問題として出題されています。
- 場面による関係推理
-
 カンガルーとウサギとネズミの3匹が、2匹ずつ競争をしました。上の3つの絵をよく見て、1番早かった動物に、1番遅かった動物に×をつけてください。
カンガルーとウサギとネズミの3匹が、2匹ずつ競争をしました。上の3つの絵をよく見て、1番早かった動物に、1番遅かった動物に×をつけてください。 - 言葉による関係推理
-
 モモちゃんとチエちゃんとトシオ君が、キノコやドングリやきれいな葉っぱをたくさん拾って袋に入れました。みんな自分が1番たくさん拾ったと言っているので、3人の袋の重さをくらべてみることにしました。
モモちゃんとチエちゃんとトシオ君が、キノコやドングリやきれいな葉っぱをたくさん拾って袋に入れました。みんな自分が1番たくさん拾ったと言っているので、3人の袋の重さをくらべてみることにしました。
チエちゃんの袋はモモちゃんの袋よりも重たかったです。
チエちゃんとトシオ君ではトシオ君の袋のほうが軽かったです。
モモちゃんとトシオ君ではモモちゃんの袋のほうが重たかったです。- 3人の中で1番軽い袋を持っている人に、赤いをつけてください。
関係推理の中の代表的な課題であるシーソーは、「三者関係の理解」が基本ですが、入試では四者関係も出されます。三者関係ができても、四者関係がすぐに理解できるわけではありません。そこには少し壁があるように思います。
- シーソーの重さくらべ
-
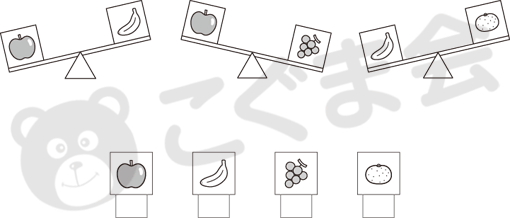 シーソーを使って果物の箱の重さくらべをしました。
シーソーを使って果物の箱の重さくらべをしました。
- 上のシーソーを見て、重い順番に×をつけてください。
この問題は、どのように解いていけばよいでしょうか。2つの方法があります。
- 一番重いものをまず探し、次に残った中で一番重いものを探し・・・を繰り返す
- 一番重いものを探し、次に一番軽いものを探したあと、2番目に重いものと3番目に重いものはどこかで比べているはずなのでそれを探し、その結果から重い順を明らかにする
四者・五者関係でも、シーソーの場面がたくさん出てくる場合は1の方法がよいと思いますが、「残った中で一番重い」ものを探す作業がスムーズにできるかどうかが課題です。1の方法が難しければ2の方法がよいかもしれません。一番重いもの、一番軽いものを探すのは、子どもにとってはやりやすいからです。入試問題はいろいろ工夫されて出てきますが、基本はこのように取り組んでください。入試問題になると、必要でない場面をあえて中に入れることで難易度を高めたり、AがBより重いということを、A1個とB2個が釣り合っている場面を出して関係を考えさせる問題も出てきます。このように、シーソーの問題はいろいろ応用されて出てきますので、なおさら基本がしっかり身についていないといけません。
- シーソーの重さくらべ
-
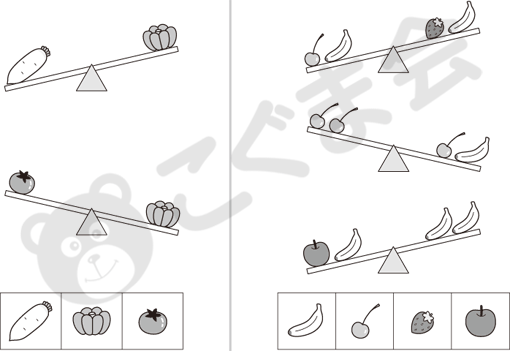 シーソーで重さくらべをしました。
シーソーで重さくらべをしました。
- 左のお部屋を見てください。この中で1番重いものはどれですか。下のお部屋にをつけてください。
- 右のお部屋を見てください。この中で1番重いものはどれですか。下のお部屋にをつけてください。
上の問題は、シーソーの入試問題です。三者関係と四者関係が問われています。三者関係は基本問題ですが、四者関係の方は同じものを左右から下ろして考えなければならないため、やや応用的な問題です。また、こうしたシーソーの基本問題が、次のように「言葉による関係推理」の問題にも変化する場合があります。
- 言葉による関係推理
-
左側の赤い帽子の子どもは太郎君です。真ん中の女の子は花子さんです。右側のメガネの男の子は次郎君です。次のお話を聞いて後の問題に答えてください。
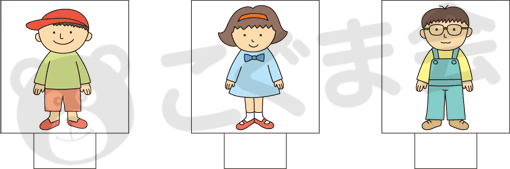 (1) 3人のお友だちでお菓子をたくさん食べました。太郎君は花子さんよりたくさん食べました。次郎君は太郎君よりたくさん食べました。
(1) 3人のお友だちでお菓子をたくさん食べました。太郎君は花子さんよりたくさん食べました。次郎君は太郎君よりたくさん食べました。- たくさん食べた順番に、赤・青・黄色のおはじきを下のの中に置いてください。
(2) 今度は3人で背くらべをしました。次郎君は花子さんより背が低かったです。でも次郎君は太郎君より背が高かったです。- 背の低い順番に、黄色・青・赤のおはじきを下のに置いてください。
-
クマ、ゾウ、カバ、3匹の動物がいます。次のお話を聞いて後の問題に答えてください。
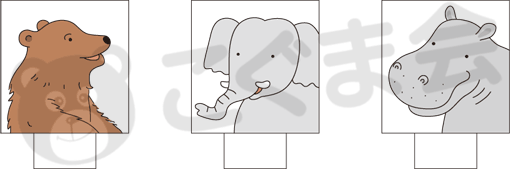 (1) 3匹の動物で重さくらべをしました。カバとゾウをくらべると、カバはゾウより軽かったです。クマとカバをくらべると、クマはカバより軽かったです。
(1) 3匹の動物で重さくらべをしました。カバとゾウをくらべると、カバはゾウより軽かったです。クマとカバをくらべると、クマはカバより軽かったです。- 体重が重い順番に、赤・青・黄色のおはじきを下のの中に置いてください。
(2) 今度は、学校からそれぞれの家までの距離をくらべました。カバの家はクマの家より学校の近くにあります。ゾウの家はクマの家より学校の遠くにあります。- 学校から家が近い順番に、赤・青・黄色のおはじきを下のに置いてください。
これまで紹介した関係推理の問題に関して、子どもがどこでつまづくかを箇条書きにしてみましょう。
- 三者関係はできるけれど、四者関係になるとできない
- 「一番重い」「一番軽い」はできても「3番目に重い」となると分からなくなってしまう
- 「言葉による関係推理」が「話の内容理解」の中に出てくると、間違いが目立つ