週刊こぐま通信
「最新入試問題で求められているものは何か?」その他:常識(ものの数え方) (光塩女子学院初等科)
第33号 2006/03/02(Thu)
齋藤 洋
齋藤 洋
- その他:常識(ものの数え方)(光塩)
- ※リンゴや皿、鉛筆が見本の絵にある。
問.この3つの見本と同じ数え方をするものを、たくさんの絵の中から探して、その見本についているのと同じ印をつけて下さい。
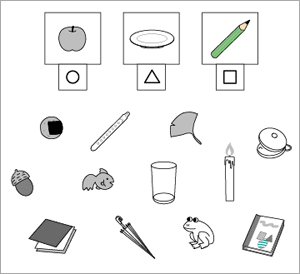 ものの数え方の問題です。いろいろな学校で出題されていますし、典型的な小学校入試の問題なのですが、一時期ほとんど出題されなくなり、最近また出題が多くなってきました。
ものの数え方の問題です。いろいろな学校で出題されていますし、典型的な小学校入試の問題なのですが、一時期ほとんど出題されなくなり、最近また出題が多くなってきました。日本語では、ものを数える時、特定の助数詞(接尾語)を使います。小学生になれば習うことですが、日常的に使用しているはずの数え方については、小学校入試でも常識問題として出題されるのです。しかし逆に小学校に入ってからやるような数え方、またそれ以上の数え方は絶対に入試に出されることはありません。
例えば、細長いものを数える時には「本」、紙・板など薄くて平たいものを数える時には「枚」を使います。ごく一般的に家庭の中で使っている言葉です。これは出されやすい問題です。
鳥を「1羽」と数えるのは良く出されます。しかし哺乳類はどうでしょう。大きければ「1頭」、小さければ「1匹」というように使い分けており、どちらも子どもに馴染みのある数え方ですが、厳密にはどこで「匹」から「頭」に呼び方が変わるのか、はっきりしません。ですから幼児には、だっこできる大きさならば「匹」、もっと大きい動物は「頭」と教えるのが一般的のようです。これもずいぶんいい加減だと思いますが、これで憶えてておけばよいということでしょう。
ウサギを「1羽」と教え込むこともあるようですが、子ども達の知るウサギはペットで、家畜としてではないと思いますから「1匹」で問題ありません。
この助数詞というのは、日本の固有語ですから、伝統的に伝えられてきた習慣です。ですから突き詰めると、親でも使わないとても古風な言い方が多く登場します。でも親が使わないならば、子どもが知るわけは無いのです。ですから「箪笥は、1棹」等を教える必要はありません。日常生活で目にするもの、手にするものなどをきちんと意識して数える習慣を大切にしましょう。
上記の問題では、次の数え方の判断を求めています。
リンゴ ・・・個
皿 ・・・枚
エンピツ・・・本
皿 ・・・枚
エンピツ・・・本
子ども達も良く使っている分かりやすいものばかりです。のはずですが、見本の段階で皿を「~個」としてしまう子もいます。また選択肢の中にも迷うものがある場合もあります。例えば大きな木やビン、バットなども「~本」と数えますが、子ども達は必ず迷います。
また出題方法で難しくしたり、迷わせる場合もあります。別の年の光塩では、3つの絵の中で1つだけ違う数え方をするものを探すという問題も出されています。
例)「絵本」「鳥」「ノート」
印象としては「仲間はずれ」です。その感覚ならば、分かっていなくても鳥をえらぶでしょう。しかし順番に数え方を確認していった場合に、絵本は「冊」と数えるのに、ノートを「枚」と数える子が多いのです。たぶん子どもが自分で使っている感覚だとバラバラのイメージなのでしょう。落書き帳のようなものでも、全て描きこんだら大切にとっておき、時々何冊たまったか数えてみると良いでしょう。まとめてみましょう。
- 普段使い慣れている数え方を、親子でチェックする
- 同じ数え方をするものをたくさん考え、しっかり整理する