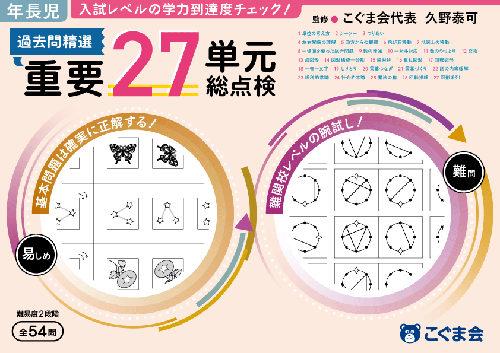週刊こぐま通信
「代表のコラム」海を渡るKUNOメソッド
第938号 2025年10月28日(火)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可
 こぐま会のKUNOメソッドは、直営教室だけでなく、国内の提携教室や保育園・幼稚園にも提供しています。受験・非受験に関係なく、このメソッドは幼児期の基礎教育、特に将来の主要教科の土台作りとして実践し、評価されてきました。それだけではありません。事物教育・対話教育を通して、主体的な「学ぶ力」を育てることも大事にしてきました。また、現在文部科学省でも検討している「幼小一貫教育」の連続したカリキュラム作りにも挑戦し、小学校3年生まで完成させ、実践しています。
KUNOメソッドによる幼児教育が、教材・教具を通して海外の人々の目に留まり、「ぜひわが国でも導入したい」という要請を受けて、現在、東南アジア諸国を中心に駐在する日本人および現地の子どもたちにメソッドを提供しています。
こぐま会のKUNOメソッドは、直営教室だけでなく、国内の提携教室や保育園・幼稚園にも提供しています。受験・非受験に関係なく、このメソッドは幼児期の基礎教育、特に将来の主要教科の土台作りとして実践し、評価されてきました。それだけではありません。事物教育・対話教育を通して、主体的な「学ぶ力」を育てることも大事にしてきました。また、現在文部科学省でも検討している「幼小一貫教育」の連続したカリキュラム作りにも挑戦し、小学校3年生まで完成させ、実践しています。
KUNOメソッドによる幼児教育が、教材・教具を通して海外の人々の目に留まり、「ぜひわが国でも導入したい」という要請を受けて、現在、東南アジア諸国を中心に駐在する日本人および現地の子どもたちにメソッドを提供しています。
最初は韓国でした。こぐま会の教材を九州の書店でご覧になった韓国の方が、ぜひこの教材を韓国の幼稚園に広めたいということで、500園近い幼稚園に教材を提供しました。その後、中国でも提携教室を作り1,000名近い子どもたちに学びを提供しましたが、現政権の政策として民間の教育機関はすべて閉鎖ということで、撤退しました。その後バングラデシュ・インド・台湾でも提携教室に提供しましたが、政治的な規制や人材育成の問題で撤退を余儀なくされました。そんな経験を経て、現在シンガポール・ベトナム・タイ・インドネシア・トルコの5か国で、提携教室や幼稚園にメソッドを提供しています。 ではなぜ海外に出ていくのか。
少子化の影響で日本での教室運営が先細っていくという懸念はありますが、決して生徒集めのためや教材販売のために出ているのではありません。ほとんどすべてが、KUNOメソッドの教育理念に賛同し、導入の要請があって海外に出ていったというのが本当の理由です。そのうえで、KUNOメソッドが世界に通用するのかどうか、言語や文化の違う国々でも、私の開発したメソッドが現地の子どもたちにも意味のあるメソッドとして通用するのか、それを知りたくて、多くの国で講演会や模擬授業を通じて教育関係者に評価を求めてきました。幼児教育に対する思いは国によって確かに違います。また、教材で使う絵カード1枚についても検討が必要になってきます。牛は使えないけど豚は使えるといったように、宗教上の制約などもあります。そうした文化的な違いはあるにせよ、考える力を育てるKUNOメソッドの内容と方法にどの国の幼児教育関係者からも高い評価をいただいたことは大変光栄なことで、自信を持ちました。日本発のプログラムが海外に広まっていけば、「世界に通用するKUNOメソッド」として、今後活動の輪を一層広めていくことができるのではないかとひそかに期待しています。
日本の子どもたちが減少していく中で、海外に出て子どもを獲得するという意味ではなく、私たちの願いは、日本で生まれたこのメソッドが世界の子どもたちに広まっていってほしいということです。
 世界の子どもたちに「KUNOメソッド」の学びを
世界の子どもたちに「KUNOメソッド」の学びを
国内・海外からの実践報告