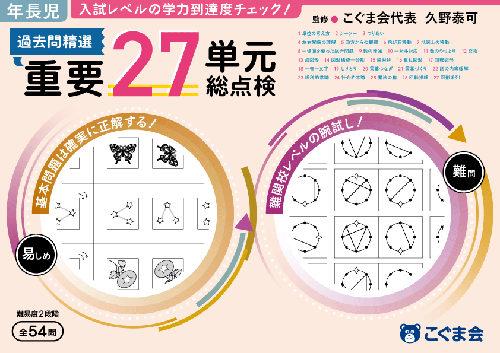週刊こぐま通信
「代表のコラム」広島での講演会でお伝えしたこと
第937号 2025年10月22日(水)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可
 10月12日(日)に、こぐま会のKUNOメソッドを提供している広島の大木スクールを訪問し、今年2回目の講演会を行いました。新年度から年長クラスに通う子どもたちの「学力診断テスト」の実施に合わせ、入試問題の分析とKUNOメソッドの教育内容と方法をお伝えしました。日曜日とあって、お父さまの参加が目立ちました。今回は「あと伸びする子になる正しい幼児教育とは」というテーマで、これから1年間どんな考え方で受験対策を進めればよいのか、私たちの考える指導法をお話しさせていただきました。
10月12日(日)に、こぐま会のKUNOメソッドを提供している広島の大木スクールを訪問し、今年2回目の講演会を行いました。新年度から年長クラスに通う子どもたちの「学力診断テスト」の実施に合わせ、入試問題の分析とKUNOメソッドの教育内容と方法をお伝えしました。日曜日とあって、お父さまの参加が目立ちました。今回は「あと伸びする子になる正しい幼児教育とは」というテーマで、これから1年間どんな考え方で受験対策を進めればよいのか、私たちの考える指導法をお話しさせていただきました。
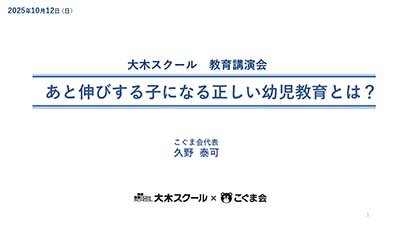
 お伝えした内容は以下の通りです。
お伝えした内容は以下の通りです。
- 今なぜ幼児教育に注目が集まるのか
- 学校側は入試で何を見ようとしているのか
- どんな能力が求められているのか
(A)広島大学附属小学校2025年度入試問題分析
(B)広島大学附属小学校10年間の問題傾向
(C)安田小学校2025年度入試問題分析 - 入試でよく出される27単元の学び
- 主体的な学びを育てるKUNOメソッドとは
(A)教育内容 6領域の学習内容
(B)教育方法 事物教育・対話教育
(C)3段階学習法について - 教科学習を支える「学ぶ力」をどう育てるか
- 幼児期の基礎教育を徹底する中で合格をめざす
実際、大木スクールと提携してからこの10年間で、入試結果にどんな変化が見られたかを副塾長に報告していただきました。 昨年度は広島大学附属小学校に50名、広島大学附属中学校に36名の合格者を送り出すという快挙を成し遂げました。
提携する以前は1桁台の合格者でしたが、それが50名まで伸びたのです。それだけではありません。広大附属中の合格者が、2025年度入試で飛躍的に増えました。小学校入試の抽選で合格できなかった子どもたちが再度中学入試に挑戦し、大勢の子どもたちが合格を果たしているのです。私は、この数字が大変意味のある事実だとお伝えしました。ペーパー主義の教育ではなく、きちんとした幼児期の基礎教育を実践し、入試に望んだ子どもたちの入試結果です。小学校の入試で念願かなわなかった子どもが再挑戦した中学校入試で難関校を突破するという事実は、東京のこぐま会でもたくさん報告されています。あと伸びする教育とは、目先のペーパーでの得点を高めるパターン学習ではなく、事物に働きかけ、試行錯誤し、本物の学力をつける事物教育です。ある私立小学校の先生にお会いした際、「最近の子どもたちの算数の学力が、以前と比べると落ちている」というお話を伺いました。3歳ごろから相当の時間とお金をかけて入試対策をし、試験には合格したものの、入学後に学力が伸びない子どもたちが大勢存在するということはどういうことでしょうか。その理由の一つは、誤った受験対策の結果だと思います。自分で試行錯誤して答えを導き出す経験のない子には本当の「考える力」は身につきません。それだけではありません。毎日何十枚というペーパーをこなすような学びでは、子どもたちの主体的な「学ぶ力」の芽は摘み取られてしまいます。私が「間違った受験対策をしないように」と繰り返し主張していることは、こうした事実が存在するからなのです。
その意味で、私たちが実践している3段階学習法における「事物教育」と「対話教育」はとても大事です。特に教え込みの教育に変わる「対話教育」は重要です。今回の講演会でも、映像を使って学ぶ力を育てる授業の実際を見ていただきました。
セミナー終了後、何人かの方から個別の相談を受けましたが、参加された皆さまからも感想を寄せていただきましたので、ここに少し紹介させていただきます。
- 子供の学びを現時点で小学校受験に限定せず、その後の学びの土台を作るためのものとして考えることが大切だと言うことが良く分かる説明でした。事物を使っての具体的イメージを作る力や言葉を理解できる言葉能力を向上させること、このことを大切にこれからの子供の教育を進めていこうと思います。たとえ小学校受験によい結果がでなくてもこどもに何より大切な学ぶ力が着くように頑張ります。
- 小学校受験がゴールではなく、その後にもつながるような教育を今からやっていくことが大切なことが良く分かりました。自分で考えを言語化する力を培うことができる教育がとても魅力的だなと思いました。
- 幼児教育が大切とぼんやり意識していましたが、KUNOメソッドの内容を聞き、より今の娘たちの育ちを支えていきたいと思いました。私自身小学校で教員をしており、幼少連携の必要性を強く感じています。公教育にもぜひ取り入れて頂きたいと思います。
- 入試ではペーパーテストだけでなく非認知能力を重視する傾向があるお話が印象的でした。身体を使い→手を使い→頭を使うがとても良いと思いました。
- 事物を使った教育の重要性。国立小は抽選があるため合格できるとは限らないが、仮に抽選で落ちたとしてものちに残るものが大事だと思っている。その点でこぐま会の方向性はとてもいいものだと感じた。