週刊こぐま通信
「代表のコラム」就学準備の授業を終えて
第923号 2025年3月14日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

4月に入学する年長児の子どもたちを対象に1月から始めた就学準備クラスも、今週が最後の授業となりました。ばらクラスで学習した内容を踏まえ、1年生から始まる算数・国語の学習に自信をもって取り組んでもらえるように、次のような目標を掲げて「橋渡しの授業」を行いました。
- 国語は読解につながるように音読を徹底する
- 算数は計算を正確に早くやるだけでなく、四則演算の考え方を学び、文章題につながる立式練習を徹底して行う
| 算数 | 国語 | |
|---|---|---|
| 1 | たし算・ひき算って何? | 自己紹介 音読「いろはがるた」遊び |
| 2 | たし算・ひき算の計算法 | 読解「物語文」1 音読 |
| 3 | 隠れた数を探せ | 読解「物語文」2 |
| 4 | かけ算って何? | 読解「説明文」 |
| 5 | わり算って何? | 言葉の学習 長音表記 |
| 6 | かけ算の答えはどう出すの? | 読解「物語文」1 |
| 7 | 文章題に強くなる1 立式練習 | 読解「物語文」2 |
| 8 | 図形課題・時計 | 読解「物語文」3 |
| 9 | 文章題に強くなる2 数式を見てお話を作る(作問) | 読解「物語文」4 |
| 10 | 総まとめ | 言葉の学習 短文作り |
1. 音読が上手にできない子が多い。
女子はすらすら読める子が多い一方で、男子は拾い読みが目立ちました。言葉がどのような音の組み合わせでできているか、また文章がどんな言葉のつながりでできているかということを理解できていないのかと考えると、ばらクラスで行った「一音一文字」の考え方がどれだけ身についているかがとても大事だと思います。
リンゴは「り・ん・ご」ではなく、3つの音の組み合わせで「りんご」という言葉が形成されていることが理解できていないと、一音一音声を出して読んでしまうために、拾い読みになってしまいます。そこで、まず黒板に単語を書き、声を出して読ませる練習をしました。また以前、子ども向けの詩を読み、耳から覚えたその詩を復唱したあと、今度は覚えた文章の文字を見て声を出して読んでみる、というようなこともやってみました。耳から覚えた文章を目で見て読んでみる・・・という方法は、拾い読みをなくす一つの練習法として有効です。日本語の美しい言葉のリズムを身につけるためにも、詩を暗唱することはとても有効な方法だと思っています。
2. 計算のスピードに大きな差がみられる
今回は、ばらクラスで学習した数の学習を踏まえ、四則演算の考え方を学び、そのうえで、たし算・ひき算・かけ算の計算まで練習しました。たし算・ひき算は、10までの範囲で行い、かけ算は「1あたり×いくつ分」の考え方をしっかり学習した後、とりあえず2の段と5の段の九九を暗唱させました。最終授業時には、2の段・5の段以外にも3の段・4の段を発表した子もいました。日本の教科書では、かけ算は2年生で学びますが、シンガポールでは1年生のうちに学ぶようです。日本の場合、かけ算をたし算の繰り返しと考えているのでしょうか。たし算ができたあとかけ算を学び、かけ算ができたあとわり算を学ぶため、四則演算を学ぶために、3年間も費やすのです。子どもたちの生活や遊びを見れば、幼児期にすでに四則演算の数体験はしているはずなのに、3年間もかけて計算指導をしているところを見ると、生活に密着した数の学習という発想は薄いのかもしれません。私は、子どもたちの理解の様子を見ていると、1年生のうちに四則演算の指導は十分できると考えています。なぜなら、幼児期にすべての四則演算の数体験はしているからです。その生活体験に基づいて行うなら可能です。
就学準備のクラスでは、10までのたし算・ひき算と2の段と5の段のかけ算の計算練習までしました。20問の計算問題を早い子は40秒ぐらいで解いていましたが、一方で5分以上かかる子もいます。なぜそんなに時間差が出るかと言えば、最大の理由は指を使って答えを出す子と暗算できる子の違いだろうと思います。こぐま会では、年中の段階から指を使った数の操作は絶対にさせないという方針で指導してきましたが、その成果はこうした計算練習で表面化します。この差は、繰り上がり繰り下がりの学習になるとより明確になり、1年後半から2年にかけて行う2桁・3桁の計算になるとますます計算スピードに差が出てきます。幼児期に指でもなんでも使って答えさえ出せればいいという指導を受けてきた子どもたちは、こうした場面でその指導のいい加減さが露呈してきます。その意味でも、幼児期の最初の数の指導がどういう形で行われたかは大変重要な課題です。
3. 文章題に入る前に、立式の練習をすることの大切さ
シンガポールの学力が世界一だということの理由は考えてみる必要がありますが、日本と比べて大きく違うのは、計算よりも文章題に相当力を入れている点だと思います。私は、日本の算数は計算主義だと以前から言ってきましたが、計算さえできれば算数はわかったと思っていると、高学年になってからの文章題がお手上げになってしまいます。計算主義の算数では、訓練すれば幼児でも四則演算ができるようになりますが、そうした子に次のような問題ができるのか果たして疑問です。
下の式になるように、お話をつくってください。
・4+2 ・4-2 ・4×2 ・4÷2
ほかの3つの式は、身近なテーマでお話できますが、4×2になるとほとんど口を閉ざしてしまいます。なおかつ、少し進めて4×2と2×4の違いを説明する問題になると、ほとんど手がつけられません。文章題の練習に入る前の、このように式を見てお話をつくる練習はとても有効です。
4. 自分で問題を読み文章題を解く練習は、読解の練習にもなる
最後の仕上げは、自分で文章を読み、式を立てて答えを導き出す文章題の練習です。ばらクラスで行ったのは、話を聞いて答えを導き出す練習でしたが、今度は自分で問題文を読み、式を立て答えを導きだす練習です。
(1) 問題文を読み、話の内容を理解する
(2) 式を立てる
(3) 計算して答えを導き出す
という3つの過程を自分で行い解答する作業は、文章をスラスラ読めない子にとっては大変難しい課題でもあります。その意味で、文章題を使って読解の基礎を練習することも十分可能です。
10回の講座を終え、4月から小学1年生になる子どもたちですが、受験を意識して行ってきた10月までの教科前基礎教育と、小学校の算数・国語につながる就学準備の教育をうまくつなげていくことが、「橋渡しの教育」として、とても大事だと思います。そして、幼小一貫教育の理念を貫き、小学校3年生までの指導につなげていきます。
- もうすぐ小学生!
こぐま会の教材を使った就学準備
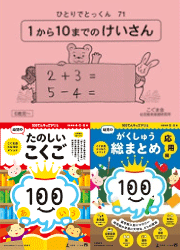 これまで合格を目指して頑張ってきた学習を、4月から始まる小学校での教科学習にスムーズに繋げるために、またより高いレベルでの学習をするための「こぐまオリジナル知育教材」「100てんキッズ」をご紹介いたします。
これまで合格を目指して頑張ってきた学習を、4月から始まる小学校での教科学習にスムーズに繋げるために、またより高いレベルでの学習をするための「こぐまオリジナル知育教材」「100てんキッズ」をご紹介いたします。