週刊こぐま通信
「代表のコラム」運筆練習はなぜ大事か
第921号 2025年2月21日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

私たちが日常行っている「発達診断テスト」は、具体物やカードを使った個別テストとペーパーテストを組み合わせて、学力の診断をしています。このほかに「行動観察テスト」も重要な課題として位置づけ、実施しています。
毎回テスト結果を一人ひとり個別に分析し、いま何が問題か、弱点克服のために何が必要かをまとめ、保護者の皆さまにお伝えしています。
そうした分析を通じていつも感じることは、ペーパーテストで点が取れても具体物を使った個別テストで点が取れない子と、その逆で、個別テストではよく答えられているのにペーパーテストで点が取れない子が何人も見られるということです。両方のテストでまんべんなく点が取れている子は、高得点を取り偏差値も高くなります。 なぜ、テストの種類や質問方法によって結果に違いが出てしまうのか、ここをしっかり見ておかないと効果的な学習ができません。ここ2~3年、そうした目で子どもたちの結果を分析したり、テスト現場の子どもの様子を観察したりしてみると、得点できない子どもの背景がわかってきました。
1.ペーパーテストはできるのに個別テストで点が取れない子の多くは、基本を本当に理解していないけれど、訓練によって「できてしまう」というパターンです。特に「なぜ?」と答えの根拠を求められると答えられない子が多いです。
2.逆に、個別テストで理由もしっかり言え、基本は理解しているのに、ペーパーで点が取れない子の多くは、反復練習が十分できていないということに尽きます。その中身は、「問題を1回で聞き取る力」「記憶力」「作業に必要な運筆力」などがありますが、最近テストの現場を観察してみてはっきりわかってきたのは、「運筆力」がどれだけ身についているかが想像以上に大事だということです。
ペーパーテストでは、質問を聞いてから「はじめ」と言われて取り組みます。その際、線を引いたり囲んだり形を書いたりする作業を通して答えを書き表すわけですが、子どもたちの様子を見ていると、その作業が時間内にできなくて「やめ」となり、問題をいくつか残したまま終わってしまうケースが多いのです。 きわめて単純なことですが、運筆能力が結果的に得点の差につながっていくということです。つまり、「手先の巧緻性」の習得がペーパーテストの結果を大きく左右するということです。集中力の問題でもあるわけですが、作業する技術的な問題を解決しないままペーパーに取り組むと、そうしたことが起こりうるということは知っておくべきです。 もちろんペーパーテストの内容をしっかり理解することが大事ですが、表現する手段としての運筆が得点差に大いに関係があるということをしっかり踏まえ、その対策を取るべきです。わかっていながら得点できない、ここに運筆の問題が大いに関係していることを知っておいてください。
この運筆課題は手先の巧緻性の大事な課題として単独で出される場合もありますが、今回お伝えしたことは、すべてのペーパー作業に関係している話です。これとは別に、運筆単独の問題も大事です。最後に参考までに、2025年度入試で出された「運筆」に関する課題をいくつかご紹介しましょう。
- 1. 運筆・色塗り
-
- 丁寧に、点線をなぞってください。できたら花の真ん中のところを塗ってください。
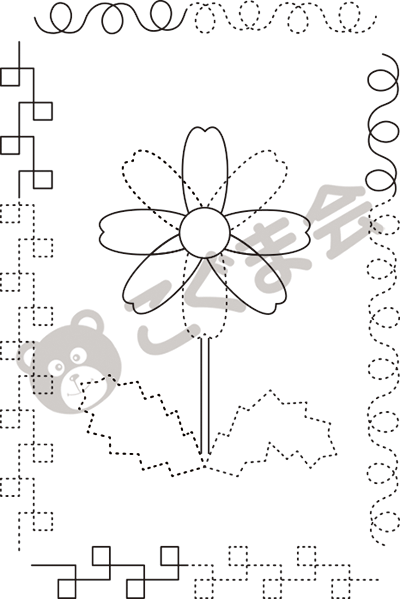
- 2. 運筆・点図形
-
- 左の点線を丁寧になぞってください。
- 右の問題です。左のお手本と同じになるように、右の点をつないでください。上は同じところに〇もかいてください。
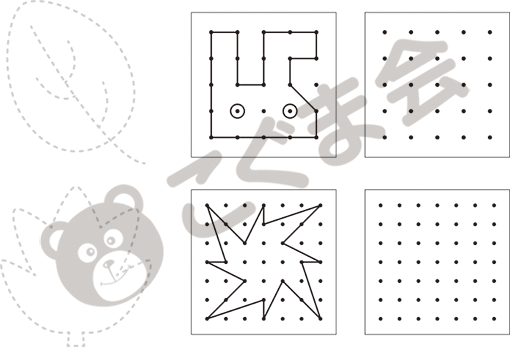
- 3. 運筆・塗り絵
-
風船があります。
- 左下の●からはじめて、風船の模様の▲まで線をかいてください。道からはみ出したり、道の線にぶつからないようにしてください。
- 青の色鉛筆で、風船の中にある3個の模様を塗ってください。はみ出したり、白いところが残ったりしないようにしてください。
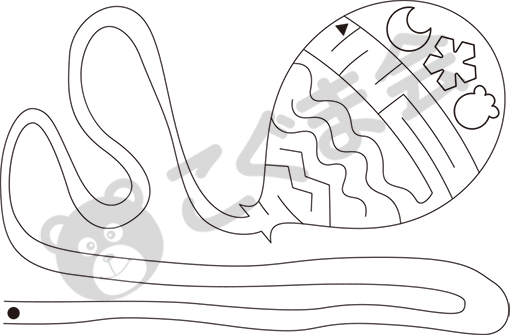
出典: 「東京都立立川国際中等教育学校附属小学校」ホームページ 「過去の適性検査問題等」より。 令和7年度 適性検査(一般枠)の入試問題をもとに作成しています。
- 4. 点図形
-
- 上のお部屋のお手本と同じになるように、下のお部屋の点をつないで形をかいてください。
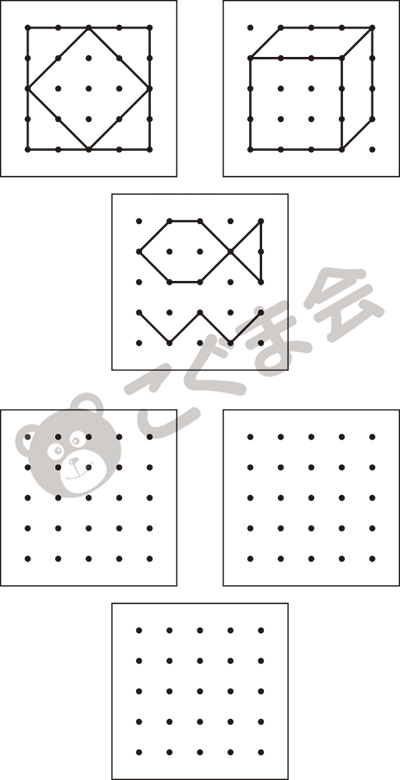
- 5. 重ね図形・図形模写
-
- 左の問題を見てください。透明な紙に形がかいてあります。上のマスを太い線のところで折って重ねると、中の形はどうなりますか。下のマスに形をかいてください。
- 右の問題を見てください。上のお手本と同じように、下のマスに線をかいてください。
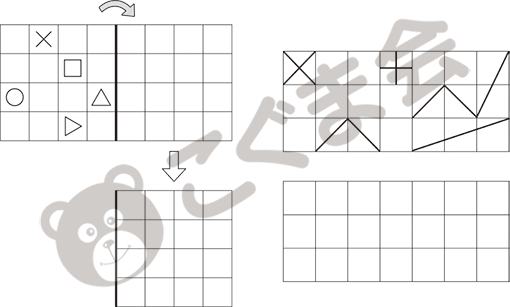
- 6. 回転図形
-
見本
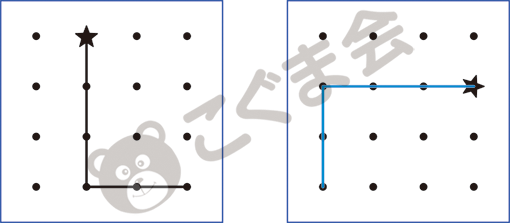
- 上の形が下のように回ると、中の線はどうなりますか。★の位置をよく見て、鉛筆で点をつないでかいてください。
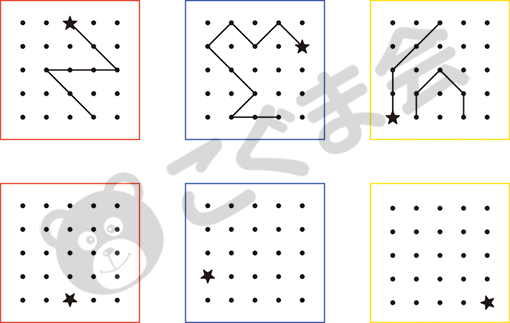
- 読み・書き・計算はまだ早い!
こぐま会代表 久野泰可 著「子どもが賢くなる75の方法」(幻冬舎)
 家庭でできる教育法を一挙公開
家庭でできる教育法を一挙公開
子どもを机に向かわせる前に実際の物に触れ、考えることで差がつく。- 食事の支度を手伝いながら「数」を学ぶ
- 飲みかけのジュースから「量」を学ぶ
- 折り紙で遊びながら「図形」を学ぶ
- 読み聞かせや対話から「言語」を学ぶ

KUNOメソッド こどもがかしこくなる絵カード(幻冬舎)
幼児の日常生活の中にある学びをカード化!
おうちで体験できるKUNOメソッド子どもたちの生活の中でできる学習経験を、ご家庭でより実践しやすいようにカード化いたしました。お求めは、SHOPこぐま・こぐま会ネットショップ ・全国の書店・各書籍ECサイトにて