週刊こぐま通信
「代表のコラム」入試問題をどう分析するか
第920号 2025年2月14日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

毎年秋の入試が終わると、子どもたちから問題を聞き取り、出題された課題を分析してきました。教科書のない入試ですから、この作業をしないと受験生に何をどう学習させればよいかがわからないまま、むやみに難しい課題に取り組ませてしまうことになりかねません。その結果、必要でない課題を子どもに押し付け、子どもたちを追い詰めていくことになってしまいます。どこまで難しい問題に取り組ませるかは、実際に出された問題を分析して明らかにしていく必要があります。現在行われている受験のための準備教育は、子どもの理解度を超え、むやみに難しくする傾向にありますが、それは教育者の責任において厳に慎むべきです。小学校受験が教育的な観点を離れてビジネスチャンスとして受け止められ、さまざまな業種が参入し、今大きな混乱が起こっています。この動きは何としても阻止しなければなりません。 ところで学校側は、入試問題をどういう観点で作成しているのでしょうか。「教科書のない入試」で、一体何を基準に問題を作っているのでしょうか。コロナ禍明けの入試問題を見ると、何か昔に戻ったような変化が見られます。一つには問題を作る先生方の世代交代が進んでいるのではないか、そのためこれまで蓄積されてきたその学校独自の良い問題がどこかに消えていっているようにも思います。私が幼児教室の教師として見てきたこの50年間の入試問題作りは、次のように推移してきました。
- 知能テストが問題作りの根拠になっていた時代
- 受験者が増え、知能テストのような形式的な問題では合否が決まらず、小学校低学年の学習内容を易しくして、ペーパー問題を大量に出していた時代
- 考える力を求める多くの難問が出された時代
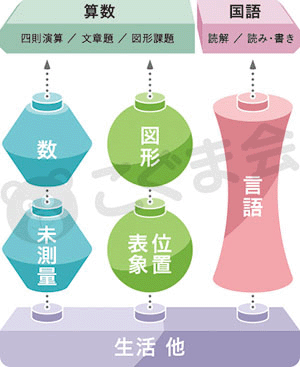
| 未測量 | 単位の考え方/シーソー/つりあい |
|---|---|
| 位置表象 | 左右の理解/四方からの観察/飛び石移動/地図上の移動 |
| 数 | 一場面を使った総合問題/数のやりとり/交換/暗算 |
| 図形 | 図形構成―分割/対称図形/重ね図形/回転図形 |
| 言語 | 一音一文字/しりとり/言葉つなぎ/言葉づくり/話の内容理解 |
| 生活 他 | 常識/魔法の箱/回転推理/図形系列 |
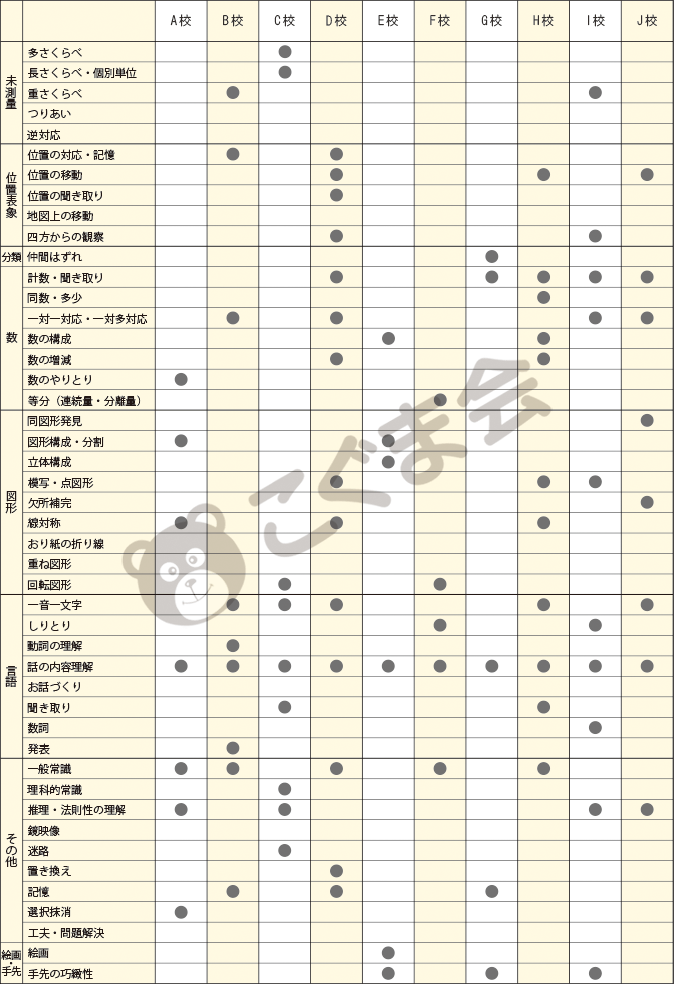
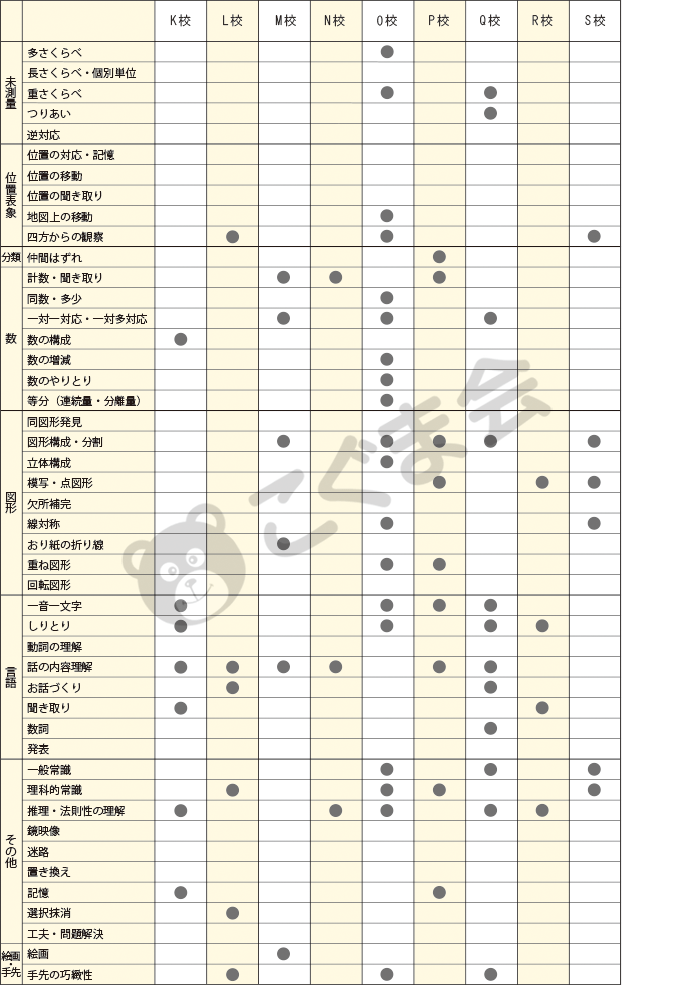 出題傾向は毎年少しずつ変化していますが、最近はさまざまな領域にまたがり論理性を求める問題が増えています。また、「逆しりとり」に象徴されるように、「逆からの問いかけ」が増えています。それだけ学校側も工夫し始めたということですし、数の総合問題や折り紙を使った課題、そしてオセロやトランプやだるま落としにみられるような生活に身近な問いかけや、子どもたちが経験するゲームを素材に問題が作られています。ものごとの関係性をどう捉えるかが考える力の原点になっているように思います。
出題傾向は毎年少しずつ変化していますが、最近はさまざまな領域にまたがり論理性を求める問題が増えています。また、「逆しりとり」に象徴されるように、「逆からの問いかけ」が増えています。それだけ学校側も工夫し始めたということですし、数の総合問題や折り紙を使った課題、そしてオセロやトランプやだるま落としにみられるような生活に身近な問いかけや、子どもたちが経験するゲームを素材に問題が作られています。ものごとの関係性をどう捉えるかが考える力の原点になっているように思います。
大学入試をはじめ、上級学校の入試問題が大きく変化している時代の中で、小学校入試の問題も変化していくことは避けられません。本当に「生きた学力」の育成につながっていくのかどうか、その観点から見ると、必ずしも良い問題だけが出されているわけではなく、いったい何の目的で・・・と思われる問題も実際には出されています。
入試であろうとなかろうと、幼児期の教育課題は将来の学習の基礎づくりです。その意味でも、入試では将来の学び、生きた学力につながる良い問題がたくさん出題されることを期待しています。問題を担当される先生方に、ふるい落とすための問題作りにならないよう切にお願いしたいと思います。
- 読み・書き・計算はまだ早い!
こぐま会代表 久野泰可 著「子どもが賢くなる75の方法」(幻冬舎)
 家庭でできる教育法を一挙公開
家庭でできる教育法を一挙公開
子どもを机に向かわせる前に実際の物に触れ、考えることで差がつく。- 食事の支度を手伝いながら「数」を学ぶ
- 飲みかけのジュースから「量」を学ぶ
- 折り紙で遊びながら「図形」を学ぶ
- 読み聞かせや対話から「言語」を学ぶ

KUNOメソッド こどもがかしこくなる絵カード(幻冬舎)
幼児の日常生活の中にある学びをカード化!
おうちで体験できるKUNOメソッド子どもたちの生活の中でできる学習経験を、ご家庭でより実践しやすいようにカード化いたしました。お求めは、SHOPこぐま・こぐま会ネットショップ ・全国の書店・各書籍ECサイトにて