週刊こぐま通信
「代表のコラム」ゲームのすすめ
第918号 2025年1月17日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

小学校の入試問題がどのように作られているかは、大変関心のあるところです。 私も50年間、小学校入試問題の分析を続けてきましたが、小学校受験にかかわり始めた1970年代以降、学校側が問題制作のために一番参考にしたのは、知能検査の内容でした。その後受験者が増えていく中で、大量のペーパー試験を課しましたが、その内容は、小学校低学年で学ぶ内容を幼児向けに易しくしたような問題でした。その当時は文字を読ませたり書かせたりはしない、数字を使った計算などは出題しないといった暗黙の了解がありました。しかし、ペーパー問題が多く出されるとそれに伴って準備する側も毎日大量のペーパーをこなさなければならず、それに適応できない子どもたちが精神的なバランスを崩し、心療内科や精神科に大勢通う結果になり、現場の医師から警告が発せられました。それを受けて、学校側も一時期ペーパーを無くした時期がありました。しかし限られた時間で評価するためには、個別テストよりペーパー試験のほうが効率が良いということで、それまでの30~40枚のペーパーを使った試験ではなく、8枚前後のペーパー試験として復活しました。その後、ペーパーに加えて行動観察や面接の総合点で合否が決まる試験に代わり、今日まで続いています。
ペーパー試験の内容は、年を重ねるたびに工夫された問題が作られるようになっています。知能検査のように機械的なトレーニングで答えられる問題はだんだん少なくなり、「考える力」を求める工夫された問題が出題されてきました。最近のペーパー問題は以下のような特徴があります。
- 聞く力がどれだけ身についているかを検査する
- 作業能力がどれだけ身についているかを見る
- 論理性を求める問題が増えている
- 生活や遊びで経験することを素材に問題を作成している
- 法則性の理解(オセロ)
- 黒と白のコマがあります。それぞれコマを置いたとき、自分の色で相手の色を挟んでいると、間にある相手のコマを取ることができます。 縦、横、斜めで挟むことができます。
(1) お日様のお部屋を見てください。黄色い枠の中に黒いコマを置くと、白のコマを何個取ることができますか。その数だけ下のお部屋に青い〇をかいてください。 (2) お月様のお部屋を見てください。白をなるべくたくさんひっくり返すには、どこに黒いコマを置けばよいですか。その場所に赤い〇をかいてください。
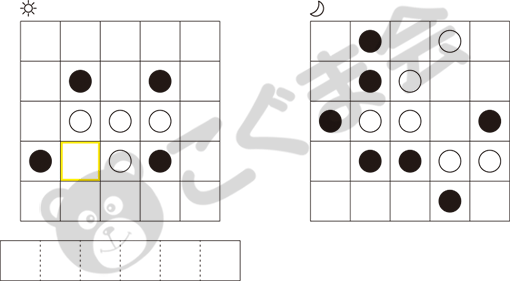
- だるま落とし
- 見本
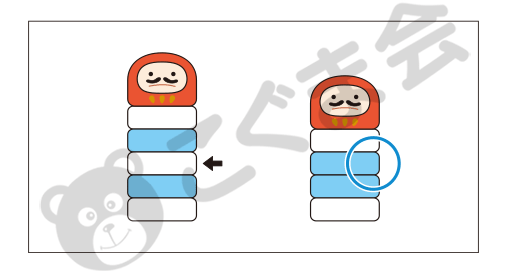
(1) 青いお部屋を見てください。左の矢印のところを叩いて抜くと、ダルマ落としはどうなりますか。右から選んで〇をつけてください。 (2) 赤いお部屋を見てください。左の矢印のところを叩いて抜きました。そのあと下から3番目も抜くと、ダルマ落としはどうなりますか。右から選んで〇をつけてください。 (3) 黄色のお部屋を見てください。左の矢印のところを叩いて抜きました。そのあと下から3番目を抜いて、そのあと下から3番目を抜くとダルマ落としはどうなりますか。右から選んで〇をつけてください。
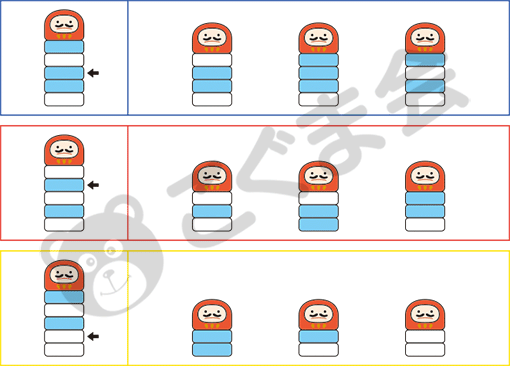
また、以前トランプカードを使った次のような問題も出されています。
- 「数の推理」
- 上の絵を見てください。パンダとウサギが星のカードを3枚ずつ持っています。相手からは持っているカードは見えません。
これから相手のカードを1枚ひきます。ひいたカードを見せ合い、数が多いほうが勝ちです。ひいたカードは自分がもらえます。- ウサギが2のカードをひくと、パンダが勝ちました。パンダは星いくつのカードをひいたのでしょうか。その数だけイチゴのお部屋にをかいてください。
- 今度はパンダが2のカードをひきました。すると今度もパンダが勝ちました。ウサギは星いくつのカードをひきましたか。その数だけリンゴのお部屋にをかいてください。
- 2回勝負をしたあと、2匹が持っているカードの星の数の違いはいくつですか。その数だけバナナのお部屋にをかいてください。
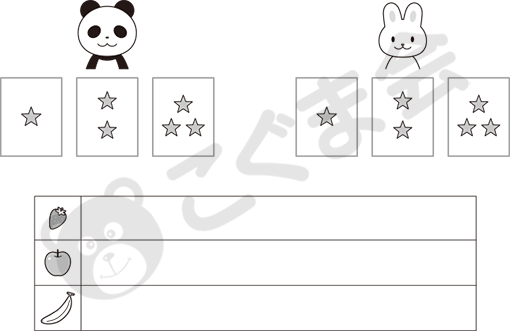
- 図形構成
- 上にある3つのパズルを使って、左の形を作ろうと思います。それぞれどのパズルをいくつ使えばできるでしょうか。使うパズルのお部屋に使う数だけ〇をかいてください。
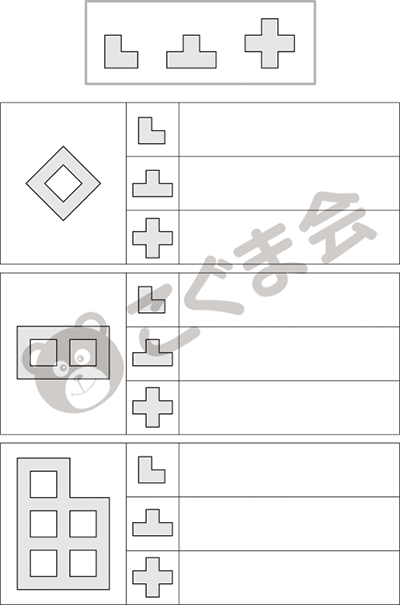
ところで、先週から受験の終わった子どもたちの就学準備クラスが始まりました。ばら(年長)クラスで学んだことを、算数科や国語科の内容につなげる学習です。算数は、数字を使った学習を取り入れ、たし算・ひき算だけでなく、年長児に学習した内容を思いだしながら、かけ算やわり算の考え方まで指導する予定です。先週はたし算・ひき算の考え方を学んだあと、数式を使った計算まで練習しましたが、簡単な計算でも問題を解く時間に大きな差が見られました。取り組んでいる様子を見ると、時間がかかってしまう子の多くが指を使って答えを出そうとしていることです。1分間でできる子もいれば、4~5分かかる子も見られます。簡単な1~10までの計算でこの有様です。これから先、繰り上がり・繰り下がりなど難しい計算になればもっと差は開きます。こぐま会では、こうしたことが予想されるため、年長児の段階で、絶対に指を使わない約束をして数の操作を学んでいます。そうした暗算練習を経験してきた子は、数字を見ただけで具体的な場面がイメージでき、数の操作も頭の中でできるのです。
私は以前、小学校6年生まで算数の授業を担当してきましたが、この就学前の時期の差が後々の学びに決定的な差をもたらすことをたくさん見てきました。ですから入学前のこの時期の暗算能力はとても大事です。しかし、だからといって計算だけ早くできればいいというのではなく、生活場面に即して文章を読んで立式できる能力が伴わないといけません。
具体物や〇などの記号を書いて考えていた時期から数字の世界に導くために、数字を見た瞬間、それまでの具体物や〇などの記号をイメージできるかどうかが問われます。数字の「5」を見てリンゴ5個、ミカン5個、おはじき5個などが思い描けるかどうかはとても大事なことです。数字はきわめて抽象的な約束事です。数字の背後にある量をイメージするために、遠山啓氏はタイルを使った指導法を開発しました。量を土台として数を捉えることはとても大事です。その意味が一番はっきりわかるのは、この就学前の子どもたちの学習の時です。タイルを使った指導は、抽象的な数を映像化しやすい指導法として現在小学校でも採用されています。具体から抽象へ導くだけでなく、抽象から具体へ戻るための橋渡しを就学前にしっかりやっておくことが大事です。その意味で、数字に親しむ経験は大事です。そのための一つの方法として「トランプゲーム」は最適です。ひとりでも遊べますし、2人でも4人でも遊べます。その楽しさの中で、数字(抽象)から具体的場面をイメージできれば、必ず数に強い子に育っていくはずです。
- 読み・書き・計算はまだ早い!
こぐま会代表 久野泰可 著「子どもが賢くなる75の方法」(幻冬舎)
 家庭でできる教育法を一挙公開
家庭でできる教育法を一挙公開
子どもを机に向かわせる前に実際の物に触れ、考えることで差がつく。- 食事の支度を手伝いながら「数」を学ぶ
- 飲みかけのジュースから「量」を学ぶ
- 折り紙で遊びながら「図形」を学ぶ
- 読み聞かせや対話から「言語」を学ぶ

KUNOメソッド こどもがかしこくなる絵カード(幻冬舎)
幼児の日常生活の中にある学びをカード化!
おうちで体験できるKUNOメソッド子どもたちの生活の中でできる学習経験を、ご家庭でより実践しやすいようにカード化いたしました。お求めは、SHOPこぐま・こぐま会ネットショップ ・全国の書店・各書籍ECサイトにて