週刊こぐま通信
「代表のコラム」入試速報(7)
常識問題も多岐にわたっている
第917号 2025年1月10日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

小学校入試で出題される問題は、将来の算数科につながる「未測量・位置表象・数・図形」領域と、国語科につながる「言語」領域がほとんどです。しかし、現在では生活科(小学校1・2年)といわれるかつての理科・社会につながる内容もよく出題されています。身の回りのことについての理解がどこまで進んでいるかということですが、それをこぐま会では「理科的常識」「社会的常識」「一般常識」として括り、入試問題の分析を続けてきました。どちらかというと知識として覚えておかなくてはならない問題で、思考力云々というものではありません。しかし、かなり細かい内容が問われることも多く、実際に経験していないと答えられないこともあります。常識については、日常生活の中で身につけていくことですから、学校側は「豊かな家庭生活を送っていますか」と問いかけているようにも見えます。その意味で、図鑑的な知識だけでは対応できません。
いま手元にある資料の中から、2025年度入試における常識問題がどんな内容であったかを見てみると、理科的常識問題が6校で、社会的常識(一般常識を含む)問題が16校で出されています。その中の典型的な問題をご紹介しましょう。
- 聞き取り(理科的常識)
- これから4人の女の子が好きな花についてお話しします。それぞれどの花が好きなのか、よく聞いてください。
青いお洋服の子が言いました。「私が好きなのは春のお花で、球根で咲くお花よ」
赤いお洋服の子が言いました。「私が好きなのは夏のお花で、大きくて背が高いお花よ」
黄色いお洋服の子が言いました。「私が好きなお花は、花びらがサクラと似ているから秋のサクラとも言われているのよ」
緑のお洋服の子が言いました。「私が好きなのはいっぱい花びらがついている春のお花よ。最後、枯れる前に綿毛が出るよ」- 上の女の子が好きな花を下から選んで、青で線結びしてください。
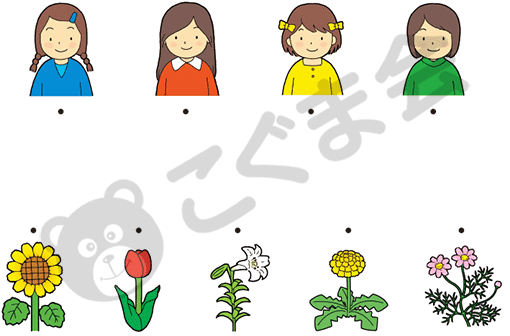
- 理科的常識
-
- 上の絵はどの動物の尻尾ですか。下から選んで、同じ印をかいてください。
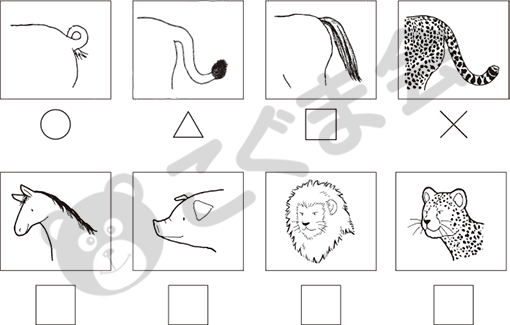
- 理科的常識
-
- 上の絵のように、水が入ったコップを傾けるとどうなりますか。下から選んで○をつけてください。
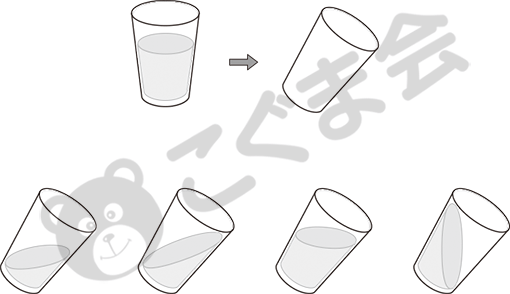
- 常識(季節)
-
- 左上の「鏡餅」からはじめて、季節の順番になるように、カードを置いてください。
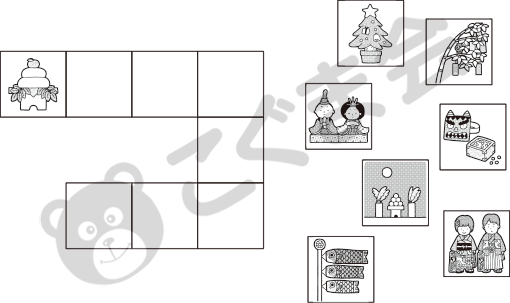
- 常識(季節)
-
- お正月の次にする行事は何ですか。〇をつけてください。
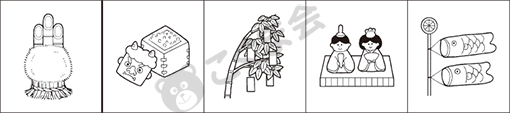
- 常識(季節)
-
- 太い線の四角の中に、アジサイの絵があります。日本には、春、夏、秋、冬の季節があります。アジサイの花をよく見る季節と、同じ季節によく見かけるものや、よくとれて味がよいと言われるものがかかれた絵が、隣の4枚の絵の中に1枚だけあります。その絵を大きく〇で囲んでください 。
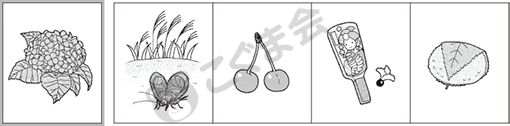
- 社会的常識
-
- この絵の中で、いけないことをしている人を指でさしてください。
また、それはどうしてですか。お話ししてください。
- この絵の中で、いけないことをしている人を指でさしてください。
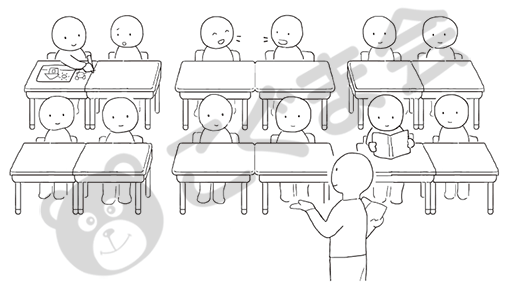
- 社会的常識
-
- この絵の中で、いけないことをしている人を指でさしてください。また、それはどうしてですか。お話ししてください。
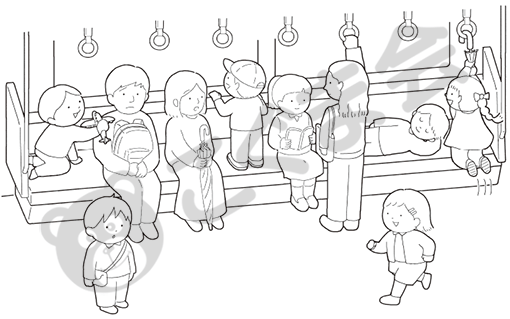
- 常識
- 上のお部屋から下のお部屋まで順番に答えてください。
これから歌が流れます。よく聞いて後の問題に答えてください。
※「もみじ」の音源が流れる。- 今の歌の季節の、次の季節の絵に〇をつけてください。
- ※「七夕」の音源が流れる。
- 今の歌の季節の、次の次の季節の絵に〇をつけてください。
- ※「まっかな秋」の3番の音源が流れる。
- 今の歌に出てきたものに〇をつけてください。
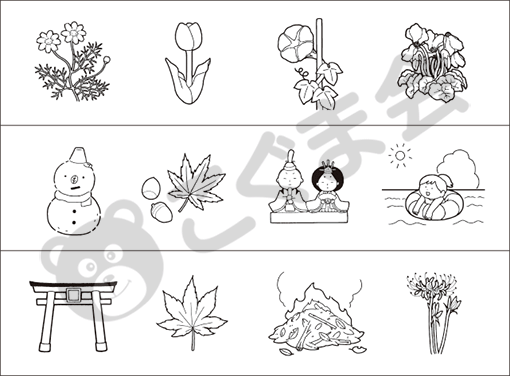
- 常識(昔話)
- ※「こぶとりじいさん」の音源が流れる。
- 今流れた歌はどの昔話の歌ですか。〇をつけてください。
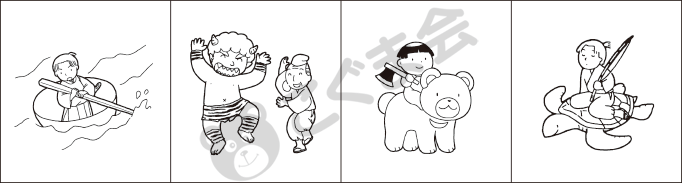
| 理科的常識 | 季節に関する問題/動物に関する知識/植物に関する知識/どこで育つかの問題/どこに住んでいるかの問題/食品と原料の関係 |
|---|---|
| 社会的常識 | 交通道徳/公衆道徳/標識/音の理解 |
| 一般常識 | 数詞/昔話 など |
- 読み・書き・計算はまだ早い!
こぐま会代表 久野泰可 著「子どもが賢くなる75の方法」(幻冬舎)
 家庭でできる教育法を一挙公開
家庭でできる教育法を一挙公開
子どもを机に向かわせる前に実際の物に触れ、考えることで差がつく。- 食事の支度を手伝いながら「数」を学ぶ
- 飲みかけのジュースから「量」を学ぶ
- 折り紙で遊びながら「図形」を学ぶ
- 読み聞かせや対話から「言語」を学ぶ

KUNOメソッド こどもがかしこくなる絵カード(幻冬舎)
幼児の日常生活の中にある学びをカード化!
おうちで体験できるKUNOメソッド子どもたちの生活の中でできる学習経験を、ご家庭でより実践しやすいようにカード化いたしました。お求めは、SHOPこぐま・こぐま会ネットショップ ・全国の書店・各書籍ECサイトにて