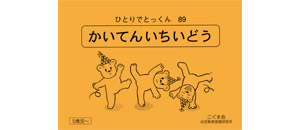週刊こぐま通信
「代表のコラム」がんばれ受験生 (1)
第905号 2024年9月13日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

9月に入り、学校説明会も活発に行われるようになり、首都圏では願書提出も始まった学校もあります。いよいよ2025年度の入試が始まりました。11月1日から始まる都内の入試まで、残すところ40日足らずになりましたので、追い込みに力が入るところですし、模擬テストを受けて学力の完成度に不安があると、焦りばかりが先に立ち、じっくり腰を据えた学習が進められない時期でもあります。どうか、これまでの頑張りを信頼し、落ち着いて試験を迎えてください。ゆとりをもって対策をとるには、最近の入試の現状をしっかり把握しておかなければなりません。ペーパーテストで満点を取れば、どこでも合格できると勘違いしている保護者が多いのは困ります。多くの場合、学力テスト・行動観察・三者面談の3つの柱で入試を行い、その総合点で合否が決まります。学力だけで合否が決まらないのが小学校受験の特徴です。毎日40枚過去問トレーニングをやっても合格できない現実をしっかり受け止めてください。特に最近は行動観察や面接を重視する学校が増えています。コミュニケーション能力や、他者をいたわる気持ち、最後まであきらめず頑張りぬく意志の強さ、仲間とともに一つの目標に向かって頑張りぬく気持ち・・・など、非認知能力といわれる観点も重視されています。学力だけなく、そうした能力も大事だということを理解し、普段の生活を見守ってください。また子育てにおける父親の役割を重視した質問内容が増えていることも見逃せません。
行動観察では課題を与えて集団でどう解決していくかを見るために相談・話し合いの場を設定し、その中で自分の考えを主張するだけでなく、人の話をしっかり聞けるかどうかも大事な観点として問われています。
さて最大の関心事である学力試験はどのように変わっていくのでしょうか。コロナ禍が明けて2年目の入試になりますので、学校側も相当工夫した問題を出してくるはずです。今年の小学校6年生の学力テストで明確になった、基礎学力はあるが、思考力・記述力に劣った子どもたちの現状を見て、学校の先生方は主体的な学びができる子をどう育てるかに関心を持っているはずです。2年も3年もかけて受験対策を行ってきた子どもたちが入学後伸びない現実を見て、受験対策としてやってきた学習の仕方に大きな問題があると感じているはずです。教え込みの指導による機械的なトレーニングによって身につけたうわべだけの学力では、入学後伸びないという当然なことを、現場の先生方は深刻な問題として感じているはずです。ですからトレーニングによってできてしまう問題ではなく、「考える力」を問う問題を出そうと、問題作りに相当時間をかけているはずです。自分で考え、作業し、自分で答えを導き出す学習を積み上げてこない子では、こうした工夫された問題には対応できなくなってくるはずです。
では、思考力を問う問題とはどんな問題なのでしょうか。最近の工夫された問題を見ると、その傾向が見えてきます。そこで、今年受験する皆さんに、最後のトレーニング課題をお伝えしましょう。学校の先生方が問題作りの際に考えるのは次の視点です。
- 生活に密着した問題であるかどうか
- 問題の意図をしっかり聞き取る力があるかどうか
- 問題の指示に従い作業して答えを導き出せるかどうか
- 限られた時間で、答えを導き出せるかどうか
- 視点を変えて物事を考えることができるかどうか
その典型は「逆思考」を求める問題として、さまざまな領域で問われている - 回転の要素をどう盛り込むか
位置関係をイメージする力がどこまで身についているか - 法則性を導き出し、それを適用できるかどうか
考える力の問題として、具体的には図形系列・観覧車・魔法の箱として出されている