週刊こぐま通信
「室長のコラム」子どもの学力はどこまで伸びたか
第866号 2023年8月4日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

7月17日から始まった夏季講習会には大勢の子どもたちがお弁当持ちで参加し、お昼を挟んだ4時間、毎日元気に学んでいます。秋の受験に向けて、午前中は入試レベルの問題に挑戦する思考力育成の学習を、午後は行動観察対策として「自ら考え・判断し・行動できる」力を身につけるための活動に取り組みました。最終日に行う踊りと劇の発表会の準備を5日間かけて積み上げていく中で、行動観察で求められる非認知能力を高めるために新しい課題に挑戦しています。
私が担当する午前中の学習では、これまで難しいとされてきた課題がどこまで理解できているかをチェックしながら、過去問だけでなく独自に考えた予想問題に挑戦させました。そして、答え合わせをするだけでなく、1問1問の解き方を前に出て説明する時間を設け、考えのプロセスを言語化する授業を通して、理解を確実なものにしていきます。こうした授業を通して子どもたちの成長ぶりを目の当たりにし、これまでの学習の成果を実感しています。これまでできなかった問題が自分の力で解決できたときの笑顔と、そのあとの意欲的な取り組みを見ると、子どもはこのようにして自信をつけ、変わっていくのだという実感を持つことができます。特に、お友だちの前で考え方のプロセスを発表できたという自信は、成長の原動力として大きな意味を持ってきます。
4日目に行った「置き換えを伴う交換」の学習は、次のような内容です。
- 【交換の約束】
動物村の果物屋さんは次のように果物を取り替えてくれます。
ミカン1個はクリ2個と交換できる
ブドウ1房はミカン2個と交換できる
リンゴ1個はミカン1個とクリ1個と交換できる - 【問題】
(1) クリ4個はミカン何個と交換できるか
(2) ブドウ2房はクリ何個と交換できるか
(3) リンゴ4個はブドウ何房と交換できるか
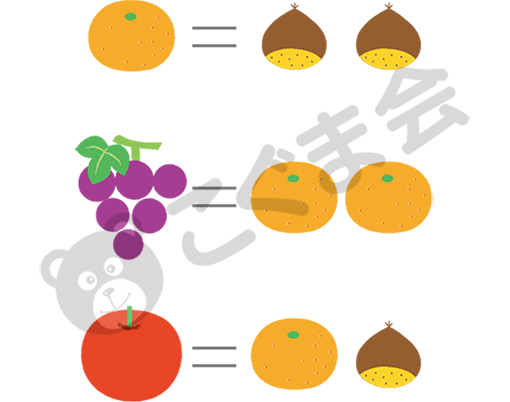
この課題は、ずいぶん以前にある小学校の入試で出題された次の問題を参考に作ったものです。
- 【交換の約束】
動物村のパン屋さんは次のお約束でパンを取り替えてくれます。
メロンパン1個はドーナツ2個と交換できる
食パン1斤はメロンパン2個と交換できる
ハンバーガー1個はメロンパン1個とドーナツ1個と交換できる - 【問題】
(1) ドーナツ4個はメロンパン何個と交換できるか
(2) 食パン2斤はドーナツ何個と交換できるか
(3) ハンバーガー4個は食パン何斤と交換できるか
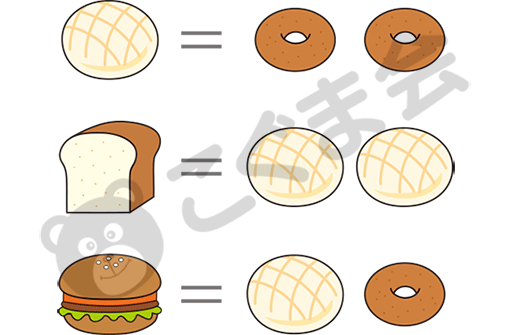
この過去問を何回も練習して答えを覚えてきてしまっている子もいるのではないかと思い、今回は同じ趣旨の問題を素材を変えて作りました。
(1)はクリとミカンの関係を、クリから問う問題です(包含除の考え方) (2)はブドウとクリの関係を、ミカンを仲立ちとして考える問題です(かけ算の考え方) (3)はリンゴとブドウの関係を、ミカンやクリを仲立ちに考える問題です(包含除の考え方)
(3)をどう解くかが課題ですが、解き方を機械的に覚えてしまっている可能性もあるため、(2)の後に、「ブドウ3房はリンゴいくつと換えてもらえますか」というように、(3)の逆思考の問題として取り組んでみました。解ける子はいないのではないかと予想しましたが、なんと8名中3名の子が正解し、説明もしっかりできました。ここまで理解していればどのように問われても必ず解けるはずで、やはり(3)の問題も正解できていました。
ではどのように考えたのでしょうか。子どもの発想に沿って述べてみます。
ブドウ3房をリンゴに換える場合
- まずブドウ3房をミカン6個に換えます
- ミカンだけではリンゴに変えられないため、ミカン1個をクリ2個に換えます
- ミカン1個とクリ1個の組み合わせが2つできるので、これでリンゴが2個になります
- 残ったミカン3個のうち1個をクリに換えると、ミカン2個とクリ2個となり、ここの組み合わせでリンゴ2個に換えられます
- その結果、ブドウ3房はリンゴ4個と換えられることになります
ここまで整然と説明はできませんが、正解できた子のプロセスはこのようなものでした。ブドウはミカンにしか換えられない、しかしリンゴに換えるにはクリが必要と考え、6個のミカンのうちまず1つだけクリに換える、それでもクリが足りないので、もう一つクリに換える・・・ここが子どもらしい発想で、ミカンを一度に2個換えず、1個ずつ換えていくというところが試行錯誤の結果だと思います。先を見越して、最初から「ミカン2個をクリ4個に換え、ミカンとクリの組み合わせを4つ作って、だからリンゴは4個」という大人の発想とは違う、子どもが一生懸命考えた結果です。4カ月前にはできなかった(3)の問題にも8割の子どもたちが正解しており、成長の跡がしっかりとつかめました。
過去問でも今回の問題でもそうでしたが、子どもたちが正解に至る道筋は、最初のうちは大人の発想と必ずしも一緒ではありません。しかし、子どもなりに精一杯考えて編み出した方法のなかにこそ、子どもが物事をどのように考えたかがはっきりつかめます。その発想を前提に、大人の思考に近づけていけばいいわけで、最初から大人のやり方を押し付ける必要はありません。子どもが物事をどう考えるかを学びながら、適切な指導を工夫する必要があることを、教室での授業を通して痛感しています。
※次回は8月18日(金)です
- こぐま会代表 久野泰可 著「子どもが賢くなる75の方法」(幻冬舎)
読み・書き・計算はまだ早い!
 家庭でできる教育法を一挙公開
家庭でできる教育法を一挙公開
子どもを机に向かわせる前に実際の物に触れ、考えることで差がつく。- 食事の支度を手伝いながら「数」を学ぶ
- 飲みかけのジュースから「量」を学ぶ
- 折り紙で遊びながら「図形」を学ぶ
- 読み聞かせや対話から「言語」を学ぶ