週刊こぐま通信
「室長のコラム」基礎段階の学習を終えた子どもたちの学力の現状 (2)
第807号 2022年3月30日(水)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

前回に引き続き、ステップ4までの基礎段階の学習を終えた子どもたちの学力の現状をお伝えします。今回は「図形」「言語」「生活 他」の領域です。
まず「図形」領域です。図形の基礎は「基本図形の理解」を前提として、「図形構成(平面・立体)」と「図形分割」を中心に学習を進めました。以前から小学校入試の図形問題は、図形構成・図形分割が6割以上を占めていました。現在は少し傾向が変わってきていますが、やはり図形課題の中心はこの2つです。そうした観点で考えると、これまで行ってきた課題の中で理解度に差が出る問題は、
- 秘密袋を使った図形模写
- 三角パズルの構成と分割
- つみ木を使った形の変化
- 触索による図形模写
- 用意された袋の中に手を入れて、中の具体物に触ってみる。その後、入っていたものの形を画用紙にクレヨンで描く。
※中に入っていた形
立方体、丸いもの、円柱、両側に丸いものがついている棒、2つの形がひもでつながっている形など。立方体はつみ木、円柱や丸いものはモコモコとした素材でできている。
次は「2. 三角パズルの構成と分割」です。以前は、三角パズルが入試でよく出題されていました。最近はそれほど多くはありませんが、三角パズルはすべての図形構成の基本ですので、しっかり身につけておく必要があります。しかし、現段階では理解度に相当の開きが見られ、パズル8枚を使う図形構成をやってみると、3分以内にできる子がいる一方で、10分かけても完成しない子もいるという状況です。三角パズルをやったことがあるかないかで差が出るのは当然ですが、それ以上に図形的なセンスがどれだけ身についているかということも大切です。遊びとして行っている「ピクチャーパズル」のような経験が大きな差になっているのではないかと思います。三角パズルの入試問題は次のようなものです。
- 三角パズルの構成
- 大きい三角パズル2枚と、小さい三角パズル2枚を合わせてできる形にを、できない形に×をつけてください。
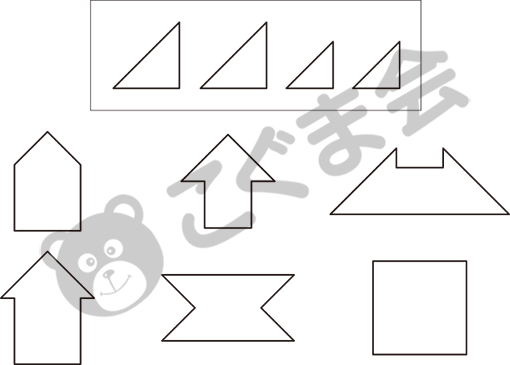
- 大きい三角パズル2枚と、小さい三角パズル2枚を合わせてできる形にを、できない形に×をつけてください。
「3.つみ木を使った形の変化」は、入試問題では次のような課題になります。
- つみ木の移動
- 上のお部屋のつみ木から、2個動かしてできる形を下から探して、をつけてください。
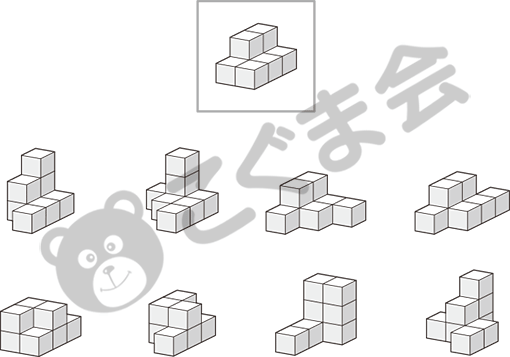
- 上のお部屋のつみ木から、2個動かしてできる形を下から探して、をつけてください。
こうした課題を意識しながら、8個のつみ木を使った「山手線ゲーム」を授業で行いました。1個ずつ動かしながら形を変えていく練習です。こうした練習を通して、変化したところと変化しないところを把握する目を養いたいと思います。三角パズルを使った「山手線ゲーム」より易しいはずですが、作業時間には差の出る課題です。
「言語」領域では、「話の内容理解」「お話づくり」「日本語の理解」の3つが学習の中心になります。基礎段階の学習において差がつく課題は次の3つです。
- 前に戻るしりとり(逆しりとり)
- 絵カードを時系列に並べ、お話をつくる
- 長いお話を聞き、登場人物とその行為を関係づける
- 逆さしりとり
- 左上のお部屋を見てください。ブタ→タヌキ→キツネと、しりとりでつながります。逆しりとりで「キツネ」から考えると「キツネ」の「き」が「タヌキ」の「き」とつながって「タヌキ」の「た」が「ブタ」の「た」とつながります。
- 逆さしりとりで青いのお部屋の「ラッパ」が最後になるように、青でつないでください。3つの絵がつながります。
- 逆さしりとりで赤いのお部屋の「かさ」が最後になるように、赤でつないでください。3つの絵がつながります。
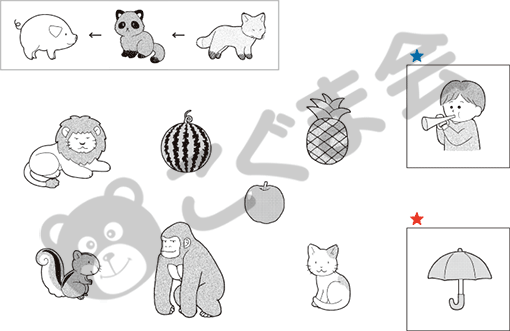
「逆しりとり」は「頭とり」ともいいます。しりとりのルールをしっかり理解し、後ろにつなげるゲームを逆思考的に前に戻るという問題ですから、しりとりの中でも難易度は高くなります。しりとり課題にはいろいろなパターンがありますので、まず後ろにつなげる問題、空欄を埋める問題をしっかり理解してから取り組んでください。
次は「2.絵カードを時系列に並べ、お話をつくる」です。現在、非認知能力の一つとして「表現する力」が求められています。「お話づくり」は幼児期の課題として最適です。4枚の絵カードを時間的経過に沿って並べ、それを使ってお話をつくる課題がその典型ですが、絵カードの枚数が3枚になり、2枚になり、最後は1枚だけで前後関係を考えながらお話をつくることもあります。言葉で話すことの得意・不得意もありますが、それ以上に場面をつないでいく、例えば原因と結果のような論理性が身についているかどうかも問われます。この課題は、小学校入試では個別テストで行うことが多いため、ペーパー中心の学校ではあまり出題されませんが、口頭試問や行動観察で「話す力」は求められていますので、どんな試験形式の学校を受験するにしても、大事な基礎力としてしっかり身につけてください。最近の入試でも次のような問題が出されています。
- お話づくり
- 3枚の絵を1人に1枚ずつ子どもに配る。何をしている絵か1人ずつ場面を説明する。その後、3人で3枚の絵を合わせてお話づくりをする。お話をみんなで相談してそれぞれ違った発表をする。
- 「3枚の絵はつながります。合わせるとどんなお話ですか」
- 「違うお話をしてください」
- 「また、違うお話をしてください」
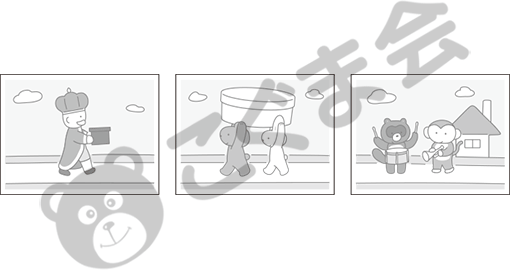
「3.長いお話を聞き、登場人物とその行為を関係づける」、つまり「話の内容理解」ですが、この課題の難易度は話の中身とそれに対する質問事項によって決まります。記憶の要素が強いですが、話の中身に対する理解がないと読解力につながっていきません。最近の入試問題はそのことを物語っています。以前から話の中身は物語文と生活文に大きく分かれ、それぞれに対し、次の4つが質問の柱でした。
- 登場人物について
- 順序について
- 数について
- 登場人物とその行為の関係づけ
「生活 他」領域では、ステップ4までに、「分類」「理科的常識」「法則性の理解」に関する内容を学習しましたが、その中で、現在も得点差になって表れる問題を3つ紹介します。
- 鏡映像
- 観点を変えた分類
- 並び方の法則性
- 鏡映像
- 上の絵を見てください。傘をさし、カバンを持った女の子が、鏡の前に立っています。鏡にはどのように映るでしょうか。下から探してをつけてください。
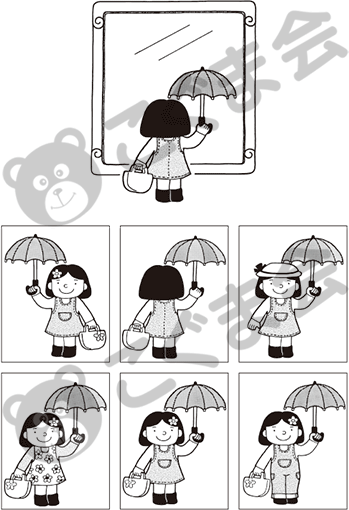
- 上の絵を見てください。傘をさし、カバンを持った女の子が、鏡の前に立っています。鏡にはどのように映るでしょうか。下から探してをつけてください。
次は、仲間あつめや仲間はずれに象徴される「分類」課題の中の「2.観点を変えた分類」です。具体物やトランプカードのようなやや抽象的なものを使って行いますが、特に仲間の数が指定された次のような問題に、出来不出来の差がよくみられます。
- 観点を変えた分類
- ここにあるカードを仲間に分けてください。
- 今度は別の方法で仲間に分けてください。
- ここにあるカードを3つの仲間に分けてください。
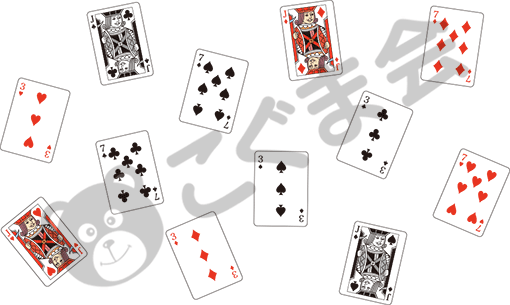
こうした問題の前に、まず自分で一度仲間あつめをし、それをばらばらにして今度は違った観点で仲間あつめをする練習を繰り返してください。具体物カードやトランプカードなどを使って繰り返し練習し、最後に仲間の数が指定された分類に挑戦してください。
最後は「3. 並び方の法則性」です。一般的には図形系列といわれているものですが、いろいろなレベルの問題があります。解き方の基本は、「口ずさむ」か「指送り」をするかの2つしかありませんので、まずこれを徹底して身につけてください。そのうえで、図形の変化だけでなく、数や位置などいろいろな並び方の変化に気づくようにしてください。最近、こうした図形系列に加え、次のような変化の法則性を考えさせる問題も出ていますので、一つ一つの形の動きに着目できるような練習をしてください。この課題の出来不出来が目立ちます。
- 図形系列
- まわの星の形は、左上から矢印の方向にあるお約束で並んでいます。ウシとブタのお部屋にはどんな形が入りますか。
真ん中の大きな星のお部屋から選んで、ウシのところに入る形には、ブタのところに入る形にはをそれぞれつけてくだささい。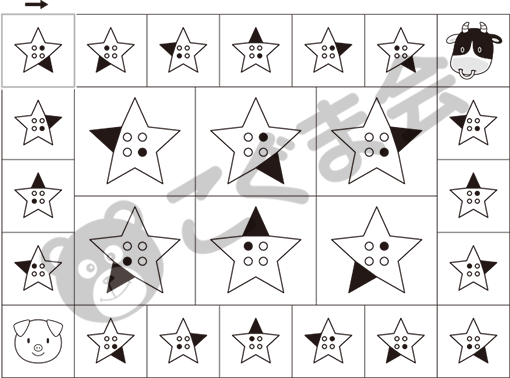
- まわの星の形は、左上から矢印の方向にあるお約束で並んでいます。ウシとブタのお部屋にはどんな形が入りますか。
以上2回に渡り、ステップ4までの学習内容で理解度に差が出る問題をお伝えしました。多くの場合、こうした差が出る問題が入試ではよく出されますので、基礎をしっかり固め、いろいろな問題にチャレンジしてください。
- 重版決定!! こぐま会代表 久野泰可 著「子どもが賢くなる75の方法」(幻冬舎)
読み・書き・計算はまだ早い!
 家庭でできる教育法を一挙公開
家庭でできる教育法を一挙公開
子どもを机に向かわせる前に実際の物に触れ、考えることで差がつく。- 食事の支度を手伝いながら「数」を学ぶ
- 飲みかけのジュースから「量」を学ぶ
- 折り紙で遊びながら「図形」を学ぶ
- 読み聞かせや対話から「言語」を学ぶ