週刊こぐま通信
「室長のコラム」読解力の基礎としての「話の内容理解」
第801号 2022年2月11日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

今年行われた大学入学共通テストの平均点が低かったことが話題になっています。数学においては、数式をいじっていれば解答できるような問題だけでなく、日常生活の状況を数学的に考えさせる問題まで出され、文章読解力や情報処理能力が問われた点がこれまでの問題とは違ったようです。数学の問題を処理するために読解力が問われる・・・と聞くと、小学校で計算ができても文章題が解けないという状況と重なってきます。最近日本の子どもたちの読解力が落ちているという事例がたくさん報告されています。新井紀子氏の「AI vs. 教科書が読めない子どもたち」(東洋経済新報社, 2018)で指摘されたこともその一つですが、そこで懸念されていることと、今回の大学共通テストの結果とがつながっているようにも思います。
ところで、そうした学校教育における「読解力」の育成は国語科の4つの柱の一つですが、その内容をめぐっていろいろ議論され、文学作品中心の読解力の育成だけではだめなのではないかといった意見も出てきます。今回の数学の問題の中には、「日本国外における日本語教育の状況」について国際交流基金のWEBページを読ませる問題も入っています。「法律の文章や取り扱い説明書なども読ませ、読解の教材を文学作品中心から変えるべきだ」という意見もうなずけます。
ところで、読解力の育成に関し、幼児期の基礎教育ではどのように考えたらいいのでしょうか。私は、国語科の4つの柱である「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能のうち、「読む」「書く」の前に、「聞く」「話す」を徹底すべきだと考え、セブンステップスカリキュラムの言語領域の課題として「話の内容理解」「お話づくり」「日本語の理解」の3つを柱として、1年間のカリキュラムを考え実践してきました。
では将来の「読解力」につながる「話の内容理解」は、小学校入試でどのように問われているのでしょうか。今年の入試の中から典型的な問題を一つ紹介しましょう。
- 2022年度入試 「話の内容理解(A校)」
- 次のお話を聞いて後の問題に答えてください。
- ある秋の日のことです。ニワトリのコッコさんが野原で散歩をしていると、ネコさんが草むらに座って何かを食べているのが見えました。「ネコさん、何を食べているの?」とコッコさんがたずねると、ネコさんは「散歩をしていたら、丸くて黄色いものが落ちていたんだ。おいしそうだったからつい食べちゃった」と言いました。不思議に思ったコッコさんは、残っていた黄色いかけらを見ました。そして、驚いたように跳び上がると、大きな声で言いました。「大変よ!これはきっとお月様だわ!」ネコさんもびっくりです。「昨夜の風でここに落ちてきたのよ」とコッコさんは言いました。ネコさんは「ど、どうしよう・・・」と今にも泣きそうになりました。
そこへ、コッコさんの大声を聞いたウサギさんとブタさん、クマさんがやって来ました。コッコさんが「ネコさんがお月様を食べちゃったのよ」と言うと、3匹は「それは大変だ!」と驚いて言いました。ブタさんは「お月様がなかったら夜の外は真っ暗じゃないか!困るよ、お友だちとぶつかって、たんこぶができたらどうするんだ!」とネコさんに言いました。ウサギさんとクマさんも怒っています。困ったネコさんはとうとう泣き出してしまいました。そのとき、コッコさんが「いいことを思いついた。みんな私について来て」と言いました。
少し歩くと、ゾウさんのお家に着きました。出て来たゾウさんにコッコさんは「ホットケーキを焼きたいから、ゾウさんのお家の台所を貸してくださいな」と言いました。ゾウさんが不思議そうに「まぁ、どうしてうちに?」と聞くと「大きなホットケーキを作りたくてね」とコッコさんは答えました。料理上手なコッコさんは台所に入ると、持って来た材料とゾウさんの大きなフライパンを使って、あっという間に大きなホットケーキを焼きあげました。「さぁ、新しいお月様の完成よ。みんなでこのホットケーキを山に置いて来てちょうだい」とコッコさんが言うと、ネコさん、ウサギさん、ブタさん、クマさんは「はーい!」と元気よく返事をしました。
早速4匹は出発しました。ホットケーキは力持ちのクマさんが持って行ってくれます。山道を登って山のてっぺんに着くと、ホットケーキを置きました。
夕方ごろ、山を下りて来た4匹は、コッコさんと一緒に野原でお月様がのぼるのを待つことにしました。みんなどきどきしながら空を眺めています。そのとき、山のてっぺんからお月様がゆっくりと空にのぼっていくのが見えました。「わー、よかった!これで元通りだね」みんな大喜びです。ネコさんも嬉しそうににっこり笑いました。
- お話に出てきたものにをつけてください。
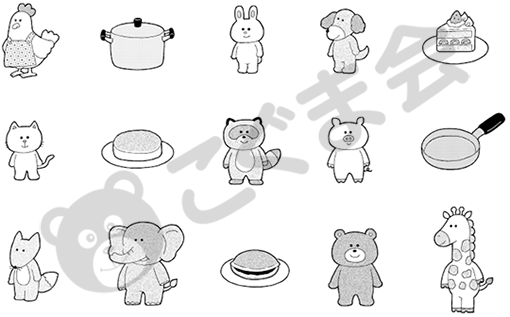
- 今のお話の順番になるように線結びしてください。
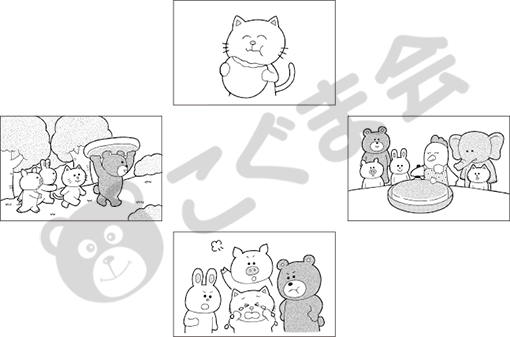
- ゾウさんのお家に行ったのはなぜですか。をつけてください。
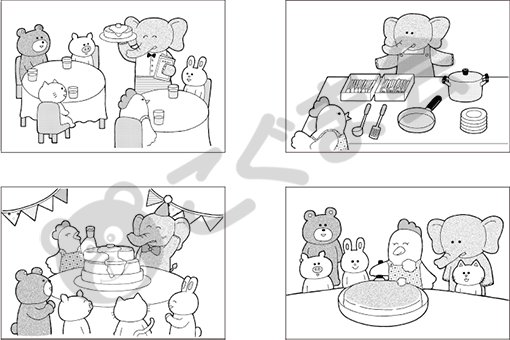
- ブタさんは、お月様がないと何が困ると言っていましたか。をつけてください。

- 最後にお月様がのぼったときの絵はどれですか。をつけてください。
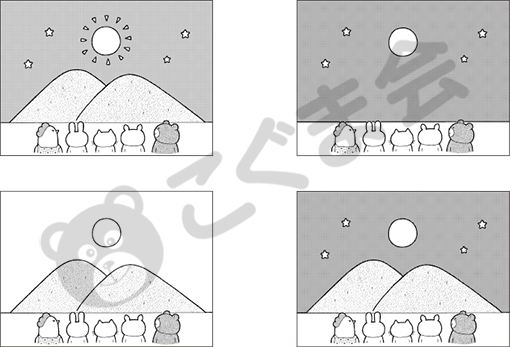
- お話に出てきたものにをつけてください。
小学校入試においては、どんな試験形態でも必ず「話の内容理解」は取り上げられています。いかに聞く力を重視しているかが伺えます。入試における話の内容理解は、生活文と物語文のどちらかが出されますが、いずれにしても質問される内容は、昔から以下の4つが中心でした。
- 登場人物に関する質問
- 順序に関する質問
- 数に関する質問
- 登場人物と物事の関係づけ
話の内容理解は確かに覚えることが多く「記憶」の側面もありますが、記憶問題としてではなく、将来の読解力につながる「内容を理解する」ことに重点をおいた指導が大事です。ここに紹介した動物たちの行為の背景を問いかけるような問題を見るにつけ、記憶ではなく内容理解として受け止めることが大事だと感じます。2022年度入試において女子校で出題された話の内容理解の質問事項を整理してみると次のようになります。
| 2022年度入試「話の内容理解」 A~I校:質問事項(ペーパー枚数) | |
|---|---|
| A校 | 登場人物 / 時系列 / 理由 / 発言内容 / 見た景色(計5枚) |
| B校 | 季節 / 作ったものの特徴 / 持参したもの / 身に着けたもの / 出てきた人数(計1枚) |
| C校 | 理科的常識 / 時系列 / 手伝いの内容(計3枚) |
| D校 | 季節 / 音の聞き取り / 数 / 関係づけ / 傘の色 / 行ったお店(計3枚) |
| E校 | 身に着けた服 / 花束の特徴 / 持ち物 / 等分 / 四方からの観察(計2枚) |
| F校 | 食事の内容 / 身に着けた服 / 見た絵(計3枚) |
| G校 | 見つけた場所 / 身に着けた帽子 / 身に着けた服 / 持ってきた動物 / 入れなかった食べ物 / 季節 / 見た景色(計1枚) |
| H校 | 発明したもの / 登場人物 / 持ってきたもの / 鳴ったもの(計1枚) |
| I校 | 天気 / 作ったもの / 入れなかったもの / 季節(計1枚) |
質問の内容が多様化していることがわかります。日常的な絵本の読み聞かせだけでなく、話を聞いて自分の生活や遊びを振りかえる経験をたくさん積んでいただきたいと思います。いずれ小学生になれば「話を聞いて」内容を理解する段階から、「文章を読んで」内容を理解する段階に進んでいくわけですが、聞いて理解する経験を幼児期にたくさん積むことが大事です。
読解力は本をたくさん読めば自然と身につくといった考え方を改め、読む文章の内容も含め、相当力を入れて準備し、指導しなければいけないと思います。読解力を育てるために何ができるのか、どのようなカリキュラムを作り、どんな素材を使うのか。今回の大学共通テストの分析を通して、これから先の教育の在り方を考えると、やるべき課題はたくさんあるように思います。
- 重版決定!! こぐま会代表 久野泰可 著「子どもが賢くなる75の方法」(幻冬舎)
読み・書き・計算はまだ早い!
 家庭でできる教育法を一挙公開
家庭でできる教育法を一挙公開
子どもを机に向かわせる前に実際の物に触れ、考えることで差がつく。- 食事の支度を手伝いながら「数」を学ぶ
- 飲みかけのジュースから「量」を学ぶ
- 折り紙で遊びながら「図形」を学ぶ
- 読み聞かせや対話から「言語」を学ぶ