週刊こぐま通信
「室長のコラム」ステップ1 関連入試問題
第743号 2020年10月30日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

9月から始まったセブンステップスカリキュラムに基づく学習は、すでに今週からステップ2に入りました。7つあるステップの最初の4ステップは基礎学力の育成ですから、すぐに入試問題を扱うわけではありません。そこを勘違いされると、学習内容がやさしすぎるという意見につながります。しかし、実際の1年間の指導はらせん型カリキュラムになっていて、自分で問題を解く力を身につけるためには基礎学力を徹底して身につけなくてはなりません。ところが、すべてを1年後の受験に結び付けて考える方が大勢いて、すぐにでも過去問に取り組ませようとする間違った指導が始まります。そのような指導者は、教育の系統性についての理解ができていないですし、基礎と応用の違いや、間違えたときにどこまで戻って指導すればいいか何も分かっていません。ですから過去問の分析すらもできないまま、横並びでともかくたくさんの過去問をやれば合格できると考えています。過去問さえやれば合格できるといった訓練主義の教育で指導する人たちは、大事な幼児期の学習が将来の教科学習の基礎になっていくということを理解せず、ただ合格をゴールに考えているのです。しかし、合格はスタートラインに立っただけの話で、それからあとに続く教科学習の基礎がしっかりできているかどうかが問題です。やさしいからだめだということではなく、将来の学習の基礎として何が大事なのかの理解が必要です。その意味で、ステップ1は基礎中の基礎であり簡単です。しかしここをしっかり身につけないと、5月の連休明けから始まる本格的な過去問トレーニングで壁に突き当たります。その壁を突破するのは「自分で考える力」です。これをしっかり身につけておかないと、最近のよく練られた問題は自分の力で解くことはできません。焦らず一歩一歩階段を上っていくような積み上げをぜひ実行してください。いま行っている基礎学力がどのように入試問題につながっていくのか、いくつかの例を示しますので、ステップ1の基礎がどれだけ大事かをしっかり受け止めてください。
ステップ1で学習した内容は、前回のコラムでお伝えした通りです。
| 未測量: | 大きさ・多さくらべ / 量の系列化 |
| 位置表象: | 上下・前後関係 / 位置の系列化 |
| 数: | 正確に数える / 分類計数 / 数の構成 |
| 図形: | 基本図形の理解 |
| 言語: | 一音一文字 / 同頭音・同尾音 / しりとり |
| 生活 他: | 分類 / 観点を変えた分類 |
- 分類計数
- 基本図形の構成
- 一音一文字
- しりとり
- 観点を変えた分類
実際の過去問を見てみましょう。
- 1. 分類計数
- 動物たちが運動会をしています。
- サルとウサギの数の違いはいくつですか。その数だけイチゴのお部屋にをかいてください。
- 応援をしている人で、手を挙げているのは何人ですか。その数だけミカンのお部屋にをかいてください。
- 応援をしている人の中で、手を挙げていて、ウサギとイヌの間にいる人にをつけてください。
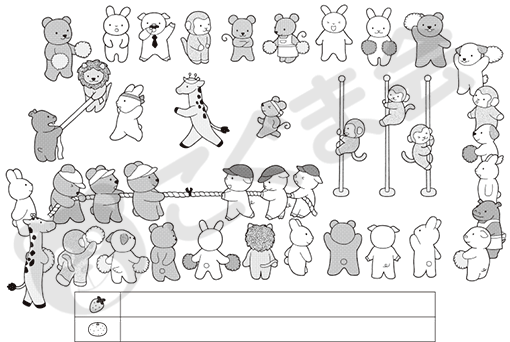
- 2. 基本図形の構成
- (イ)のお部屋を見てください。三角パズルが4枚ありますね。このパズルを使ってできない形はどれですか。3つの中から選んでをかいてください。
- (ロ)のお部屋を見てください。上の3つのパズルを使ってできない形はどれですか。3つの中から選んでをかいてください。
- (ハ)のお部屋を見てください。上のパズルを使って、いろいろな形を作ります。このパズルを使って作れる形はどれですか。3つの中から選んでをかいてください。
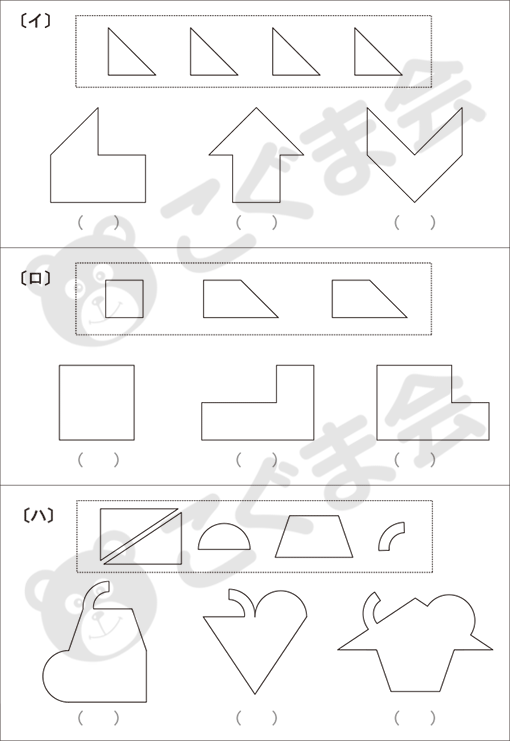
- 3. 一音一文字
- 〈れい〉のお部屋を見てください。1番上のお部屋のものの名前と、はじめの音が同じものを下から選びます。ウサギは「う」からはじまるので、ウシにがついています。では〈れい〉の隣から順番に1問ずつ問題を解いていきましょう。
- 1番上のものと名前のはじめの音が同じものを選んで、をつけてください。
- 1番上にあるものの名前の真ん中の音が、名前のはじめにあるものにをつけてください。
- 1番上にあるものの名前の最後の音が、名前のはじめにあるものにをつけてください。
- 1番上にあるものの名前の最後の音が、名前の最後にあるものにをつけてください。
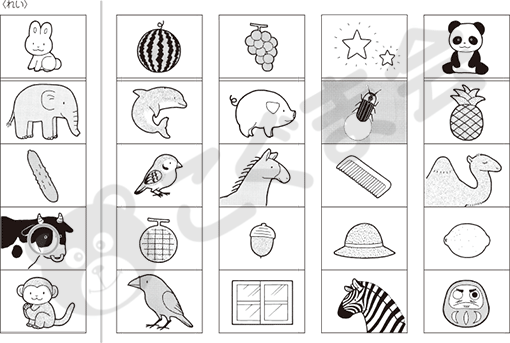
- 4. しりとり
- 左上の(れい)のお部屋を見てください。リンゴ -ゴリラと、しりとりでつながるものはラッパなので、右のラッパの絵に星のマークがついています。同じように他の並んでいる3つのお部屋が、しりとりでつながるには、空いている「?」のお部屋に何を入れたらよいですか。お部屋の下についている印と同じ印を右の絵につけてください。
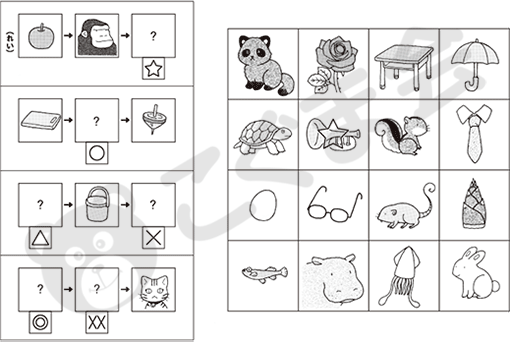
- 5. 観点を変えた分類
- ここにあるものを使って仲間あつめをしてください。仲間にあつめたら、何の仲間なのかお話ししてください。1つの仲間あつめができたら、他の方法での仲間あつめも考えてください。
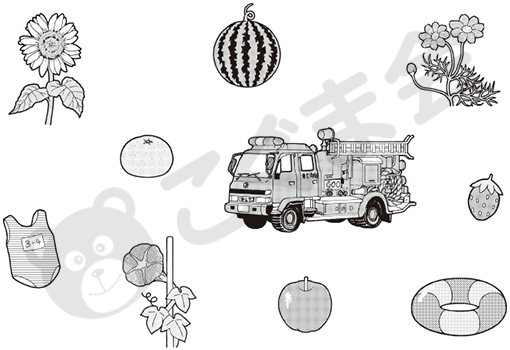
現段階ですべての問題が解けるわけではありませんが、こうした問題の基礎づくりがステップ1のやさしい内容の中にあるということです。過去問トレーニングをしていて、なぜ間違えるのか分析をしていくと、結局一番基礎的な部分の理解があいまいであったという結論に至るのです。そこを理解しないと「難しい問題を練習するのが受験トレーニングだ」というような誤った考え方に陥ってしまい、悪循環が始まるのです。難しい問題が解けるようにならなければなりませんが、それはこれから学習を積み上げていった結果のことで、今すぐに難問をトレーニングするということではないのです。他人と比較して一喜一憂したり焦りを感じたりしたら、一度冷静になってください。これからの学習の見通しをしっかり持ち、ともかく今は基礎をしっかり身につけてください。難しい過去問は、5月連休明けに取り組めばそれで充分です。