週刊こぐま通信
「室長のコラム」「新年度の授業が始まりました」
第695号 2019年10月25日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

11月から始まる38期の授業は、来週が試験期間で休講になるため、前倒しで今週から始まりました。セブンステップスカリキュラムの授業はすでに9月から始まっていますので、ばらクラスでは「ステップ2」の学習から開始することになります。
先日20日の日曜日、広島の「大木スクール」で開催された講演会に登壇し、幼児期の基礎教育のあり方についてお話しさせていただきました。広島でこぐま会の授業が始まって5年経ちました。この5年間で広島大学附属小学校への合格者は3倍に増えました。「10年間の過去問を繰り返しやっておけば合格できる」といったような間違った宣伝が横行する中で、事物教育と対話教育による受験対策が大勢の皆さまに支持され、その結果、合格者の飛躍的拡大につながっていると思います。セミナーでもお話しさせていただきましたが、過去問を繰り返しやるという方法は、教え込みのパターン学習であり、1年後にできればいい問題を1年近く前倒しして行うということであり、子ども自身の力で解ける筈はありません。それが受験対策だという風に刷り込まれているのが、偽らざる現状です。そんな学習では受験が終わればすぐに忘れてしまい、将来の学習の基礎になることはありません。私たちは「幼児期の基礎教育をしっかり行い、その延長に受験がある」という考え方で受験対策を行っています。過去問は年長の夏にできれば十分です。それを解けるだけの力を、それまでの基礎教育でしっかり身につけていくことが大事です。らせん型カリキュラムで学習を積み上げ、学びの系統性を重んじた学び方をしなければいけません。9月から始まったセブンステップスカリキュラムは1年間の学習内容を構造化したもので、基礎から応用へ、具体から抽象への学びの基本を踏まえたカリキュラムです。11月から来年4月までを基礎段階の学習(ステップ4まで)にあて、5月~8月までを応用段階の学習(ステップ5・6)として位置づけ、9月~10月を総まとめの直前トレーニングにあてています。そうした見通しの中で、1回1回の授業を大切にしています。
ところで9月から始まったステップ1の授業では、以下のような内容を学習してきました。
ステップ1の学習内容(6領域)
| 領域 | 単元 | |
|---|---|---|
| 第1週 | 未測量 | 大きさ・多さくらべ |
| 第2週 | 位置表象 | 上下・前後関係 |
| 第3週 | 数 | 計数、同数発見、5の構成 |
| 第4週 | 図形 | 基本図形とその構成 |
| 第5週 | 言語 | 一音一文字、しりとり |
| 第6週 | 生活 他 | 分類1(仲間あつめ) |
今週から始まっているステップ2の学習内容は以下の通りです。
ステップ2の学習内容(6領域)
| 領域 | 単元 | |
|---|---|---|
| 第7週 | 未測量 | 重さくらべ |
| 第8週 | 位置表象 | 左右関係 |
| 第9週 | 数 | 一対一対応 |
| 第10週 | 図形 | 立体構成 |
| 第11週 | 言語 | 短文づくり |
| 第12週 | 生活 他 | 理科的常識 1 |
基礎段階の学習とはいえ、小学校の入試でもよく出される課題につながる大事な学習がたくさん含まれています。そのいくつかを紹介しましょう。
- 重さくらべ
- シーソーの課題を学習する前にまず自らの体で重さを感じ、そこでの系列化の方法を、実際のシーソーの操作に生かす
- 左右関係
- 空間認識の基礎となる、自分以外の右手・左手を理解し、地図上の移動の基礎となる交差点の曲がり方を実際の場面で体験する
- 一対一対応
- 数を比較する方法を身につけ、「違いはいくつ」に象徴される5つの違った問いかけに答えられようにする
- 立体構成
- 触策のみでものの形の特徴をつかむ秘密袋の課題に取り組む。また、8個の立方体つみ木を使って指示された形をつくる
- 短文づくり
- 動きを表す言葉(動詞)を短文づくりの方法で学び、4枚の絵カードを時系列にならべ、それを使ってお話づくりの練習をする
- 理科的常識 1
- 切断面・生活の中の音・鏡映像・季節の花など、入試でよく問われる内容について実物を使った学習で理解を定着させる
こうした事物を使った教育は、一人ひとりの試行錯誤する時間を保障し、物事に働きかけることを通して認識能力を高めていく方法です。その上で、ペーパートレーニングを積み上げていく方法が「KUNOメソッド」の特徴です。入試対策を「過去問を徹底してトレーニングするやり方でいい」と考えている人たちとは全く違う方法です。上で述べましたが、将来の学習の基礎をまともな方法で身につけ、そのうえで入試に必要なペーパートレーニングを積み上げる「幼児期の基礎教育をしっかり行い、その延長で受験も考える」という方法です。この方法を入試にとっては生ぬるいと方法だと批判する方々は、幼児期の教育のあり方を理解できず、小学校の入試は特別な訓練でよいと考えているのでしょう。しかし、現在の入試問題を分析すれば、学校側がそんな特別な訓練を求めていないということは明らかです。自分で考え、自ら判断する力を求めているからです。毎日50枚ものペーパーをやらなければ合格できないという話は、全く根拠のない噂話であり、時代錯誤もはなはだしいばかげた話です。考える力を求める学校の意図に沿えば、1枚のペーパーを大事にし、それを使ってさまざまな問いかけに答えていくという学習方法が大事です。最近の問題に込められた学校側からのメッセージを読み解くと、「逆からの問いかけは必ずある」ということです。それを徹底して練習することが今一番必要な入試対策です。
こぐま会の事物教育 実践例
Step2 - 第10週 「図形:立体構成」
- (1) 秘密袋
- 右手と左手を両側から入れることができる袋の中に、いくつかの立体物が入っている。手探り(触索)をして、教師が示した形と同じ形を取り出す。

- (2) 立体の特徴
- 球・立方体・直方体・円柱・円すい・三角すいなどの立体を比較して、似ているところと違うところを説明する。
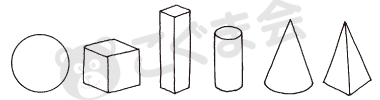
- (3) 円柱・円すいづくり
- 見本を見ながら、粘土で円柱や円すいを作る。
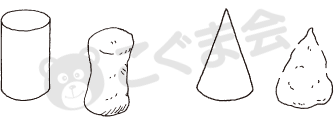
- (4) つみ木の構成
- 8個の立方体のつみ木を使って、見本と同じ形を構成する。
- 教師が作っているところを見て作る。
- できあがったつみ木を見て作る。
- できあがったつみ木の絵を見て作る。
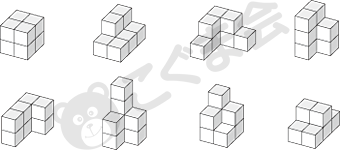
- (5) ペーパートレーニング
- つみ木の数-1:6個のつみ木でできているものを選ぶ
- つみ木の数-2:いくつのつみ木でできているかを考え、その数だけを描く
- つみ木の数-3:いくつのつみ木でできているかを考え、その数だけを描く
- つみ木の数-4:同じ数でできているつみ木同士を線で結ぶ
- つみ木の数-5:つみ木の数を数え、見本のつみ木より多いものはその数だけ、少ないものはその数だけ×、同じものはを描く
次回の更新は11月8日(金)です