週刊こぐま通信
「室長のコラム」対話教育の可能性
第637号 2018年8月10日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

KUNOメソッドは、教育方法の大事な柱に「対話教育」を掲げています。教師と子どもの関係が、教師からの一方的な教え込みにならないように・・・ということが第一の目的ですが、この対話教育には別の意図も持たせています。
- 子どもが自分の思考のプロセスを言語化することができるかどうか
- あるテーマをめぐって子ども同士の話し合いが可能かどうか
例えば、このコラムでもよく取り上げる「交換」の問題です。
- みかん1個は、イチゴ2個と換えてもらえる
- りんご1個は、みかん2個と換えてもらえる
- もも1個は、みかん1個とイチゴ1個と換えてもらえる
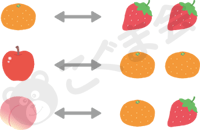 質問1:みかん4個は、りんご何個と換えてもらえますか
質問1:みかん4個は、りんご何個と換えてもらえますか質問2:りんご2個は、イチゴ何個と換えてもらえますか
質問3:もも4個は、りんご何個と換えてもらえますか
こうした問題を学習する場合、必ず絵カードやおはじきを使って子ども自身に考えさせます。そして、子どもにまず答えを出してもらい、その答えが合っていても間違えていても、前に出てきてもらって、なぜそうした答えになったのかを説明させています。その際、間違った答えを出した子が、前に出てカードを使って説明しているうちにその間違いに自ら気づき、そこで答えを修正する場面に良く出くわします。
先日もこんなことがありました。
「りんご2個がイチゴ何個と換えてもらえるか」を問いかけたとき、「4個」と答えた子が多かったので、その理由を説明できると挙手した子に前に出てもらって、果物カードを使って説明させました。すると、
「りんご2個は、みかん4個でしょ」
「そのみかんを1個につき2個ずつイチゴに換えると・・・」とそこまで話すと、
「先生 4個じゃなくて8個だった」
と言うのです。言語化することによって、考え方の筋道が明確になり、自分の答えが間違っていたことに気づいたのです。
また、同じ約束で「もも4個はりんごいくつですか?」と問いかけたところ、2個、3個、4個と答えが出てきたので、一番答えが多かった4個と答えた子の中で説明できるという子に前に出てきてもらいました。
| 子ども | 「もも1個は、みかん1個とイチゴ1個でしょ。だからもも4個はみかん4個とイチゴ4個になるの」 そこでその子の説明をわたしが一旦止め、 |
| 先生 | 「みんなそこまでは分かる?」と聴くと、 |
| 子ども | 「わたしもそうした」という子が多く、そこまではみんな納得しました。 |
| 先生 | 「じゃあ続けて」と言うと、 |
| 子ども | 「みかん4個はりんご2個に換えられるの」 |
| 先生 | 「そうだね。それからどうしたの?」 |
| 子ども | 「残った4個のイチゴをみかんに換えるでしょ。そうするとみかんは2個。それをりんごに換えるの」 |
| 先生 | 「そうだね」 |
| 子ども | 「そうすると、みかん2個はりんごは1個になるの」 すると、さっきみかん4個からりんご2個に換えたカードをじっと見て、 |
| 子ども | 「わたし、間違えていた。4個じゃなくて3個だった」 |
| 先生 | 「よく気づいたね」 |
と、ここでも説明することによって、自分の間違いを修正することができました。このように自分の考えを言葉に置き換えていくことによって、幼児でも自ら気づいていけるのです。
同じことを小学校2年生の算数の授業でもやってみました。さすがに小学生ですから、年長児が行うこの問題はできますので、最後に「りんご3個はももいくつ?」という問題も入れて、3人グループで考えさせながら答えを発表してもらいました。すると、3つのグループのうち2つのグループは答えを「4」としたのに対し、1つのグループは「5」と答えたので、幼児と同じように絵カード使って説明してもらいました。すると、
| 子ども | 「まずりんご3個をみかん6個に換えるの、それからみかん6個のうち2個をイチゴに換えるの、そうするとりんご3個は、みかん4個とイチゴ4個になるでしょ」 |
| 先生 | 「そうだね」 |
| 子ども | 「それからみかん1個とイチゴ1個を組にすると、・・・」とここまで説明すると、 |
| 子ども | 「先生わたし間違っていた、5個じゃなくて4個だった」 |
と説明していくうちに問題の意図が明確になり、自分の出した答えの間違いに気づき、修正していくのです。
2年生に投げかけた「りんご3個はもも何個?」という問題を、幼児ではとても無理だろうと予想しつつも、夏季講習会の雙葉クラスで出してみました。予想したとおり以前の学習で「もも4個はりんご3個」と答えられた子でも、その逆を問うとお手上げです。そんな中で、「4個」と答えた子がいたので、前に出て説明してもらいました。すると、
| 子ども | 「りんご3個はみかん6個でしょ。そのうちの2個だけイチゴに換えるの、そうするとイチゴ4個でしょ」といって、みかん4個とイチゴ4個になったカードを動かして、みかん1個とイチゴ1個の組み合わせを4つ作り、 |
| 子ども | 「だから、ももは4個なの」・・・・ |
あてずっぽうで4個と答えていたのではないかと疑っていた私も、大変びっくりしました。小2の子どもが分からない問題を、きちんと説明して正解に導きだせる力が、年長のこの頃になるとすでに身についているのです。この問題は、言語化だけでなく、カードを使って視覚的にも分かりやすくしたということが、正解に導くことができた大きな原因だろうと思います。
幼児期の子どもたちの「考える力」を育てるためには、試行錯誤し自分で解決させる時間がどうしても必要です。教え込んでしまえば簡単に済むものを、子どもたちの発想で解決にたどりつけないか・・・これは、教える側のわれわれも「待つ」時間の長さに耐える覚悟が必要です。しかし、自分で解決の糸口を見つけ出すことが将来の学習にはとても大事です。その意味でも、「対話教育」の持つ意味をもう一度考え、実行してください。
- 試行錯誤させる
- 具体物やカードを使って考えさせる
- 導いた答えの根拠を言葉で説明させる
特に対話教育の一環として行っている「理由の言語化」は幼児でも可能であるし、そのことは認識をしっかり定着させていく大事な方法だと思います。幼児期の教育に新しい風を吹き込むためには、こうした不可能とされていた方法を可能にする方法を模索していくことが大事です。それは、これまでのように教え込んで分かるものではありません。幼少期の学力を高めるためには、こうした同じテーマの問題に年齢や学年を問わず取り組ませることもひとつの方法だと思います。その取り組みの違いを、教育の方法に生かしていけばいいわけですから・・・。2020年度から始まる教育大改革には、理念だけでなく、こうした一つ一つの子どもの現場を踏まえた具体的な提案が必要です。好ましい姿を打ち出しても、それを実現する方法を持ち合わせなければ何の改革にもなりません。幼児教育の改革に今必要なのは、こうした現場の取り組みをもっと大事にすべきだということです。文献を寄せ集めて望ましい姿を打ち出すような、研究者の仕事には現実を変える力はありません。