週刊こぐま通信
「室長のコラム」幼児にかけ算をどう教えるか
幼小一貫教育の実践
第612号 2018年2月16日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

幼児期の学びを小学校の教科学習にどうつなげるか・・・こぐま会では、「教科前基礎教育」を指導理念の一つにしているため、常にこのテーマを念頭に置いて日々の実践を積み上げてきました。それは、子どもたちのこれまでの学習と、その理解度に沿って無理なく積み上げていくためのプログラムの構築ということでもあります。たとえば数の学習であれば、具体的な生活場面の数の変化を抽象的な数式の世界につなげるために、どのようなプログラムを用意すべきかということです。1月から始まった就学準備クラスの内容は、まさしくその橋渡しの授業でもあり、その橋渡しが成功すれば、幼児期の基礎教育の意味が明確になってくるということです。
第4週の「かけ算って何?」と第6週の「かけ算の答えの出し方」の授業は、まさしくそうしたことの典型と言える授業です。「幼児にかけ算?」と思われる方も多いと思いますが、2年生にならなくても理解は可能です。むしろ、これまでの学習につなげようとするならば、今が一番ふさわしい時期なのです。もっともこれは、かけ算九九を早く覚えさせる計算主義の教育ではありません。かけ算が、たし算やひき算と違ってどんな計算なのかを考えさせながら、その考え方の基礎をしっかり学ぶには、今が一番良い時期なのです。
こぐま会のばらクラス(年長)では、かけ算の基礎となる「一対多対応」の授業を行っています。お客さんごっこや車づくりの作業を通して、1に対して2以上の数を対応させる学習です。その授業は次のようなカリキュラムで指導しています。
- セブンステップスカリキュラム step4-3
数4「一対多対応」 - (1) お客さんごっこ
- 5人のお客さんに1人1個ずつコップを配ったり、1人に2個ずつキャラメルを配ったり、1人に3枚ずつ折り紙を配ったりする。
- 用意したものがお客さん全員に行き渡るかどうか確認する。余ったり足りなかったりした場合は、その数について答える。
- (2) 車づくり
- タイヤのない自転車カードを見ながら、5台の自転車を作るには全部で何個のタイヤが必要なのかを考えて、その数だけおはじきを出す。また、台数を変えた場合についても考える。
- タイヤのない三輪車カードを見ながら、4台の三輪車を作るには全部で何個のタイヤが必要なのかを考えて、その数だけおはじきを出す。また、台数を変えた場合についても考える。
- タイヤのない自動車カードを見ながら、3台の自動車を作るには全部で何個のタイヤが必要なのかを考えて、その数だけおはじきを出す。また、台数を変えた場合についても考える。
- (3) 袋づくり
- 3つの袋に3本ずつ鉛筆を入れるには、全部で何本の鉛筆が必要かを考える。
- 12本の鉛筆を3本ずつ袋に入れるには、袋がいくつあればいいかを考える。(包含除の考え方)
- 全部の鉛筆の数や1袋に入れる鉛筆の数を変えて考える。
この授業には子どもたちも大変興味を持ち、その後に続く「交換」などの問題の基礎として私たちも力を入れて学習しています。この一対多対応の学習を踏まえ、それを数字で表す数式の世界に子どもたちを連れて行き、いわゆるかけ算九九の学習につなげていければと考えて工夫した授業です。その方法を少し具体的にお伝えしましょう。就学準備クラスで用意したカリキュラムは、以下の通りです。
- 「かけ算って何?」
- (1) 一対多対応の復習(おはじきを使って)
- お客さんの問題
お客さん1人にあげる物の数と人数との関係をふまえ、全体でいくつ必要かを考える。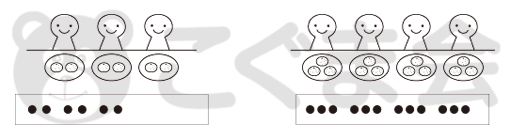
- タイヤの問題
自転車・三輪車・自動車の数とタイヤの数との関係を考える。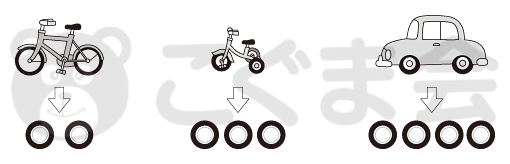
- お客さんの問題
- (2) ペーパーを使って
- 一対多対応の復習
- 一対多対応の復習
- かけ算の意味
- かけ算の意味
- かけ算の意味(まとまりを作る)
- かけ算の立式問題
- かけ算の立式問題
- かけ算って答えをどう出すの?
- (1) 一対多対応の復習
- お客さんの問題
お客さん1人にあげる物の数と人数との関係をふまえ、全体でいくつ必要かを考える。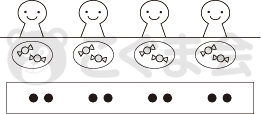
- タイヤの問題
自転車・三輪車・自動車の数とタイヤの数との関係を考える。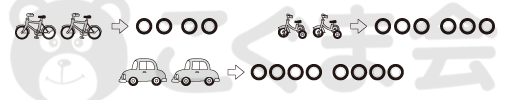
- お話づくり
かけ算の式を使ってお話をつくる。
- お客さんの問題
- (2) ペーパーを使って
- 1人にあげるものの数と人数の関係(人数が一定の場合)
- 1人にあげるものの数と人数の関係(ものの数が一定の場合)
- 何がいくつ集まると、全部でいくつになりますか?
- 何がいくつ集まると、全部でいくつになりますか?
- 答えが12になるかけ算の意味
- 2×(かける)の計算
- ×(かける)3の計算
- 2の段のかけ算
- 5の段のかけ算
- かけ算の計算
今年もすでに第4週の授業まで終了し、今週はかけ算の答えの出し方の学習を行いました。
ペーパーを使った学習では、最初のうちはばらクラスと同じ内容を行います。×記号の意味を伝え、お話づくりからはじめます。その課程で2×3と3×2の違いをしっかり理解してもらうために、タイヤを使っお話に徐々に切り替えていきます。その上で、これまでやってきた学習が実はかけ算という数式に表現できるんだ、ということを学んでもらいました。ばらクラスで行った一対多対応の復習をした後の、かけ算につなげる導入ペーパーは次の通りです。ばらクラスで行った内容を思い起こしながら、それにつなげる形でかけ算の意味を伝えてあげれば、子どもたちの理解は進みます。
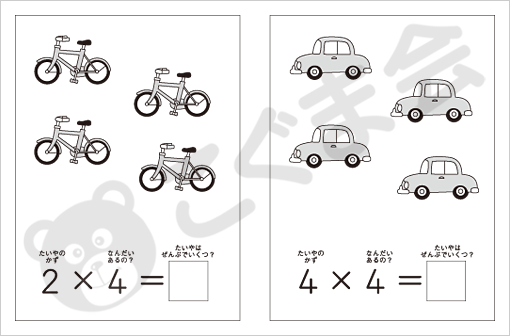
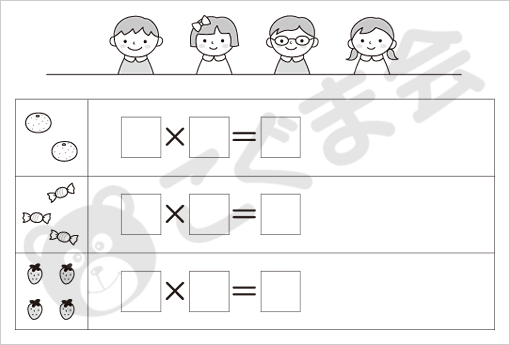
 一対多対応で学習した、お客さんの問題とタイヤの問題に即し、「一あたり量×いくつ分」の式に当てはめていけば、かけ算が、たし算やひき算とどう違うのかが伝わっていきます。そうした練習の中で私たちが最も力を入れているのは、立式練習やお話づくりです。それは、かけ算の意味をしっかりと理解させるために、どうしてもやらなければならない課題です。かけ算九九の計算をやる前に、またかけ算が足し算の繰り返しだと勘違いさせないためにも、立式と式を見てかけ算のお話をつくる練習を徹底して行います。かけ算イコール九九の暗唱と考えている人たちにとっては、何でそんな面倒なことを・・・と思われるやり方かもしれませんが、今後、文章題に取り組むようになった時にその意味は分かるはずです。2×3も3×2も同じ答えだから、どちらでもいいじゃないかというレベルの議論ではありません。計算主義の日本の算数から抜け落ちていく、数式の意味を理解する大事な学習を徹底しなければ、高学年の文章題で、立式のプロセスが求められたとき必ず壁にぶつかります。算数的な思考は九九の暗唱だけでは身につきません。
一対多対応で学習した、お客さんの問題とタイヤの問題に即し、「一あたり量×いくつ分」の式に当てはめていけば、かけ算が、たし算やひき算とどう違うのかが伝わっていきます。そうした練習の中で私たちが最も力を入れているのは、立式練習やお話づくりです。それは、かけ算の意味をしっかりと理解させるために、どうしてもやらなければならない課題です。かけ算九九の計算をやる前に、またかけ算が足し算の繰り返しだと勘違いさせないためにも、立式と式を見てかけ算のお話をつくる練習を徹底して行います。かけ算イコール九九の暗唱と考えている人たちにとっては、何でそんな面倒なことを・・・と思われるやり方かもしれませんが、今後、文章題に取り組むようになった時にその意味は分かるはずです。2×3も3×2も同じ答えだから、どちらでもいいじゃないかというレベルの議論ではありません。計算主義の日本の算数から抜け落ちていく、数式の意味を理解する大事な学習を徹底しなければ、高学年の文章題で、立式のプロセスが求められたとき必ず壁にぶつかります。算数的な思考は九九の暗唱だけでは身につきません。就学準備のために作ったこの教材は、1年生でも2年生でも、初めてかけ算を学習する子どもたちにとっては有効です。実際にもうすぐ2年生になる子どもたちに、今週からこの教材を使って、かけ算指導を行うつもりです。2年生の後半にならなければ、かけ算の学習は早すぎると批判する人たちにぜひ見ていただきたい幼小一貫授業のひとつです。