週刊こぐま通信
「室長のコラム」最後のセミナーでお伝えしたこと
第550号 2016年10月14日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

首都圏の小学校では面接試験も始まり、いよいよ入試本番です。東京の本試験は、11月1日からはじまりますが、受験生は最後の追い込みに力が入ります。6月から始めた「室長特別受験セミナー」も、10月11日に最終回を迎えました。今回のテーマは、「残り2週間の学力総点検」と題し、学習のみならず、「いかにして一番よい状態で入試を迎えるか」について、過去の経験を踏まえてお伝えしました。話の内容は以下の通りです。
- 第7回 室長特別受験セミナー 「残り2週間の学力総点検」
-
1. 最後の2週間にすべきこと2. 学力点検項目の解説3. あらためて、注意すべき新傾向の問題4. 試験当日とその後に起こる問題の対処法試験日以前および当日
- ベストコンディションで入試を迎えるために - 体調管理・親子関係
- 棄権する場合
- お互いに迷惑をかけないように
- 忘れ物をしない
- 遅刻しないように「早めに」
- 悪天候および災害などの場合に備えて(雨具は必需品)
- トイレの問題
合格発表後に起こる問題- 合格発表から手続きに関し
- 補欠の場合
- 合格を辞退する場合
- 国立受験を目指す場合
試験終了から入学までの学習について- せっかく身につけた学習習慣をぜひ持続してください
- こぐま会では幼小一貫教育の理念に基づき、入試終了後「就学準備クラス」が始まります
学習課題においてこれから2週間ですべきことは、
1. 基礎がしっかりできているかどうか、もう一度確認する
2. 新傾向の問題をもう一度チェックする
この2つです。この2点がチェックできるように、4冊のチェックプリント(1冊6枚・合計24枚のペーパー)をお渡しし、家庭で点検ができるようにしました。基礎的な問題と新傾向の問題を合わせて24枚のペーパーにまとめました。その上で、予想される新傾向の問題のどこで子どもたちがつまづくかを具体的に明らかにし、そこをもう一度復習するようにお願いしました。特に今年は、
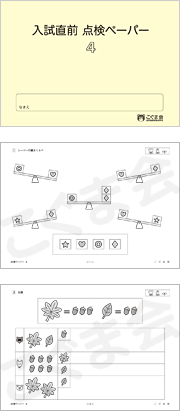
- 飛び石移動
- 交換
- 四方からの観察
- 線対称
- 重ね図形
- 回転図形
- 一音一文字の応用
- 一場面を使った数の総合問題
- シーソーの応用問題
- 魔法の箱
の中から、相当工夫された問題が出されることが予想されます。入試直前の今になっても解決できない問題があれば、それをこそ早急に改善すべきです。その解決のポイントを具体的にお伝えしました。
しかし、今この時期になって、問題が解けないという子はほとんどいません。しかし、ペーパーで点検テストをすると差がつくのはなぜでしょう。大きく2つの理由があります。
- 問題の意図が正確につかめない
- 限られた時間内に処理できない
これを残された時間でどう解決するか・・・それが最後にすべき課題です。
小学校入試は、自分で問題文を読んで解くわけではなく、1回限りの指示を聞き取り、取り組まなければなりません。そこの聞き取りができなければ、どんなに理解力があっても問題の意図がつかめず、はもらえません。正確に聞きとれないのには、いくつかの理由があります。
- ペーパーを見た瞬間、やったことのない問題だと緊張し、予想立てをするが、それが見当外れの場合が多い
- これまでたくさんの難しい問題に挑戦してきた結果、易しいはずの基本問題を、勝手に難しく考えすぎてしまう
- 解き方だけを教え込まれた結果、違った角度から質問されると質問の意味が聞き取れなくなってしまう
これを解決しなければなりませんが、それを短時間に練習する方法があります。それは、ペーパーを出して、質問するまではいつもと同じですが、そのまま子どもにやらせるのではなく、「お母さんがやってみようと思うので、どんな質問だったか言ってみて?」と子どもに先生役をやらせ、問題の意図を言葉で表現させるという方法です。限られた時間の中で「聞き取りの練習」をするには、この方法がお勧めです。仮に、問題をやらなくても、問題の意図がしっかり掴めていれば半分以上成功です。間違える子の多くは、この段階で自分の言葉で説明できない子です。聞き取りが正確にできれば、間違いなくできます。もし問題があるとすれば、あとは、時間内にどれだけ処理できるかという「スピード性」の課題です。スピードに関しては、それほど深刻にならなくてもいいと思いますが、もしこれを練習課題とするならば、「何秒以内にできなければだめ」とプレッシャーを与えるのではなく「頑張ればできるんだ」という自信をどうつけるかということです。こぐま会では、9月以降「スピードトレーニング」と称し、いろいろなことをやってきましたが、子どもたちも運動会感覚で取り組み、とても自信をつけています。たとえば、限られた時間内でどれだけたくさんが描けるかどうかのようなトレーニングでよいのです。何回も繰り返すうちに、頑張ればたくさんできるんだという経験を持たせ、意識を変えさせていくのです。「できない」という不安感を与えるのではなく、頑張ればできるという自信をどうつけるかがポイントです。聞き取りの練習とスピード性の解決の方法はいろいろあると思いますが、我々の経験では以上の方法が一番効果的です。
さて、入試直前になるといろいろなうわさ話で、保護者の皆さまはいろいろ戸惑うことが多いと思いますが、それが入試本番を迎えるにあたり一番避けなければならないことです。小学校受験は特別な受験ではありません。受け入れてくれる学校の先生方も、特別な考えを持っているのではなく、子どもたちを立派な人間に育てるために、専門性を生かして、現場で日々奮闘している方々です。私たちと同じように、だれもが納得する常識的な判断をしています。入試で特別なことが必要だと言っているのは、幼児教室の教師だけです。「~しないと合格できない」「合格するには~しなさい」そんな形式的なことを学校側が求めているはずはありません。求めていないにもかかわらず、うわさ話に拍車をかけるのは、商業主義に満ち溢れた幼児教室の人間だけです。教室の先生に言われたことで、保護者の皆さまが「おかしいな」と思われたら、その感覚のほうが確かだと考えて間違いありません。形を教え込むことが受験対策だと考えている教師たちがなくならない限り、受験で傷つく子どもたちもなくなることはありません。受験には、子どもたちの成長にとって光の部分と影の部分があります。その影の部分を根絶しなければ、何のための受験か・・・ということになりかねません。うわさ話に足元をすくわれないようにしてください。今まで取り組んできたことに自信を持ち、入試までの残り少ない日々を、これまでの生活リズムを崩さないように、子どもを温かく見守り、試験当日元気に送りだしていただきたいと思います。