週刊こぐま通信
「室長のコラム」新傾向の問題分析セミナー
第532号 2016/6/3(Fri)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

応用段階の学習に入り、これから難しい過去問に取り組まなければなりません。最近の入試問題を分析していくと、学校側も問題作成に相当力を入れており、パターン練習で解けてしまうような問題は出さなくなりました。考える力が求められ、指示をしっかり聞いて、作業して答えを見つけ出したり、違う領域の問題が複合されて一つの問題を形成したり・・・と、新しい傾向が見られます。また、ある学校で出された新しい問題が、次の年に他校に波及したりしています。直接学校間で話し合いはないにもかかわらず、工夫された問題づくりにおいてお互いに影響し合っていることは事実です。そうして形成された「新傾向の問題」を分析し、学習の仕方を伝えるセミナーを、5月29日に行いました。60名定員の募集が2日間で満席になるほど皆さまの関心が高く、それに応えるためにできるだけ具体的にお伝えするように努めました。
私が伝えた内容は以下の通りです。
- 第1回室長特別受験セミナー
「新傾向の問題にどう対処すべきか」 - 入試問題変化の背景にあるもの
- (1) 社会の変化
(2) 志願者の学校選び変化
(3) 学校の考え方の変化 - ペーパー試験はどのように変わってきたか
- (1) 知能テスト
(2) 大量のペーパー
(3) ノンペーパー
(4) 現在の方式 工夫された問題 - 新傾向のペーパー問題とその対策
- (1) 領域別分析
(2) 最近の問題とその分析未測量 つりあい/単位の考えかた 位置表象 飛び石位置移動/つみ木を使った四方からの観察 数 一場面の数/交換 図形 図形構成/線対称 言語 言葉づくり/言葉つなぎ その他 作業を通した関係推理 - 行動観察はどのように変わってきたか
- (1) 一時期なぜ「自由遊び」が増えたのか
(2) 最近の傾向は課題を与えた活動
(3) なぜ、2012年度から変化しているのか - 新傾向の行動観察とその対策
- 最近10年間の問題分析
この中で特に時間をかけて説明したのは、「領域別問題分析」のところです。具体的な問題を示し、その中で求められる思考力をどう身につけるかを一つ一つ解説しました。その中で、典型的な問題12問を家庭学習の素材として提供し、「どこでつまづくか」「どう解決していくか」など、そこでみられる子どもの取り組みをお伝えしました。
- 1. 交換
-
上のお部屋を見てください。メロンパン1個は、ドーナツ2個と換えてもらえます。食パン1斤は、メロンパン2個と換えてもらえます。ハンバーガー1個は、メロンパン1個とドーナツ1個と換えてもらえます。
- メロンパン4個は、食パンいくつと換えてもらえますか。その数だけリンゴのお部屋にをかいてください。
- 食パン2斤は、ドーナツいくつと換えてもらえますか。その数だけブドウのお部屋にをかいてください。
- ハンバーガー4個は、食パンいくつと換えてもらえますか。その数だけバナナのお部屋にをかいてください。

- 2. 言葉づくり
- 上にかいてあるものの名前を下の絵の最初の音を使って作ります。使うものにをつけてください。
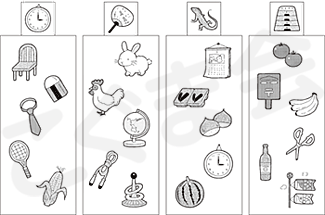
- 3. 図形構成
-
- 大きい三角パズル2枚と、小さい三角パズル2枚を合わせてできる形にを、できない形に×をつけてください。
※試験では、動かせるパズルが大小1枚ずつ渡されていた。
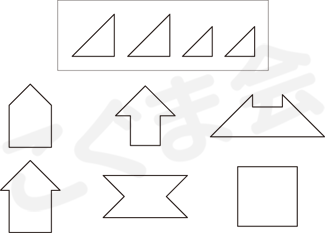
- 大きい三角パズル2枚と、小さい三角パズル2枚を合わせてできる形にを、できない形に×をつけてください。
- 4. ジャンケンを使った関係推理
-
上のお部屋を見てください。お部屋の中の動物は、いつもジャンケンで同じ手を出します。
- ここにあるトーナメント表のように、動物たちがジャンケンをしました。それぞれの勝負で、どの動物が優勝するでしょうか。優勝する動物の下にをかいてください。
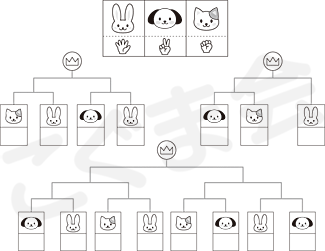
- 5. 飛び石移動
-
カエルとウサギとカンガルーが飛び石を跳んでいきます。3匹は一緒に跳びますが、カエルは1つとばし、ウサギは2つとばし、カンガルーは3つとばしで進みます。
- 3匹がそれぞれ2回ずつ跳んだとき、カエルとカンガルーの間に飛び石はいくつありますか。リンゴのお部屋にをかいてください。
- 真ん中の飛び石の絵を見てください。カンガルーがゴールに着いたとき、カエルとウサギはどこにいますか。カエルのいる場所に、ウサギのいる場所に×をつけてください。
- カンガルーはゴールまで行ったら、今度は折り返して戻ってきます。カンガルーとカエルが一緒に跳び始めると、戻ってきたカンガルーがカエルに会うのは、はじめから数えると、何回跳んだときですか。その数だけブドウのお部屋にをかいてください。
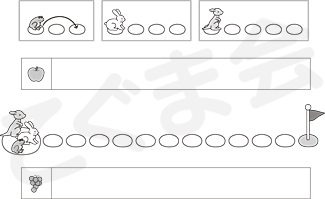
- 6. 広さくらべ
-
- 左のお手本を見てください。白いところと黒いところは広さが同じです。では、右の形の中で白いところと黒いところの広さが同じものを探して、青いをつけてください。
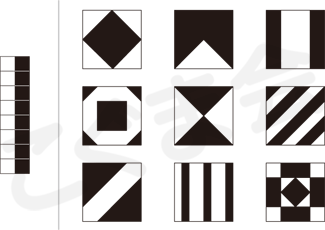
- 7. 四方からの観察
- 4人の子どもたちが、机の上に置いてあるつみ木をそれぞれの方向から見ています。
- 星のお部屋のようにつみ木が見える子にをつけてください。
- 太陽のお部屋のようにつみ木が見える子に△をつけてください。
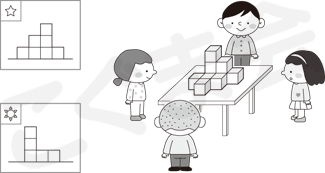
- 8. 言葉つなぎ
-
左のお部屋を見てください。まず練習をしてみましょう。ここにかいてあるものの名前の最後から2番目の音ではじまる言葉を探しましょう。エンピツの最後から2番目は「ぴ」ですね。「ぴ」から始まる言葉はピアノなので、エンピツとピアノを線結びしてください。次にピアノの最後から2番目は「あ」なので、アヒルと線結び・・・というようにつなげていきます。
- 右のお部屋にあるものを今練習したお約束で、できるだけ長くつないで、青で線結びしてください。はじまりはわかりません。使わないものもあります。
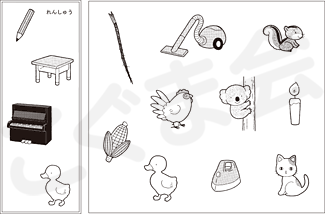
- 9. シーソーの重さくらべ
-
- 1番上のお部屋のシーソーをよく見てください。イヌ1匹とサル1匹を比べるとサルの方が重く、イヌが2匹ならサル1匹よりもイヌの方が重くなっています。では、下のシーソーのように乗せるとどうなるでしょう。シーソーの下がる方にをつけてください。
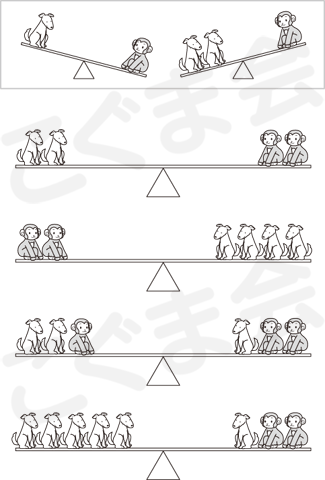
- 10. 図形構成
-
- 上にある3つのパズルを使って、左の形を作ろうと思います。それぞれどのパズルをいくつ使えばできるでしょうか。使うパズルのお部屋に使う数だけをかいてください。
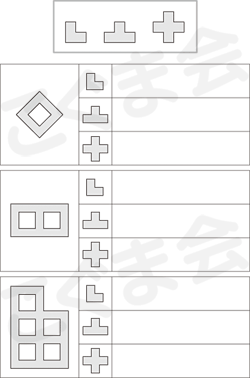
- 11. 数の総合問題
-
動物たちが運動会をしています。
- サルとウサギの数の違いはいくつですか。その数だけイチゴのお部屋にをかいてください。
- 応援をしている人で、手を挙げているのは何人ですか。その数だけミカンのお部屋にをかいてください。
- 応援をしている人の中で、手を挙げていて、ウサギとイヌの間にいる人にをつけてください。

- 12. 線対称
-
- 左のお手本を右の黒いところに置いて、鏡に映すとどのように見えるでしょうか。お日様のマスに青でかいてください。
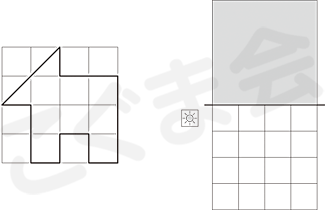
新傾向の問題が、必ずしも難問というわけではありません。ただし、これまでの問題と違って、次のような点が子どもにとって難しい内容となります。
- 指示をしっかり聞き取り、問題の意図を理解した上で、作業しながら答えを見つける
- 視点を変えてものごとを考えるタイプの問題が多い
- 小学校の特殊算につながる考え方を求める問題も出始めた