週刊こぐま通信
「室長のコラム」入試が変わる(6) 常識問題がなぜ増えているのか
第487号 2015/6/19(Fri)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

小学校入試の問題を分析する際に、我々が「常識問題」として括っているものは、主に入学後の「生活科」につながっていく内容です。以前は、「理科」・「社会」としてあった教科が低学年ではなくなり、「生活科」となっています。その生活科につながる内容は、大きく「理科的常識問題」と「社会的常識問題」に分けられます。このほかに一般常識があり、入試問題として次のようにまとめることができます。
| (1) 理科的常識 | 季節の行事・季節の花・季節の食べ物・野菜や果物が育つ場所・野菜や果物の断面図・生活音や自然音の判別・ものの浮き沈み・光と影・風向き・鏡映像・色の混合・斜面の転がり方・力の強さ |
| (2) 社会的常識 | 交通道徳・善悪判断・公衆衛生・仕事と働く人々・標識理解 |
| (3) 一般常識 | ものの数え方(数詞)・昔話の理解・童謡の理解・音を聞いて絵を描く |
こうした、どちらかと言えば知識に訴える問題は、受験者の多くがほぼ間違いなく満点を取っていました。ですから常識問題で差がつくことはあまり考えられませんでした。ところが最近の常識問題は、簡単にがもらえる問題ではなくなってきています。その大きな理由は、自分の経験を通さない知識の詰め込みでは、対処できなくなっているからです。以前にも紹介したように、今年の次のような問題は、その典型例です。
- 「常識」(2015年度入試 雙葉小学校)
- 今の季節は秋です。これから咲く順番で考えると、4番目に咲く花にをつけてください。

- 今の季節は秋です。これから来る楽しい日の中で、3番目に来るものにをつけてください。
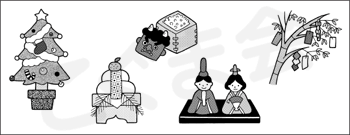
- 今の季節は秋です。これから咲く順番で考えると、4番目に咲く花にをつけてください。
4つの季節に分けるこれまでの問題より一歩進んで、同じ季節の行事でも順番があるということを問いかけています。それはすなわち、自分自身の経験を通して考えていかなければならない問題です。また、登場人物について問いかける昔話の問題も、実際に絵本やDVD等で見聞きしているということを前提に設問がつくられています。昨年秋に行われた入試で出された問題の一部を紹介すると、次のようになります。
- 「常識(職業)」 (2015年度入試 聖心女子学院初等科)
- 上のお仕事をしている人が使うものはどれですか。真ん中と下からそれぞれ1つずつ選んで、エンピツで線結びしてください。
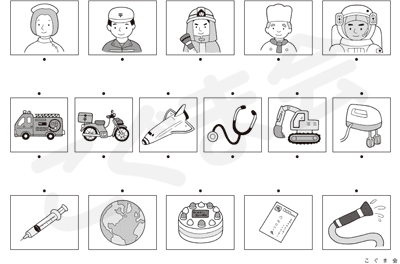
- 上のお仕事をしている人が使うものはどれですか。真ん中と下からそれぞれ1つずつ選んで、エンピツで線結びしてください。
- 「理科的常識」 (2015年度入試 学習院初等科)
- 上にある果物を半分に切ったらどうなりますか。下から選んで赤で線結びしてください。
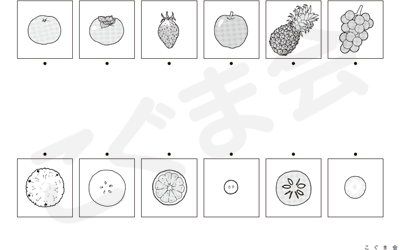
- 上にある果物を半分に切ったらどうなりますか。下から選んで赤で線結びしてください。
- 「理科的常識」 (2015年度入試 洗足学園小学校)
- それぞれの左にあるお花の葉っぱを右から選んでをつけてください。
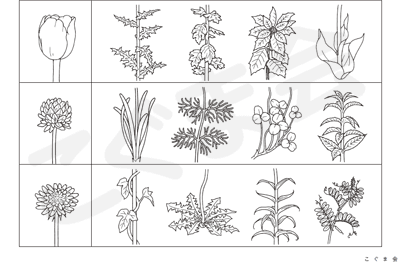
- それぞれの左にあるお花の葉っぱを右から選んでをつけてください。
- 「常識」 (2015年度入試 立教女学院小学校)
-
これから歌が流れます。よく聞いて後の問題に答えてください。
※「どんぐりころころ」の歌が流れます。
「♪どんぐりころころ、どんぶりこ おいけにはまって さあたいへん どじょうがでてきて こんにちは ぼっちゃん いっしょに あそびましょう」- 今の歌に出てきたものを1番上のお部屋から探して、をつけてください。
※「とんぼのめがね」の歌が流れます。
「♪とんぼのめがねは ぴかぴかめがね おてんとさまを みてたから みてたから」- トンボの子どもを上から2番目のお部屋から探して、をつけてください。
- お天道様はどれですか。上から3番目のお部屋から探して、をつけてください。
※「ちょうちょう」の歌が流れます。
「♪ちょうちょう ちょうちょう なのはにとまれ なのはに あいたら さくらにとまれ さくらのはなの はなからはなへ とまれよ あそべ あそべよ とまれ」- 今の歌に出てきた花を下から2番目のお部屋から探して、をつけてください。
※「やまのおんがくか」の歌が流れます。
「♪わたしゃ おんがくか やまの こりす じょうずに バイオリンを ひいてみましょう
キュキュ キュッキュッキュ キュキュ キュッキュッキュ キュキュ キュッキュッキュ キュキュ キュッキュッキュ いかがです」- 今の歌に出てきた動物と楽器を1番下のお部屋から探して、をつけてください。
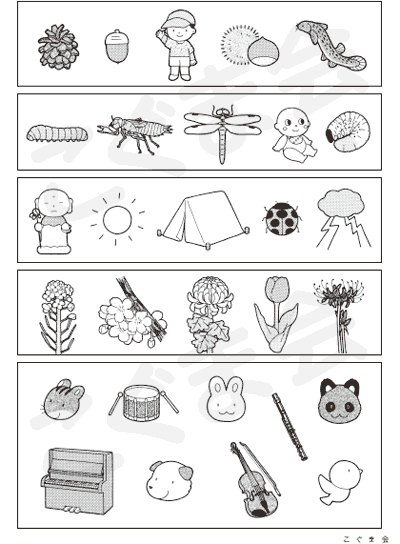
- 「常識(歌の理解)」 (2015年度入試 慶應義塾横浜初等部)
-
※「うれしいひなまつり」の歌が流れます。
- 今の歌に合う絵が1つあります。それに赤いをつけてください。
※「お正月」の歌が流れます。- 今の歌に合う絵が2つあります。それに赤いをつけてください。
※「七夕さま」の歌が流れます。- 今の歌に合う絵が1つあります。それに青いを1つつけてください。
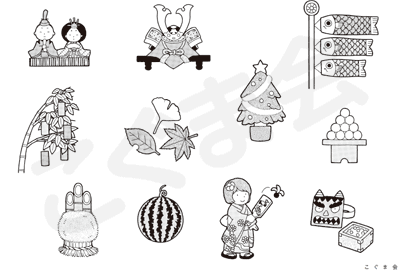
- 「常識(季節)」 (2015年度入試 東京学芸大学附属小金井小学校)
- ここにある4つのお部屋の中で、左から季節の順番が正しく並んでいるものはどれですか。右にをかいてください。
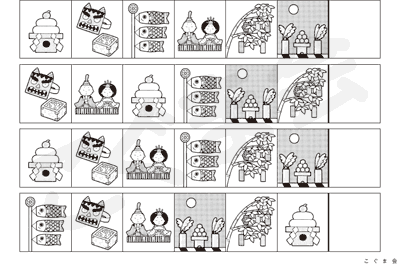
- ここにある4つのお部屋の中で、左から季節の順番が正しく並んでいるものはどれですか。右にをかいてください。
- 「常識(社会的常識)」 (2015年度入試 東京学芸大学附属大泉小学校)
- 上のお部屋を見てください。お友だちと2人で遊んでいたら雨が降ってきました。あなただったらどうしますか。「自分だけお部屋に入る」、「気にしないで雨の中で遊ぶ」、「水たまりの中に入って遊ぶ」、「お友だちと一緒にお部屋に入る」お部屋の中から選んでをつけてください。
- 真ん中のお部屋を見てください。風邪をひいて寝ていたお母さんが、夕ご飯を作っています。あなただったらどうしますか。「早く作って、と泣いて頼む」、「お手伝いをする」、「早く!早く!と言う」、「冷蔵庫にあるものを自分で出して食べる」お部屋の中から選んでをつけてください。
- 下のお部屋を見てください。外国人のお友だちが、あなたのお家に来て一緒に遊ぶことになりました。あなただったらどうしますか。「話しかけられたら聞こえない振りをする」、「静かに一緒にテレビを観る」、「お名前を聞いてみる」、「その子のお友だちになるのをやめる」お部屋の中から選んでをつけてください。
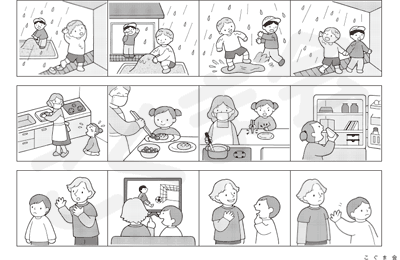
- 「常識(昔話)」 (2015年度入試 横浜雙葉小学校)
- 上のお部屋の中で、打ち出の小槌が出てくるものにをつけてください。
- 上のお部屋の中で、柱時計が出てくるものにをつけてください。
- 下のお部屋の中で「シンデレラ」と「おむすびころりん」の両方に出てくる生き物にをつけてください。
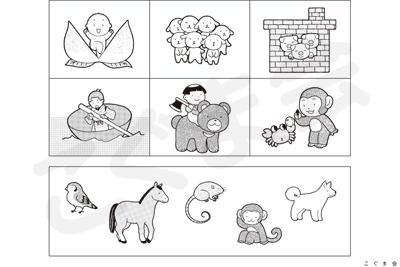
こうした問題が出てくる背景をどのように考えればよいのでしょうか。将来の「生活科」の学習に備え、知識を豊富に持っていることを求めているのではありません。常識問題がたくさん出されているのは、その問題を通して、その子の5~6歳児としての経験を問いかけられているのです。すなわち、普段の生活の中で、そうした経験を持っているかどうか、また、年齢にふさわしい経験を通して、将来の学習の基礎が出来上がっているかどうかを見ようとしているのです。多様化した問題を見て、たくさんの図鑑を買い込んで知識を増やすのではなく、その一つ一つについて実際に経験してみるという発想が大事です。そうした経験の有無をチェックし、年長児にふさわしい「育ち」をしているかどうかが問われているからです。
常識問題は、体を通して理解させることを原則として行うべきです。ですから、とても時間のかかる課題でもあるわけですが、子どもにとってはとても楽しく、生活を豊かにする経験になるはずです。