週刊こぐま通信
「室長のコラム」間違った受験対策をしていませんか
第242号 2010/4/30(Fri)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可
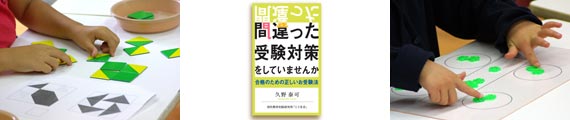
秋の受験まで残すところ半年になりました。こぐま会ばらクラスの学習も4月いっぱいで基礎段階の学習を終え、5月から応用段階の学習に入ります。夏休み前までにすべての課題を終了し、受験準備にとって最大の山場である「夏の学習」とそれに続く「入試直前の予想問題学習」に備えます。子どもの理解の道筋と学習の系統性を踏まえ、きちんとした「合格カレンダー」のもとで計画的に学習を進め、本試験を迎えます。難しい応用問題を自分の力で解いていけるよう、考え方の基礎をしっかり固めるために、基礎段階の学習は昨年11月からはじめて、この4月まで6ヶ月間を要しました。基礎といえども、入試問題の8割方はこれまで学習した単元に関連した課題です。しかし、教育相談に見える多くの方々が、すでに過去問を学習し終えたのにもかかわらず、「テストで良い成績が取れないのでこれからどうしたら良いのか」と悩んでいるのです。難しいペーパー問題はできても、基本的な質問に答えられない・・・・こうした相談は年を追うごとに増えています。そして、今からでもよいので「事物教育を受けたい」というのです。私はこうした皆さんの教育相談に応じていて最近つくづく思うのは、やはり間違った受験対策をされて、子どもの成績の伸び悩みに苦労されている保護者の方々が多いのではないかということです。間違った受験対策の一番の原因は、学習の順序を間違えているということです。
受験対策の初めからペーパー学習が先行し、難しい過去問を解くことが受験勉強だと思われている方々は非常に多いのではないかと思います。事物を使った教育はやさしくて、ペーパーを使った学習が難しい、だから一刻も早くペーパーで過去問に取り組みたい・・そうした保護者の要求に応える形で、何をどう育てたら良いのかわからない指導者が、手っ取り早いペーパー学習になだれ込んでいく構図は手に取るようにわかります。考える力が備わっていない子どもが、教え込まれた方法で問題を解いていっても、本当の学力は身につきません。その結果、理由を問われる問題や、新しい初めての問題に手がつかず、点が取れないのです。つまりはっきり言えば、本当に解っていないのです。1枚のペーパーをもっと大事にし、どんな考え方が求められているのかをつかんでおくことが必要です。本当に理解しているのかをチェックする方法は簡単です。答えの根拠を説明させればよいのです。それができなければ理解したことにはなりません。ペーパー学習の落とし穴は「解らなくてもできてしまう」ことです。本当に理解してペーパー問題を解決していかなければ、工夫された最近の新しい問題に対処することはできません。
こぐま会では、出版物の製作もしている関係でオリジナルのペーパー教材の原版を何千枚と持っています。しかも、現在でも新しい教材を作り続けています。しかし、この何千枚のペーパーをこなすことが受験対策ではなく、1枚1枚のペーパーで求められている「考える力」を掘り下げ、それをどのように身につけたら良いのかを指導するのが教師の役割のはずです。そのためには、幼児の場合どうしても「事物を使った教育」が最初にあるべきです。最初からペーパーを使った学習では、新しい認識を育てることは絶対にできません。幼児の認識は、物事に働きかけることを通して育っていくからです。そうした最低限の教育原理もわからない素人が、「受験対策」と称して幼児の教育指導に携わっているのが現状でしょう。これでは子どもたちがつぶされていくのは当然です。その子にとって初めての集団教育が、教育の原則も何もない「たたき込みの指導」では、たとえ受験対策といえども、子どもの将来のためにはなりません。
では、どうしたら良いのでしょうか。ペーパー学習を中心に進めてきた皆さんにぜひお願いしたいのは次のようなことです。1枚1枚のペーパーには単元名がついていますが、その単元を超えて、一体このペーパーで、どんな能力が求められているのか、どんな能力を育てればこの問題を解決することができるのかを考えてみてください。そうすることによって、学習単元を超えて身につけなくてはならない「考える力」が見えてくるはずです。私たちが基礎段階の学習で育てようとした「考える力」の基本は、領域を超えて存在します。だからこそ「基礎は簡単」では済まされないのです。最初からペーパー学習で行う受験対策では、こうした「考える力」の基本が身につかないまま、解き方(形式)だけを教え込まれていく結果になるのです。
20年以上も前の試験で、20枚も30枚もペーパーを出していた学校が、なぜ5~6枚のペーパー試験に変えたのか。そこではどんな問題が出され、どんな能力が求められているのか。「転移する学力」という考え方がありますが、100の課題を100通りの練習で解決するのではなく、100の課題を10の練習で解決するような学力を育てるべきです。それが「考える力」の基本ということになるのです。各領域の課題を一つ一つこなすことによって、いったい子どもの内に何を育てるのか。それが今、いろいろ形を変え、新しい問題として具体化されているのです。そこを見抜かないと、どんなに時間をかけても、どれだけたくさんのペーパーをこなしても不安は募るばかりです。領域を超えて、子どもたちが身につけなくてはならない考える力の基礎を整理してみると、大体 以下のようにまとめることができます。
- 学習単元を超えて身につけるべき「考える力」の基本
- 1. 比較する
- 数の比較・量の比較・図形の比較
- 2. 違いを探す
- 二者の異同・一対一対応・同図形発見
- 3. 系列化する
- 量の系列化・位置の系列化・時間の系列化
- 4. 相対化する
- 量の相対化・位置の相対化
- 5. 関係を考える
- 三者関係の推理・言葉による関係推理・交換
- 6. 視点を変えてものを見る
- 左右関係・四方からの観察・観点を変えた分類・数のやりとり
- 7. 対応づける
- 一対一対応・一対多対応・順対応・逆対応
- 8. 等分する
- 量の等分・数の等分・図形の等分
- 9. まとめる
- ひとまとまり・包含除
- 10. 構成する
- 数の構成・図形の構成
- 11. 分割する
- 数の分割・図形分割
- 12. 法則性を理解する
- 並び方の法則性・変化の法則性・回転推理
- 13. 変化に対し敏感になる
- つみ木の変化・量の変化・場面の変化
以上のような考え方の基本を、それぞれの領域を超えて育てることが、学校側が求めている教科学習のためのレディネス、つまり「転移する学力」なのです。こうした能力は、ペーパー学習だけでは決して身につきません。基礎は簡単、応用は難しい、過去問はなおさら難しい・・・だから過去問に一日も早く取り組みたい・・・その考えが間違いであることが、お分かりいただけたでしょうか。残り半年間となった今年の入試に向け、今多くの受験生がぶつかっている壁は、「家ではできるけれど、テストになると点が取れない」ということでしょう。その原因は明確です。本当に解っていないと考えるべきです。その多くが、これまでの間違った受験対策の結果であるということを、真摯に受け止めるべきです。まだ間に合います。もう一度事物やカードに戻って、試行錯誤させ、考え方の基本を点検してください。