こぐまオリジナル知育教材小学校受験学習の基本アイテム -3つの具体物と教科書-
小学校受験学習を始める際に必要な3つの具体物をご紹介します
就学前の3~5歳児にとって、問題集や過去問を行うだけ(ペーパー学習だけ)では本当の理解力は身につきません。具体物などの事物経験を行い試行錯誤することにより、物の本質を捉えることができます。その上でペーパー学習を行い、内面化することで理解力が高まり、応用問題にも対応できるようになります。
また中学・高校・大学受験と異なり、お子さまが1人で学習するのではなく、基本的に保護者が付き添い、1問1問「どうしてそう思ったの?」と問いかけ、ただ答えが合っているかだけでなく、結論に至る過程を大事にして、お子さまの考え方の確認をしながら学習を進めることをお勧めします。
幼児期には教科書がありませんので、学習を始める前に保護者が学習の内容をしっかり理解する必要があります。学習意図・学習順序・指導方法を理解してから始めてください。
- おはじき
- さんかくパズル
- 立方体つみ木
- ひとりでとっくん365日
数の学習-おはじき-
数の学習で必要になる具体物は「おはじき」です。数の学習をする順序として、
- 1. 数を数える(数唱)
- 20までの数を正しく唱えられるようにしましょう。
「・・・15、16、18・・・」と数を飛ばしてしまうことがありますので注意してください。 - 2. 「おはじき」を20個用意して、数唱と指で数えるスピードを合わせて数えてみる。
- 数唱で「1」の時に1つ目の「おはじき」を指差し、「2」の時に2つ目と一致しているか注意してください。
- 3. 30個の「おはじき」から20個を正しく取る(「ひとりでとっくん16:分類計数 」)
- 他にも、たくさんの「おはじき」から「青のおはじき」を取る(その上で数える)などするとよいでしょう。
※日常生活でも、「おはじき」と「青のおはじき」の関係のようなものはたくさんあります。
例えば、「食べ物」と「野菜・果物・魚」などの関係で言えば、「食べ物」が「おはじき」で、「野菜・果物・魚」が「青のおはじき」の関係になります。
さらに、「野菜」が「おはじき」だとすると、「青のおはじき」は「人参・大根・玉ねぎ」などになります。果物ならリンゴ・ミカン・スイカなど、魚なら鯖・鮭・鰤なども同様です。
上記の「野菜・果物・魚」のような総称を表す言葉を「上位概念」と言い、「人参・大根・リンゴ・ミカン・鯖」などのひとつひとつの物の名称を表す言葉を「下位概念」と言います。
この2つの概念をしっかりと豊富に理解する事はとても大切です。子どもの特徴として、とくに魚などは上位概念だけになりがちですので日常生活の会話の中で意識して取り組むと良いでしょう。
数学習の「ひとりでとっくん84:仲間集め 」、「ひとりでとっくん29:仲間はずれ 」などの学習に繋がります。 - 4. 同じ数を探す(「ひとりでとっくん10:同数発見 」)
- 「ここにあるおはじきと同じ数のおはじきを出してください」
(保護者が)8個「おはじき」を出しておいて、お子さまがたくさんの「おはじき」から8個を取り出せるようにしましょう。取り出す数は5~20くらいまでの数でいろいろ変化させてみてください。 - 5. 10の構成 (「ひとりでとっくん38:数の構成 」)
- 「数がいくつといくつでできているか」を考える問題です。この「数の構成」は今後の算数学習においても大きな意味を持つ大切な課題です。最初は「5の構成」から始めて6・7・8と順に増やすようにしてください。
- 例題1
(おはじきを3個出して)
「3といくつで5になりますか。その数だけおはじきを出してください」 - 例題2
(「おはじき」を5個並べて、子どもに確認させる。そして目をつぶらせて(保護者が)4個隠して目を開けさせてから)
「隠したおはじきは何個ですか」
※答えは4個ですが、子どもは見えている「1個」と答えてしまう場合があります。分からないときは、別の「おはじき」を5個横に並べてあげると隠れている「おはじき」がイメージしやすくなります。
- 例題1
- 6. 一対一対応(「ひとりでとっくん05:数の多い少ない 」)
- (「赤のおはじき4個」と「黄色のおはじき6個」を用意して)
「どちらがいくつ多いですか(少ないですか)」
※「多いですか」と質問したら2問目に「少ないですか」と逆も問うとよいでしょう。その次に「同じ数にするにはどうしたらよいですか」※お子さまがどのように答えを導き出すのか手の動きに注意してください。ひとつひとつのおはじきを対応させていなかったり、分からないようであれば「おはじき」を図のように並べてください。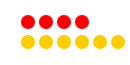
その他にも「ひとりでとっくん33:等分 」、「ひとりでとっくん35:一対多対応 」、「ひとりでとっくん46:数の増減 」、「ひとりでとっくん62:数のやりとり 」など数のいろいろな単元でも「おはじき」で事物経験を積んだ上でペーパー学習に取り組んでください。
ドーナツおはじきセット
例)「赤・黄色・青・ピンク・赤・黄色・青・ピンクの順に紐に通してください」
図形の学習で必要になる具体物は「パズル」と「つみ木」です。平面図形では「パズル」、立体図形では「つみ木」になります。
こぐま会では、学習意図・難易度に合わせてさまざまな「パズル・つみ木」をご用意していますが、その中でも中心となる「さんかくパズル」と「立方体つみ木」についてご紹介いたします。
図形の学習-さんかくパズル-
平面図形において最も基本となるのは「図形構成 」です。
図形構成の学習は、「ピクチャーパズル 」から始めて、「基本図形パズル 」(3~5片でできた○△□)、「さんかくパズル」の順番で学習することをお勧めします。

小学校入試における平面図形学習のベースになるのが「さんかくパズル」です。このパズルは1ピースが直角二等辺三角形でできています。このピースを使ってできる基本形が下記のようになります。
- 2枚を使って作る三角形・正方形・平行四辺形
- 4枚を使って作る三角形・正方形・長方形
- 8枚を使って作る三角形・正方形・長方形
下の図1では三角形2枚、図2は図1の三角形が2つでできます。つまり2枚で三角形ができれば、それぞれを組み合わせて4枚・8枚での三角形もできます。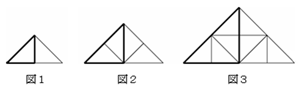
この考え方は三角形の大きさを相対的に捉える必要があり、抽象的な見方が要求されます。子どもに口頭で説明しても理解しづらいので、実際に繰り返し作業することで身につけてください。
まずは以下の図の基本形を繰り返し練習してください。基本形ができれば、形が変化したり枚数が増えたりする応用も対応できるようになります。
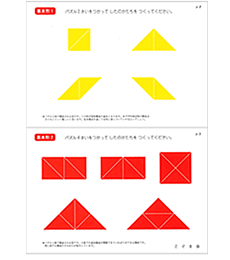 また、図形構成をしっかり身につけることで「図形分割 」にも繋がります。
また、図形構成をしっかり身につけることで「図形分割 」にも繋がります。
さんかくパズル
関連教材
図形の学習-立方体つみ木-
こぐま会では「立方体つみ木」、「こぐまつみ木 」、「ドームつみ木 」と立体図形学習のつみ木をご用意していますが、その中で基本となるのは「立方体つみ木」です。
立体図形を認識していくために、意識を平面から三次元へ広げる必要があります。また1つのつみ木が全体のどの部分に対応するかを考える事で、全体と部分の関係を捉えて立体図形の認識を高めましょう。
学習方法としては、
- まず、お子さまに基本形を積んでもらいます。
※子どもは真っ直ぐに積んでしまいがちですが、図のように尖った部分を自分の方に向けて斜めになるようにすると、立体感がつかみやすくなります。できれば2組用意して、1組で保護者が見本を作ってあげるとより分かりやすいでしょう。

- お子さまの見ている前で、見本のつみ木を1個動かして変形します。
その後、同様につみ木を動かしてお子さまに同じ形を作ってもらいます。※毎回つみ木をバラバラにしないで、基本形から変化させてください。それによりつみ木を構造的に捉えることができます。
1個動かしてできたら元に戻す。次に2個・3個と順に増やしてください。下の(3)(4)も同様です。
- お子さまに目を閉じてもらい、見本を1個動かします。
目を開けて、何を動かしたか推測して見本と同じ形を作ってもらいます。 - お子さまに目を閉じてもらい、見本を1個動かします。
30秒ほど見せたら見本を隠して同じ形を作ってもらいます。(記憶して作る) - 見本帳を見て立体をイメージして作ります。※見本帳は平面に描かれている形を立体と認識できなければいけませんので難しくなります。(2)~(4)を十分に繰り返し練習した後で取り組んでください。
立体図形を正確に捉えることにより 「つみ木の数 」、「立体と展開図 」などの図形学習に繋がります。
立方体つみ木
関連教材
ひとりでとっくん18:8個のつみ木
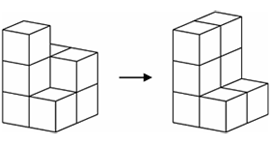
幼児期の教科書-ひとりでとっくん365日-
小学生以降と異なり、幼児期には系統的な学習ができる教科書がありません。そのため、とくに小学校受験をする方は、最初から過去問や難しい問題を子どもに与えてしまうことがあります。しかし学習は積み重ねが大切です。とくに幼児期であれば発達の段階に合わせた系統的な学習が必要になります。
こぐま会では「子どもたちが物事をどのように理解していくのか」、難しい小学校入試問題を理解するためには「何をどのように学習していけば良いのか」を具体的な問題として表した「ひとりでとっくん365日」を出版しています。とくに家庭学習で一番必要なのは、指導者である保護者が正しい学習知識を得ることですので「保護者のための学習ノート(指導書)」を付属しています。
この学習ノートは下記の内容で編集されています。
- 各単元の学習の目的と学習ポイント
- 単元の内容をさらに深めるための関連こぐまオリジナル教材の紹介と使用方法
- 家庭で行う季節行事の紹介
- 実際に小学校入試で出題された実例と分析
学習を始める前によく読んでからお子さまと一緒に学習してください。
また学習順序は、01号から始めて02号、03号と順番に進めることで系統的な学習ができるようになっています。年中の夏から秋頃から始めますと、発達の段階でも小学校受験をされる場合でも最適です。
ひとりでとっくん365日(全12冊・問題集+指導書)








