週刊こぐま通信
「今何を学習すべきか」常識15 理科的常識15 水量の変化
2008/02/08(Fri)
今回は、水量の比較について考えていきたいと思います。「ひとりでとっくん55 理科的常識2」の23ページに次のような問題があります。
左のコップの中の石を取るとコップの水はどうなりますか。をつけてください。
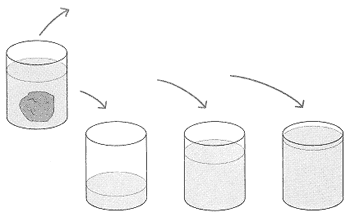
(正解)左のコップに
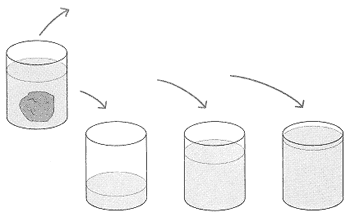
(正解)左のコップに
この問題は、体積の問題です。物体を水に入れると、その体積分の水をはねのけます。この問題では、はじめは水中に入っている石の体積分だけ水位が上がっているわけですから、逆に石を取ったら、その石の体積分だけ水位が下がります。ですから、一番左のようになります。このように科学的に理解できなくても、石をどけたところに水が流れ込んで、その分だけ水の高さが低くなると考えればいいと思います。これを理解していくためには、これとは逆の考え方を子どもにさせるといいでしょう。いっぱいにお湯の入ったお風呂に自分が入ったとき、お湯がザーッとあふれ出たという体験を、みんな少なくとも一度はしたことがあると思います。下の問題がそのような問題です。
(「ひとりでとっくん55 理科的常識2」の26ページより)
左の絵のように男の子がお風呂に入るとどうなるでしょう。をつけてください。
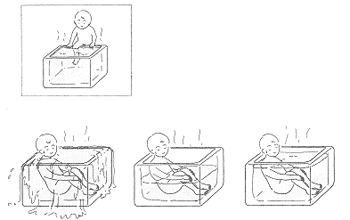
(正解)左の絵に
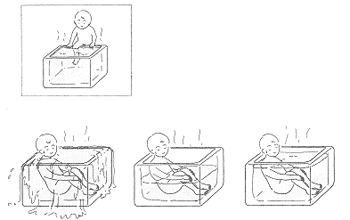
(正解)左の絵に
こうした問題を通して、何かを水に入れたら水位が上がる、ということをいろいろな事例から理解させるようにしてください。
さらにこの問題は、逆対応に発展していきます。例えば、体格の違ったお父さんと残った水量の異なったお風呂を見て、どのお父さんがどのお風呂に入ったかを考えさせる問題があります。お風呂に入ったとき、体が大きければ大きいほどお湯があふれて、残った量は少なくなりますので、一番太ったお父さんは、たくさんお湯をはねのけ、残りは一番少なくなります。ですから、二番目に太ったお父さんは、二番目に残りの少ないお風呂に入ったのだと考えられることになります。
「ひとりでとっくん37 ぎゃくたいおう」にこうした問題がたくさん載っていますので、ぜひ練習してください。