週刊こぐま通信
「室長のコラム」2023年度「第1回 全国幼児発達診断テスト」結果分析
第852号 2023年4月14日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

昨年度、延べ1万人(3回合計)近くの幼児が参加して行われた「全国幼児発達診断テスト」 を今年も実施することになり、その第1回を3月16日~30日に行いました。今回は1,836名の新年長児・新年中児にテストを受けていただきました。問題を作成するにあたり、次の点を確認しています。
- 小学校入試のための模試ではなく、将来の教科学習の基礎が身についているかどうかを確認するテストにする。そのため、平均点が70点ぐらいの難易度にする
- 通塾しているかどうかに関係なく、できる限り普段の生活や遊びの中で身についた「考える力」を見る問題とし、訓練によって身につけた力を見る問題はできるだけ避ける
- 年長児を対象にするが、年中児でも理解できる問題とする
さて、今回の参加者の内訳と平均点は次の通りです。
- 学年
- 年中児:533名 / 年長児:1,303名 / 合計:1,836名
- 地域
- 東京:698名 / 千葉・埼玉・神奈川 3県合計:362名 / 地方:776名
- 通塾の有無
- 通塾なし:1,272名 / 通塾あり:564名
- 総合平均点
- 全体:64点 / 年中:53点 / 年長:69点
以上のデータから、今年の第1回テストの結果を次のようにまとめることができます。
- 申込者数に比例して回答者数も全体的に増加
- 学年別受験者数は、昨年の第1回テストとほぼ同じ割合(新年中3:新年長7)
- 参加者のエリア別人数を見ると、地方受験者が昨年の3割から今年は4割に増加し、それが全体の受験者数を押し上げた要因
- 通塾状況による分類では、今年は塾に通っていない子どもの受験者比率が高い
- 全受験者の平均点は、今年のほうが昨年度より低い
- 領域別でみると、今年は図形・言語・生活 他の得点が低かった
- 通塾別平均点は、通塾している子どもはしていない子どもに比べ、全領域で8%程度の差でよい点数を取っている
【通塾状況】
| 通っている | 通っていない | 全体 | ||
| 領域別 平均得点率 | 未測量 | 76% | 68% | 71% |
|---|---|---|---|---|
| 位置表象 | 64% | 57% | 60% | |
| 数 | 77% | 67% | 71% | |
| 図形 | 65% | 56% | 59% | |
| 言語 | 66% | 58% | 61% | |
| 生活 他 | 72% | 65% | 68% | |
| 受験者数 | 698人 | 1,138人 | 1,836人 | |
| 総合平均点 | 69点 | 61点 | 64点 | |
また、今回の問題別の平均点は次の通りです。
【問題別の平均点】
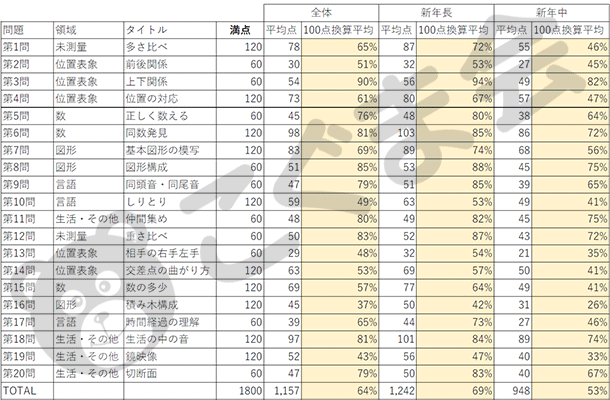
上の表を分析し、今後の課題について述べたいと思います。
- 全体の平均点が64点、年長の平均点が69点、年中が53点ということで、年長児に合わせて作ったテストとしては、難易度は適切であったと思います。同じテストを年中児が受けているわけですから、平均点が53点というのは予想以上に頑張ったと思います。生活の中での学びがしっかりできている証拠だと思います。テストが終わったあとの、保護者さまへの難易度に関するアンケートを見ても、非常に難しい 11%、難しい 44%、普通 34%、やさしい 10%、非常にやさしい 1%となりましたが、年齢による受けとめ方の違いや、通塾しているかどうかも大きく影響していると思います。
- 年長児で平均点が50点を下回ったのは、つみ木の課題と鏡映像の課題です。まず、つみ木の課題をご覧ください。
- つみ木構成(領域:図形)
- 5つのつみ木の中で、「例」の見本のつみ木から1個だけ動かしたつみ木はどれですか?赤い鉛筆でを書いてください。答えは一つではありません。
- 5つのつみ木の中で、「例」の見本のつみ木から2個動かしたつみ木はどれですか?赤い鉛筆でを書いてください。答えは一つではありません。
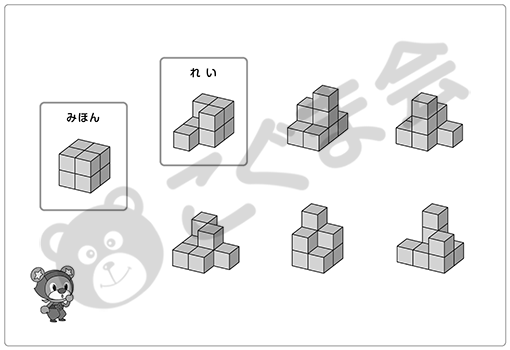
基本となる形から1個だけ動かしてできる形、2個動かしてできる形を探す問題です。変化している部分と変化していない部分を見極めることができるかという空間認識の問題でもあり、こうした空間認識が将来の図形教育に生きてきます。次に、鏡映像の問題をご覧ください。
- 鏡映像(領域:生活 他)
- ウサギさんが一人でボートに乗って、大きな池であそんでいます。風がない穏やかな日で、池は波もなく、鏡のようにしずかです。いま、ウサギさんが、きれいな池の面を覗き込んでいるところです。よく絵を見てください。さて、問題です。
ウサギさんが覗いているきれいな池には、いろいろなものが鏡のように映り込んでいますが、どこかおかしなところがあるようです。ここはおかしいと思う場所ごとに、赤い鉛筆でを書いてください。答えは一つではありません。
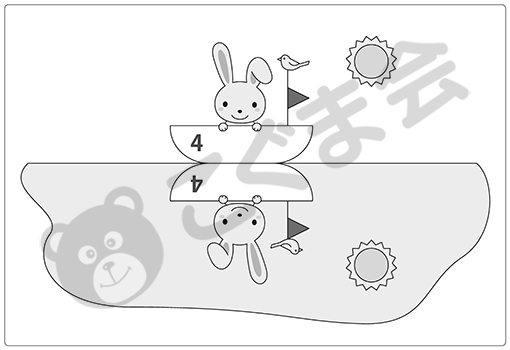
- ウサギさんが一人でボートに乗って、大きな池であそんでいます。風がない穏やかな日で、池は波もなく、鏡のようにしずかです。いま、ウサギさんが、きれいな池の面を覗き込んでいるところです。よく絵を見てください。さて、問題です。
池への映り方のおかしなところを探す問題で、対称図形の基礎となる鏡映像の課題です。普段何気なく見ているものの映り方、特に「反射」について、理解を深めるきっかけにしてください。 - 新年中の子どもたちが平均点50%以下の問題は、20項目のうちの半分の10項目あります。これが年長児と年中児の理解度の差だと思います。その中で、年長児にとっても難しかった「つみ木構成」と「鏡」以外で注目していただきたいのは、「相手の右左」「交差点の曲がり方」の2つです。これは「位置表象」領域の中の「左右関係の理解」にあたりますが、内容は自分以外の立場に立って右左を判断できるかどうかです。向かい合ったお友だちの右手が自分の左手側にあるという理解は、「交差点の曲がり方」で右左を考える問題にも共通していて、車を運転する人の立場に立って左右を理解できるかどうかです。これは「視点を変えてものを見る」という大事なものの見方の一つで、いろいろな場面で問われます。こうした問題を通してこの思考法をしっかり身につけてください。また逆に、新年中の子どもたちもよくできた課題は、上下関係の理解、同数発見、図形構成、仲間あつめ、生活の中の音などです。
今回の問題は、こぐま会の授業ではstep1~3までの内容です。また「ひとりでとっくん365日」の内容では、1~6までの内容に即しています。今後、テストが2回、3回と進んでいくにつれ問題も難しくなっていきますが、ぜひ3回とも受けていただき、将来の学習の基礎として何がわかっていないのかをしっかり把握し、それにつながる学習をペーパーだけでなく、生活や遊びの中の事物体験を通して解決できるようにしてください。
- 重版決定!! こぐま会代表 久野泰可 著「子どもが賢くなる75の方法」(幻冬舎)
読み・書き・計算はまだ早い!
 家庭でできる教育法を一挙公開
家庭でできる教育法を一挙公開
子どもを机に向かわせる前に実際の物に触れ、考えることで差がつく。- 食事の支度を手伝いながら「数」を学ぶ
- 飲みかけのジュースから「量」を学ぶ
- 折り紙で遊びながら「図形」を学ぶ
- 読み聞かせや対話から「言語」を学ぶ