週刊こぐま通信
「室長のコラム」ステップ3の学習に入りました
第608号 2018年1月19日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

昨年11月から始まったばらクラス(受験生)の授業は、先週からセブンステップスカリキュラム「ステップ3」の学習に入りました。ステップ3・4は基礎段階の学習の後半です。これからステップ7まで進みますが、入試ではステップ3・4に関係したものがもっとも多く出題されています。入試問題が易しくなっていく傾向が強い中で、この内容がますます重要になってきます。難しい問題ばかりをトレーニングするような入試対策にならないよう、基本をしっかり身に付けるようにしてください。
ステップ3で学習する内容は、領域別に列挙すると以下のようになります。
| 未測量 | 長さくらべ |
|---|---|
| 位置表象 | 方眼上の位置と移動 |
| 数 | 等分 |
| 図形 | 同図形発見・点図形 |
| 言語 | 話の内容理解・お話づくり |
| 生活 他 | 分類(2) |
先週行った「長さくらべの学習」においては、他の量の学習と同じように、比べる方法・比べる際の言葉・長さの相対化・長さの系列化の学習をした後、「個別単位」の考え方を学習しました。長さに関する単位の学習は小学校2年生で、センチメートル・ミリメートル・メートル・キロメートルなどを学びますが、物差しを使って長さを測るような課題は、小学校入試では出題されません。単位の考え方は、次の4つの段階の学習があります。
- 直接比較:物と物とを直接比べる
- 間接比較:あるものを仲立ちとして比べる
- 個別単位:あるものを「1」としたとき、いくつ分の長さかを調べて比べる
- 普遍単位:センチメートル・ミリメートルといった、世界中どこでも使える単位を使って比べる
- 長さくらべ
- ここにあるひもの中で、1番長いひもにをつけてください。
- 3番目に短いひもにをつけてください。
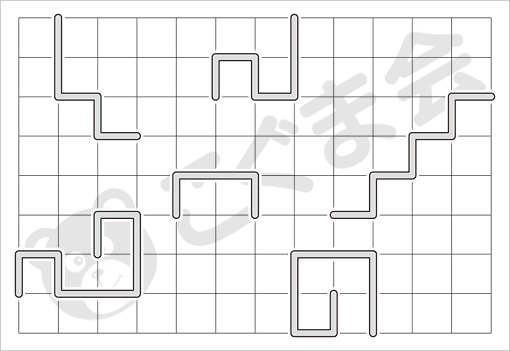
- 広さくらべ
- 4つのマスがそれぞれ白と黒で塗られています。白よりも黒が広いものはどれですか。青いをつけてください。
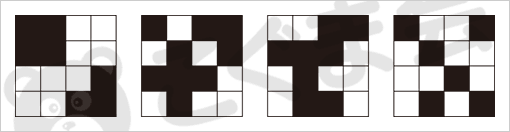
- 長さくらべ
- それぞれのお部屋の中で、1番長いものにをつけてください。
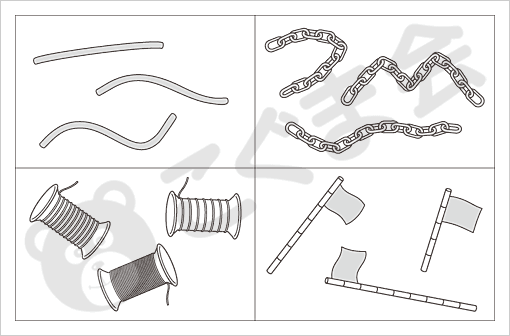
- 長さの理解
- チューリップのお部屋を見てください。左が見本です。上の線をまっすぐにのばすと、下の線のようになります。
- では、右側をやってみましょう。同じように上の線をまっすぐに伸ばすと、どのぐらいになるでしょうか。下の点をつないでかいてください。
- チョウチョのお部屋を見てください。この中で、1番長い線はどれですか。その線にをつけてください。
- トンボのお部屋を見てください。この中で、同じ長さのものはどれとどれですか。2つ選んでをつけてください。
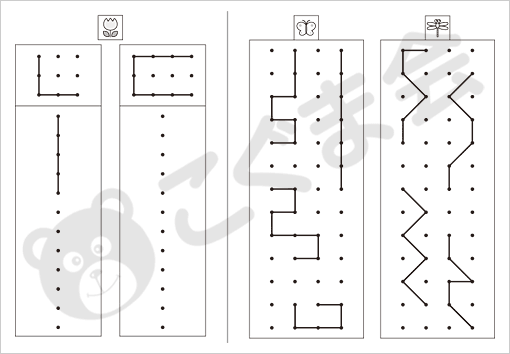
あるものを「1」としたとき、それがいくつ分あるかによって、長さや広さを比べることができることを理解するための課題です。何を1とするかは、長さくらべの場合はほとんど問題ありませんが、広さくらべの場合は、正方形を1とするか、正方形の半分の三角を1とするかを考えなくてはなりません。そうしたことに気づき、あるものを基準の1とした比較の考え方をしっかり身に付けておくことが、将来の教科学習の基礎になっていくはずです。
ところで今回の授業では、アリが歩く3つの道を想定し、どの道を歩くのが一番近いか(一番遠いか)を考えさせました。一人一人に下図のボードを渡し、「どれが一番遠いかな?」と問いかけると、じっと見つめた後おもむろに右手と左手の指で同時になぞり始め、どちらが長いかを比べたり、曲がる角の数を考えたり・・・いろいろ工夫し始めます。
それでも判断できない状況を見て、「ここにマッチ棒が1本あるけれど、これを使えないかな?」と渡してみると、みんなマッチ棒の頭を下にして筆記用具のように持ち、また線をなぞり始めます。「どう。わかった?」と聞いても反応はありません。いろいろ試行錯誤するうちに、ある子がマッチ棒を道にあてると、ちょうどマッチ棒1本分の長さにぴったり合い、それに気づくと、そのマッチ棒を動かしながら全部で何本のマッチ棒が必要かを数え始めます。それを見ていたほかの子もやり始めたので、その経験を全員の子どもに伝えました。そしてようやく、(A)の道はマッチ棒8本分、(B)の道はマッチ棒10本分、(C)の道はマッチ棒9本分で、(B)の道が一番長いことが分かりました。
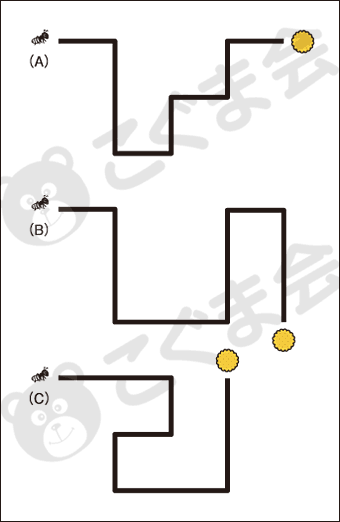 「1」という概念は難しいもので、あるものが1個あるという場合の1と、あるものを1単位と考える場合の「1」とでは意味が違います。この1単位の発想は、かけ算でもわり算でも必要になってくる「1あたり量」につながる大事な考え方です。幼児期の基礎教育においては、こうした考え方をしっかり身に付けておくことが大事です。
「1」という概念は難しいもので、あるものが1個あるという場合の1と、あるものを1単位と考える場合の「1」とでは意味が違います。この1単位の発想は、かけ算でもわり算でも必要になってくる「1あたり量」につながる大事な考え方です。幼児期の基礎教育においては、こうした考え方をしっかり身に付けておくことが大事です。