週刊こぐま通信
「室長のコラム」対話教育がなぜ大事なのか
第582号 2017年6月30日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

6月27日に行ったセミナー『年中から始める正しい受験対策 第2回「聖心合格のために」』には、大勢の皆様にご参加いただきました。
年中から始める正しい受験対策 「第2回 聖心合格のために」
- 聖心受験者が最低限知っておくべき学校の現状
- 昨年度の入試から、これからの入試動向を探る
- 今から過去問に取り組む間違った学習法
-過去問分析を通して、求められている能力の質を知る- - 洗練された問題を自分の力で解くために、学習をどう積み上げるか
- 行動観察で学校側が求めていること
- こぐま会の聖心対策
セミナーでは、最初に入試に関する最近の動きをお伝えし、新しい時代を見据えて、現在進行中の学内改革を私たちがどう評価したらよいのか・・・40年以上も聖心女子学院初等科の入試にかかわってきた私の想いもお伝えました。また同時に、今の入試において学校が直面する課題についても、子どもたちを送り出す塾側の立場から言及しました。次に、昨年度の入試問題を詳しく分析し、また、過去出された典型的な問題を紹介し、1年前から過去問に取り組むような学習法がなぜ間違いなのかを、具体的に説明しました。
 洗練された問題が多く出され、どこよりも「考える力」が求められている学校です。加えて、指示をしっかり聞き、約束に基づいて作業し正解を導き出さなければなりません。その上、一度出された問題は決して繰り返し出されるわけでもありません。毎日数十枚のペーパーをやらせてか×をつけるだけの指導では、子どもの思考力は育ちません。どのように考えて解けたのか、あるいは解けなかったのか・・・それは、子どもに説明させるのが一番です。正解でも不正解でも聞いてみると、子どもがどのように考え、取り組んだのかが手に取るように分かります。その中には、正解していても大人とはまったく違った考え方で解いたり、不正解でもあと一歩のところまで考えが及んでいる場合もあります。できていたら、できなかったら×をつけて、これはこうしてやりなさいと指導しても、何が間違いだったのかの自覚がないところでは、一瞬分かったつもりになるだけで、考え方は身につきません。そんな学習を繰り返しても、基礎から応用への積み上げにはなりません。「毎日50枚ペーパーをやらなければ合格しません」と言われて実行しても、考える力は何も身につきません。難しい問題であればあるほど、1枚のペーパーを深く学習することのほうが、量をこなすより大事なのです。
洗練された問題が多く出され、どこよりも「考える力」が求められている学校です。加えて、指示をしっかり聞き、約束に基づいて作業し正解を導き出さなければなりません。その上、一度出された問題は決して繰り返し出されるわけでもありません。毎日数十枚のペーパーをやらせてか×をつけるだけの指導では、子どもの思考力は育ちません。どのように考えて解けたのか、あるいは解けなかったのか・・・それは、子どもに説明させるのが一番です。正解でも不正解でも聞いてみると、子どもがどのように考え、取り組んだのかが手に取るように分かります。その中には、正解していても大人とはまったく違った考え方で解いたり、不正解でもあと一歩のところまで考えが及んでいる場合もあります。できていたら、できなかったら×をつけて、これはこうしてやりなさいと指導しても、何が間違いだったのかの自覚がないところでは、一瞬分かったつもりになるだけで、考え方は身につきません。そんな学習を繰り返しても、基礎から応用への積み上げにはなりません。「毎日50枚ペーパーをやらなければ合格しません」と言われて実行しても、考える力は何も身につきません。難しい問題であればあるほど、1枚のペーパーを深く学習することのほうが、量をこなすより大事なのです。ただし、1枚のペーパーを深く学習するということは、教える側にとっては簡単ではありません。すべきことがたくさんあるからです。質問し、答えを出させ、採点したあと、
- 間違えていても合っていても、どのように考えてその答えになったのか説明させる
- 間違えた場合には質問を復唱させ、どんな質問だったのかを説明させる
- 正解だった場合は、「今度はお母さんが解くから」・・・と言って、子ども自身に問題をつくらせる
- 正解でも不正解でも、同じペーパーを使って別な角度から質問をする
以上のように学習をすれば、1枚のペーパーだけでも10分も15分もかかります。ですから、毎日50枚などとんでもない数なのです。機械的なペーパートレーニングでは入試に対応できないということは、いま各学校が工夫して出している問題を分析すれば、誰にも理解できることです。
 「シーソー」の問題ができないのはなぜなのか。「四方からの観察」の問題ができないのはなぜなのか、「交換」「つりあい」の問題ができないのはなぜなのか、「飛び石移動」の間違いはどこに起因するのか・・・そこには必ず理由があるのです。難しい問題を子どもが自分の力で解いていくためには、基礎から応用への積み上げが大事です。そして意外にも、難しい問題ができない原因の多くは、きわめて単純な基礎的な学習部分にあるということも分かっています。例えば、旅人算につながっていく「飛び石移動」の問題の間違いの原因の多くは、初歩的な「こまの動かし方」が上手にできないところにあるということが統計的にもはっきりしています。
「シーソー」の問題ができないのはなぜなのか。「四方からの観察」の問題ができないのはなぜなのか、「交換」「つりあい」の問題ができないのはなぜなのか、「飛び石移動」の間違いはどこに起因するのか・・・そこには必ず理由があるのです。難しい問題を子どもが自分の力で解いていくためには、基礎から応用への積み上げが大事です。そして意外にも、難しい問題ができない原因の多くは、きわめて単純な基礎的な学習部分にあるということも分かっています。例えば、旅人算につながっていく「飛び石移動」の問題の間違いの原因の多くは、初歩的な「こまの動かし方」が上手にできないところにあるということが統計的にもはっきりしています。正解していても、それは偶然であって、その考えを他の問題には応用できないということもよくあります。例えば、今回のセミナーで紹介した次の問題を見てください。
大きいジャガイモや小さいジャガイモが袋に入っています。
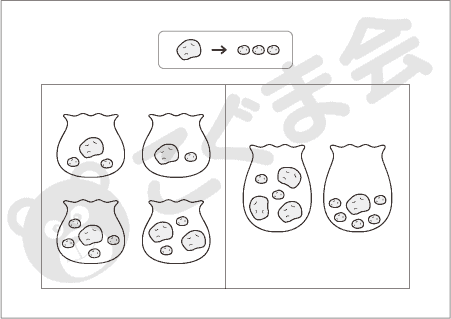
- 左のお部屋を見てください。
大きいジャガイモ1個は、小さいジャガイモ3個と同じ重さです。この中で1番重い袋に青いをつけてください。 - 右のお部屋を見てください。
右の袋を、左のジャガイモの入った袋と同じ重さにするには、小さいジャガイモがあといくつ必要でしょうか。袋の中にその数だけ青いをかいてください。
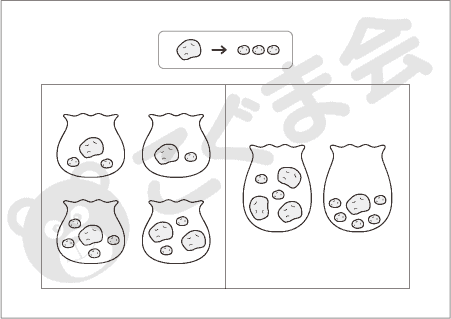
最初の問題、「どれが一番重いですか」では、いつも答えが2つに分かれます。
左下を一番重いと答えた子に「どうして?」と聞くと、「だって数が一番多いから」と言い、右下を一番重いと答えた子に「どうして?」と聞くと、「だって大きいジャガイモが一番多いから」と答えます。もちろん、右下を一番重いと答えた子の中には、「だって小さいジャガイモで考えると、左下は7個で右下は8個になるから・・・」と大きいジャガイモ1個が小さいジャガイモ3個と同じ重さという約束を使い、大きいジャガイモを小さいジャガイモに置き換え、全体の数で考えています。右下が一番重いと正解できた子の中には、置き換えをしないで、大きいジャガイモだけを見て答える子もいるということを考えると、本当に理解していなくても正解してしまう場合があるということを、大人は知っておくべきです。こうしたことを考えると、やはり本当に分かっているかどうかは、理由説明させて子どもの思考をつかんでおく必要があります。「合っていれば、間違えていれば×。間違えたところはこうやりなさい」そして、「さあ次に進みましょう」では、子どもが本当に学ぶチャンスをみすみす逃してしまっていることになります。
対話教育の大切さとして、「言語で論理を育てる」という永遠のテーマがありますが、幼児の場合は、話す力を育てるということだけではなく、子どもの考え方のプロセスを大人が把握するためには一番有効な方法だということです。その思考のプロセスに入り込んであげ、間違っていれば正しい考え方に導くということが、どうしても必要なのです。