週刊こぐま通信
「室長のコラム」小学校受験の教科書づくりを
第561号 2017年1月13日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

2007年度以降減少傾向だった私立小学校の志願者が増加傾向に転じ、小学校入試も活気を取り戻してきたように思います。働く母親に寄り添って学校側もさまざまな改革を行い、学内に「学童保育」のシステムを導入したり、お弁当作りの大変さを考慮して給食制度の導入を検討している学校もあるようです。また、これまで情報公開に消極的であった学校が積極的に授業を公開したり、大事な行事である学校説明会以外にも、民間業者が主催するさまざまな会合に出て積極的に学校の方針を話したり、塾向けの説明会を実施し、より詳しく入試に関する話をしたり・・・と、10年前にはあり得なかった学校側の姿勢の変化に驚きさえ感じます。生徒確保が厳しくなった時代だからこそ、学校側も変わらなければ・・・と考え、結果としてさまざまな改革が行われるようになってきています。受験者にとっては、受験しやすい環境ができつつあるということでしょう。大きく変わろうとしている小学校入試ですから、出題傾向も合否判定の方法も変わるのは当然です。
一方、受験対策の方は・・・といえば、相変わらずペーパーでの教え込み指導に奔走しています。それが小学校入試の対策だと何一つ疑わず、行われているのが実情です。問題の傾向は明らかに変化していますし、これまでのトレーニング法では解決できない工夫された問題が多く出されています。今の詰め込み式のトレーニングを学校側が良しとしているはずはありません。そうした子どもたちが入学後どのようになるかを知っているからこそ、間違った受験対策に警告を発し始めているのです。子どもを送り出す塾側と子どもを受け入れる小学校側が、同じ考えで子どもたちを育てなければ、受験の名において、子どもの成長の芽を摘み取ってしまうことにもなりかねません。
情報公開を積極的に行い始めた学校の動きを歓迎しながらも、もう一つ行わなければならないことがあります。それは「幼児のための教科書作り」です。最近私は、学校関係者とお会いするたびにお願いしていることがあります。それは、小学校受験を目指す子どもたちのために、私立小学校側に学びの適切な教科書を、独自に作っていただきたいということです。
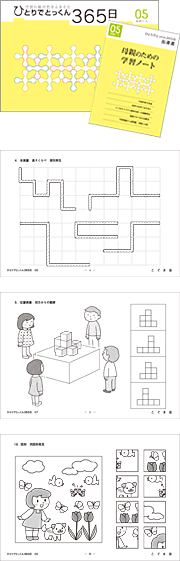 こぐま会で出版している「ひとりでとっくん365日」が今、小学校を受験する子どもたちの教科書代わりになっているようです。それだけでなく、問題を作成する学校側も、この問題集を参考に新しい問題を作成しているようです。受験向けに過去問だけを集めた問題集ではなく、幼児期の基礎教育の内容としてぜひこれだけは・・・と作った問題集が教科書代わりになっている現状は、作り手の私たちにとっては大変光栄なことですが、こうした基礎的な内容を中心に、求める能力を子どもたちを受け入れる学校側から具体的に提示していただければ、受験する保護者の皆さまも安心して学習に取り組めるはずです。もちろん、幼稚園や保育園にも教科書はありません。教科書がないのに受験問題が成立すること自体がおかしなものですが、それゆえ、実際に出された過去問を何の脈絡もなく子どもたちに学習させ、分からなければ教え込むという方法しかないのです。それ以上に困るのは、求められもしない能力を塾側が勝手に提示し、できなければ合格できないといった脅しの中で、保護者の皆さまは右往左往しているということです。このゆがんだ教育が、将来の学習の基礎をつくるべき幼児期に行われていることを学校側が歓迎するはずはありません。ですから、受験対策として目指すべき到達目標を明示した教科書がどうしても必要なのです。
こぐま会で出版している「ひとりでとっくん365日」が今、小学校を受験する子どもたちの教科書代わりになっているようです。それだけでなく、問題を作成する学校側も、この問題集を参考に新しい問題を作成しているようです。受験向けに過去問だけを集めた問題集ではなく、幼児期の基礎教育の内容としてぜひこれだけは・・・と作った問題集が教科書代わりになっている現状は、作り手の私たちにとっては大変光栄なことですが、こうした基礎的な内容を中心に、求める能力を子どもたちを受け入れる学校側から具体的に提示していただければ、受験する保護者の皆さまも安心して学習に取り組めるはずです。もちろん、幼稚園や保育園にも教科書はありません。教科書がないのに受験問題が成立すること自体がおかしなものですが、それゆえ、実際に出された過去問を何の脈絡もなく子どもたちに学習させ、分からなければ教え込むという方法しかないのです。それ以上に困るのは、求められもしない能力を塾側が勝手に提示し、できなければ合格できないといった脅しの中で、保護者の皆さまは右往左往しているということです。このゆがんだ教育が、将来の学習の基礎をつくるべき幼児期に行われていることを学校側が歓迎するはずはありません。ですから、受験対策として目指すべき到達目標を明示した教科書がどうしても必要なのです。問題づくりにおいて、学校間での取り決めはないようです。各学校の判断に任せられているようです。しかし、その中でも暗黙の了解はあるように思います。文字は読ませない、書かせない、数式は使わない・・・つまり小学校に入ってから行うべき課題は入試では問わないという暗黙の了解があります。しかし、これすらもいつまで続くのかわかりません。なぜなら、小学校の入試事務に関しては、大学入試の方法が取り入れられ始めているからです。ネットを使った合格発表はその一つです。学校外の専門家からいろいろアドバイスを受けて改革をしていく中で、入試問題そのものの外注も考えられます。実際私もそうした相談を受けたこともあります。そうなった時、これまでの慣例を破って、全く新しい発想の問題づくりが行われる可能性も否定できません。日本ではありませんが、こぐま会が提携している上海の塾の教師によれば、上海の小学校入試においては、漢字を読ませることが当たりまえに行われているということです。日本においては、すぐに「読み・書き・計算」をさせるということにならないと思いますが、世の中全体として、「幼児期に読み・書き・計算をすべきだ」という意見が強いことも事実です。そうした流れの中で、小学校入試の内容が変わる可能性は否定できません。ですから、そうした問題も含め、少なくとも私立小学校を受験する子どもたちに、学習の到達目標を示す教科書が必要なのです。情報公開をし始めた学校側の動きをより一歩進めるとすれば、間違った受験対策にならないよう、学校側から「学びのメッセージ」をぜひ送っていただきたいと思います。