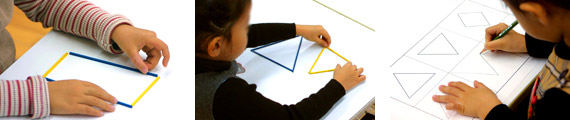週刊こぐま通信
「室長のコラム」知育を軽視する日本の幼児教育が危ない (4)
第422号 2014/1/31(Fri)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

今日本では、さまざまなレベルで「教育改革」が叫ばれ、多くの取り組みが進行しています。特に、幼児期の教育に関しては、「幼保一元化問題」や「幼小連携のあり方」、また「就学年齢1年引き下げ等による無償化」など、多くの課題を抱えています。これまでの議論の多くは、制度・政策上の改革が中心になっていますが、一番忘れてはならないのは教育内容の改革です。「幼稚園教育要領」や「保育所保育指針」など、小学校で言えば学習指導要領のようなものがあり、それに基づいて各園で教育内容が工夫されてきたわけです。
 しかし、現場で何が起こっているかと言えば、1クラス30人以上という生徒数の壁によって、「まともな学習活動なんかできない」といういわばあきらめのような声も聞こえてきます。また一方で、他園との差別化のために、英語教育や漢字教育を取り入れたり、算数教室が行われたり・・・というように、一見知育を大事にしているように見えますが、毎日の園での生活や遊びに根差した教育が行われていないため、知識先行の先取り教育をせざるをえないのが現状です。私が考えている「幼児期の基礎教育」とは全く正反対の教育が、「意図的な教育」として行われているのです。一体なぜ、こんなことになってしまうのでしょうか。最大の理由は、文部科学省にしても、厚生労働省にしても、幼児期における「知育」の位置づけが全くなされていないからです。「幼稚園教育要領」や「保育所保育指針」を読んで誰もが感じることは、指導内容に関する表現があまりにも漠然としていて、これを見て現場の先生方が工夫しようにもできないし、それだけでなく漠然としているがために、受け取る先生方の力量によってまったく違った実践内容が出来上がってしまうという現実が生じてしまうのです。
しかし、現場で何が起こっているかと言えば、1クラス30人以上という生徒数の壁によって、「まともな学習活動なんかできない」といういわばあきらめのような声も聞こえてきます。また一方で、他園との差別化のために、英語教育や漢字教育を取り入れたり、算数教室が行われたり・・・というように、一見知育を大事にしているように見えますが、毎日の園での生活や遊びに根差した教育が行われていないため、知識先行の先取り教育をせざるをえないのが現状です。私が考えている「幼児期の基礎教育」とは全く正反対の教育が、「意図的な教育」として行われているのです。一体なぜ、こんなことになってしまうのでしょうか。最大の理由は、文部科学省にしても、厚生労働省にしても、幼児期における「知育」の位置づけが全くなされていないからです。「幼稚園教育要領」や「保育所保育指針」を読んで誰もが感じることは、指導内容に関する表現があまりにも漠然としていて、これを見て現場の先生方が工夫しようにもできないし、それだけでなく漠然としているがために、受け取る先生方の力量によってまったく違った実践内容が出来上がってしまうという現実が生じてしまうのです。少し具体的に見てみましょう。幼稚園教育要領の5領域(健康・人間関係・環境・言葉・表現)の中で、私たちが重視している知育の部分は「環境」領域の中に入っているようですが、その中で例えば幼児の「数」の教育についてどのように述べているか見てみましょう。該当する部分を抜粋してみます。
- 環境
- 周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもってかかわり,それらを生活に取り入れていこうとする力を養う。
1. ねらい(1) 身近な環境に親しみ,自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心をもつ。(2) 身近な環境に自分からかかわり,発見を楽しんだり,考えたりし,それを生活に取り入れようとする。(3) 身近な事象を見たり,考えたり,扱ったりする中で,物の性質や数量,文字などに対する感覚を豊かにする。2.内容(1) 自然に触れて生活し,その大きさ,美しさ,不思議さなどに気付く。
(2) 生活の中で,様々な物に触れ,その性質や仕組みに興味や関心をもつ。
(3) 季節により自然や人間の生活に変化のあることに気付く。
(4) 自然などの身近な事象に関心をもち,取り入れて遊ぶ。
(5) 身近な動植物に親しみをもって接し,生命の尊さに気付き,いたわったり,大切にしたりする。(6) 身近な物を大切にする。
(7) 身近な物や遊具に興味をもってかかわり,考えたり,試したりして工夫して遊ぶ。
(8) 日常生活の中で数量や図形などに関心をもつ。
(9) 日常生活の中で簡単な標識や文字などに関心をもつ。
(10) 生活に関係の深い情報や施設などに興味や関心をもつ。
(11) 幼稚園内外の行事において国旗に親しむ。 - (文部科学省 幼稚園教育要領 第2章より抜粋)
教育要領の「環境」領域の中で、数に関する課題が書かれていますが、お読みになってどうでしょう。「(8)日常生活の中で数量や図形などに関心をもつ。」これだけです。
ここから幼児期における数の学習を考えなさいというのも、あまりにも大雑把過ぎるのではないでしょうか。「~に関心を持つ」等の表現が目立ちますが、一体何を指してそう言っているのでしょうか。現場の先生にしてみれば、それだけで具体的なカリキュラムが作れるはずはありません。ここが最大の問題なのです。つまり、きめ細かな知育を重視していない最大の証拠です。こんなあいまいな方針書ですから、現場は何もできないのです。その上、「指導計画の作成に当たっての留意事項」(幼稚園教育要領 第3章 第1)のなかでは、
- (2) 指導計画作成に当たっては,次に示すところにより,具体的なねらい及び内容を明確に設定し,適切な環境を構成することなどにより活動が選択・展開されるようにすること。(9) 幼稚園においては,幼稚園教育が,小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに配慮し,幼児期にふさわしい生活を通して,創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにすること。
- (文部科学省 幼稚園教育要領 第3章 第1-1より抜粋)
 と述べています。この限りにおいてはまったく異論はないのですが、「具体的なねらい及び内容を明確に設定」するための指針が何もないのです。だから、数の教育一つとっても、空間認識をとっても、時間意識を育てるためにも、出来上がってくるカリキュラムが、「創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにすること」になっていかないのです。現場の実践者が創意工夫できるようにするためには、もう少し具体的な指導目標が設定されてしかるべきで、この点のあいまいさが全体として「知育」を軽視する結果につながっていくのです。現場の実践者たちの裁量で工夫しやすくするために、細かいことはあまり書かないと言われれば、それもうなずけないわけではありませんが、これでは、何をどう具体的な到達目標にするかの議論が積み重なっていかないのです。そこをしっかりしなければ、「小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながる」はずはないのです。遊び保育や自由保育に対する反省は少しずつ現場に出ていますが、その反動で、「スキルを磨く」と称した知識偏重の教育がなされる危険性は十分に考えられます。
と述べています。この限りにおいてはまったく異論はないのですが、「具体的なねらい及び内容を明確に設定」するための指針が何もないのです。だから、数の教育一つとっても、空間認識をとっても、時間意識を育てるためにも、出来上がってくるカリキュラムが、「創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにすること」になっていかないのです。現場の実践者が創意工夫できるようにするためには、もう少し具体的な指導目標が設定されてしかるべきで、この点のあいまいさが全体として「知育」を軽視する結果につながっていくのです。現場の実践者たちの裁量で工夫しやすくするために、細かいことはあまり書かないと言われれば、それもうなずけないわけではありませんが、これでは、何をどう具体的な到達目標にするかの議論が積み重なっていかないのです。そこをしっかりしなければ、「小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながる」はずはないのです。遊び保育や自由保育に対する反省は少しずつ現場に出ていますが、その反動で、「スキルを磨く」と称した知識偏重の教育がなされる危険性は十分に考えられます。私たちがこれからすべきことは、幼児期の知育の重要性を認識し、子どもの認知発達を促す活動と反復練習によって身につけるべきことを明確にしたカリキュラムを作成するしかありません。「KUNOメソッド」は、この点に絞って、この40年間実践と研究を重ねてきた結果完成した指導法です。その経験から、こうした漠然とした雰囲気から脱するために、今しなければならないことは、
- まず、何を教育目標・学習目標とするかを明確にする
- 幼児期の学習が将来どんな学習につながっていくのかの見通しをはっきりさせる
- ある課題に対し、子どもたちの理解度の違いを具体的に明らかにし、統計的にも積み上げ、具体的なカリキュラムを作成する際に役立てる
- カリキュラムを作成する際には、反復練習する課題を明確にする
私たちが日ごろ大事にしていること、つまり、「子どもたちがどのようにものごとを理解していくか」、また「思考法や概念がどのように定着し、今後の学習活動の基礎になっていくのか」という観点に立って、新しい発想のカリキュラムを考えていく必要があります。知育を軽視してきたこれまでの日本の幼児教育のあり方に新しい風を吹き込まないと、世界の動きに取り残されてしまうでしょう。