週刊こぐま通信
「室長のコラム」第1回「お母さまゼミ」を終えて
第375号 2013/2/8(Fri)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

2月6日の午前中、こぐまクラブにおいて「第1回お母さまゼミ」を行いました。このゼミでは、家庭学習が教室授業と連動して行われるように、基本クラスで学んだ内容の中で入試に良く出される課題を取り上げ、その練習法を具体的にお伝えするお母さんのための勉強会です。今月から毎月第1火曜日に行うよう計画しています。
こぐま会の学習は、7ステップあるうち、今週でステップ3の学習が終了します。5月の連休前に、基礎段階であるステップ4まで学習が進みますが、今回の勉強会では、ステップ3の内容を中心に、何を学習のポイントとすべきか、子どもはどこでつまずくか、理解を確実なものにするためにどんなトレーニングを繰り返せば良いかなどを、学習ボードを使ってお伝えしました。
入試に向けた学習ですから、どんな問題が実際に出されているかを知らなくてはなりません。意外とこの点を踏まえないで、やみくもに難しい問題に取り組ませている場合が少なくありません。迎え入れる学校側が、何を意図して、どんな問いかけをするのか、そうした入試問題の分析をしっかり行わなければなりせん。こぐま会では、毎週1回の基本クラスの説明の際に「合格カレンダー」という冊子を渡し、その中で、学習単元に即して実際に出された入試問題を紹介しています。「どんな問題が出されているか」、「どんな問われ方をするのか」、「どこまで難しい問題をやっておけばよいか」・・・これらは、指導者である我々が勝手に決めるのではなく、入試の実態に合わせて行うことが必要です。
今回は、次のような8つの課題を取り上げ、入試問題の分析をしました。
- 各領域の内容と入試問題 - 何が重要で何が難しいか -
-
- 長さくらべ
- 比較の方法 / 系列化 / 個別単位
- 方眼上の位置
- 位置の表現 / 位置の移動 / 方眼を使った応用問題
- 分類
- 観点を変えた分類 / 仲間集めの理由
- 等分
- 量の3等分 / 余りのある等分
- 同図形発見
- 観察力
- 点図形
- 難しい見本 / 斜めの線 / 立体物
- 話の内容理解
- 問われる内容への慣れ 登場人物・順序・数・行為
- お話づくり
- 4枚の絵カード(起承転結)から3,2,1枚へ
- シーソー
- 3者から4者へ / 2番目・3番目
同じ単元でありながら、実際の入試問題はさまざまに工夫され、出題する先生方の苦労が良く伝わってきます。そうした問題を解く際に、「何が難しいのか」、「子どもはどこでつまずくか」を伝え、学習のポイントをしっかり把握してもらいました。
入試問題の分析を踏まえ、その問題を解くために必要な能力をどのように積み上げていくか。それを学習ボードを使って説明しました。例えばシーソーについては、次のような問題分析と実際のトレーニング方法を伝えました。
- 入試問題例 「シーソー」
-
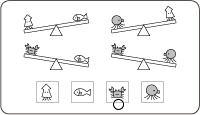 4匹の海の生き物をシーソーに乗せて重さをくらべました。1番軽かったのはどれですか。をつけてください。[ 横浜雙葉小学校 ]
4匹の海の生き物をシーソーに乗せて重さをくらべました。1番軽かったのはどれですか。をつけてください。[ 横浜雙葉小学校 ]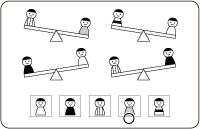 5つの人形をシーソーに乗せて重さをくらべました。
5つの人形をシーソーに乗せて重さをくらべました。
1番重かったのはどれですか。をつけてください。[ 横浜雙葉小学校 ]- 2つのシーソーをよく見てください。2番目に重いのはどの形でしょう。をつけてください。[ 立教女学院小学校 ]
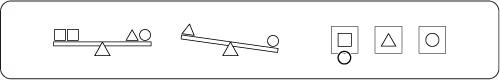
- 学習ボード 「シーソー(四者~五者関係)」
-
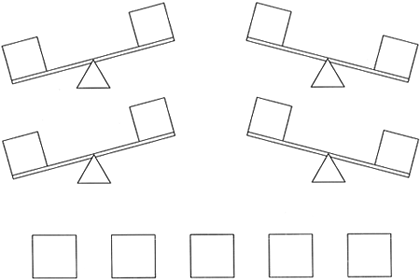
- 3つのシーソーを使って行います。
「緑と赤を比べたら、赤の方が重かった」そのようにおはじきを置いてください。
「赤と青を比べたら、青の方が重かった」そのようにおはじきを置いてください。
「青と黄色を比べたら、黄色の方が重かった」そのようにおはじきを置いてください。- シーソーをよく見て、重い順におはじきを左から並べてください。(重い順に黄色、青、赤、緑)
- 4つのシーソーを使って行います。
「青と緑を比べたら、緑の方が重かった」そのようにおはじきを置いてください。
「緑と黄色を比べたら、黄色の方が重かった」そのようにおはじきを置いてください。
「黄色と赤を比べたら、赤の方が重かった」そのようにおはじきを置いてください。
「赤とピンクを比べたら、ピンクの方が重かった」そのようにおはじきを置いてください。- シーソーをよく見て、軽い順に左から並べてください。(軽い順に青、緑、黄色、赤、ピンク)
- 設問を参考に、重さの関係を変えて出題してください。
- 3つのシーソーを使って行います。
実際に行う方法は、
1. シーソーを2つ使って、三者関係を理解させる
2. シーソーを3つ使って、四者関係の学習をする
3. シーソーを4つ使って、四者関係の学習をする
4. シーソーを4つ使って、五者関係の学習をする
この際、すべての課題について、
(1) 一番重いものを探す
(2) 一番軽いものを探す
(3) 重い順に並べる
(4) 軽い順に並べる
(5) ~番目に重いもの、~番目に軽いものを探す
というように、質問の仕方をいろいろ変えて行うことが大事です。実際に色おはじきを使って場面を設定し、お母さんに解いてもらいながら、どこが難しいのかを実感してもらいました。「三者関係はできてもなぜ四者関係になるとできないのか」「四者関係の解き方をどう教えるか」等、お母さんに生徒になってもらい、どこで子どもがつまずくか、どういう学習をさせたら解決できるのか・・・などを経験してもらいました。そのことを家庭学習に生かしてもらうことが大事です。
試行錯誤させること・・・時間はかかりますが、今の時期はこの経験が大切です。この経験を省いてペーパーだけで学習しても「考える力」は育ちませんし、同じ考え方を用いて取り組む「新出問題」には到底対応できません。
合格に向けた対策の中で、家庭学習の持つ意味は大変大きなものがあります。合格を勝ち取ったご家庭の多くが、教室授業と連動し、きちんとした方針で地道な家庭学習を積み上げてきた結果であることを、毎年入試が終わるたびに感じています。間違った受験対策で、子どもの意欲を奪ってしまわないように注意しなければなりません。