週刊こぐま通信
「今何を学習すべきか」常識27 一般常識3 伝統行事について
2008/05/23(Fri)
ここ何回か日本の伝統的行事について考えてきました。今回はそれらのついてのまとめをしていきましょう。「ひとりでとっくん91 常識2」 の中に次のような問題があります。
今日は節分です。太郎君の家では豆まきをしています。鬼役はお父さんのようですね。でも、この絵の中でおかしいところがあります。どこが変かお話ししてください。
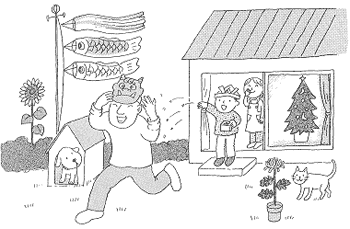 (正解)
(正解)
ひまわり、こいのぼり、子どもの被っているかぶと、クリスマスツリー、菊の花が節分のときにはない。
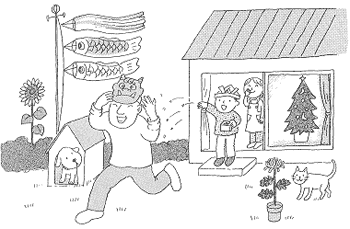 (正解)
(正解)ひまわり、こいのぼり、子どもの被っているかぶと、クリスマスツリー、菊の花が節分のときにはない。
この問題については、季節の理解と行事の理解が両方ともしっかり身についていないとできません。節分は冬の行事であると覚えているだけでは、クリスマスツリーも冬のものですから間違いではないことになります。しかし、節分のときまでクリスマスツリーを飾っている家はありませんから、これは間違いです。また、どこが変であるか指摘するだけでなく、どうして変なのかをきちんと言語化させてください。伝統行事をより深く理解していくうえでは、大切なことになると思います。このように行事を理解していくうえでは、それぞれの行事に関連のあるものについてもわかっていなければなりません。そのためには、その行事を家庭できちんと行うことが必要です。
最近では、節分のときでもこうして豆まきをするご家庭が少なくなってきているように思います。四季折々に合わせた日本の伝統行事を行うことは、日本の文化のよさ、大切さを子どもに伝えていくことになると思います。日本の伝統行事については、それぞれにそれを行う意味があります。ですから、日本の伝統行事の意味についてもお子さんと一緒にお話ししてください。例えばこの節分の行事も、悪い鬼(邪気)を払い、福を呼び込むために行います。このように、その多くの場合が子どもの成長を祝い、家族の健康について願うものが多いと思います。そうしたことを子どもに伝えることによって、自分だけでなく、他の人に対する思いやりも生まれてくると思います。
行事については、伝統行事だけではありませんが、月ごとにまとめましたので、できるだけ家族そろって行ってください。
1月 お正月
2月 節分
3月 ひな祭り
4月 お花見
5月 子どもの日
6月 梅雨
7月 七夕
8月 花火
9月 お月見
10月 芋ほり、ブドウ狩りなど
11月 七五三
12月 クリスマス