週刊こぐま通信
「室長のコラム」がんばれ受験生 最後の総点検
第872号 2023年10月13日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

すでに試験が終わり、合格発表のあった学校もありますが、いよいよ来週からは神奈川県の試験が始まり、11月1日からは都内の学校も始まります。
コロナ禍による行動制限が解除されてから初めての試験ですので、これまでの3年間とは違って、試験の内容や方法も変わってくることが予想されます。特に、コロナ禍でやさしくなった学力試験の難易度が再び高くなるとともに、行動観察もこれまでの運動課題中心の内容から、以前のやり方に戻ると思われます。
試験を控えた皆さまは、本番まで残り2週間ほどになり、あれもこれもと心配なことが多くなると思いますが、どうか入試まではこれまでと変わらない生活を続けてください。ここにきて寒暖差が激しくなり、インフルエンザの流行も見られますが、体調管理をしっかりしていただき、心身ともに一番良い状態で試験を迎えてください。
領域ごとに予想される難しい問題を列挙しますので、最後のまとめの参考にしてください。
| 未測量 | シーソー/つりあい/単位の考え方 |
|---|---|
| 位置表象 | 右手・左手/四方からの観察/地図上の移動/飛び石移動 |
| 数 | 一場面を使った数の総合問題/一対多対応/数の増減/交換 |
| 図形 | 図形構成―分割/対称図形/回転図形/重ね図形 |
| 言語 | 一音一文字/しりとり/言葉つなぎ/言葉づくり |
| 生活 他 | 理科的常識問題/観覧車/魔法の箱/図形系列 |
そしてすべての問題に共通することですが、逆からの問いかけに慣れていただきたいと思います。たとえば、しりとりを最後から逆につないでいく「逆しりとり」や、出てくる数を見て入れた数を考える「魔法の箱」などです。こうした質問の形式に対応できるように最後の練習をしてください。また、位置表象や図形の領域では、「回転」の要素を入れた問題が数多く出されています。この「逆思考」と「回転」が問題を難しくするキーワードですから、その対策をしっかりして試験に臨んでください。
過去問の中から、考える力が求められる典型的な問題を3問ほど紹介します。最後の練習課題として使ってみてください。
- 1. 数の推理
- 上の絵を見てください。パンダとウサギが星のカードを3枚ずつ持っています。相手からは持っているカードは見えません。
これから相手のカードを1枚ひきます。ひいたカードを見せ合い、数が多いほうが勝ちです。ひいたカードは自分がもらえます。- ウサギが2のカードをひくと、パンダが勝ちました。パンダは星いくつのカードをひいたのでしょうか。その数だけイチゴのお部屋にをかいてください。
- 今度はパンダが2のカードをひきました。すると今度もパンダが勝ちました。ウサギは星いくつのカードをひきましたか。その数だけリンゴのお部屋にをかいてください。
- 2回勝負をしたあと、2匹が持っているカードの星の数の違いはいくつですか。その数だけバナナのお部屋にをかいてください。
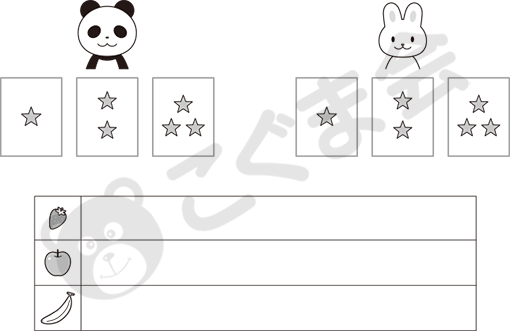
- 2. 数の増減とやりとり
- クマとイヌとパンダが、持っているリンゴを半分の数だけ、同時に矢印のほうにいる動物にあげます。2回、同じようにリンゴをあげたとき、パンダが持っているリンゴの数はいくつになりますか。その数だけ下のお部屋にをかいてください。
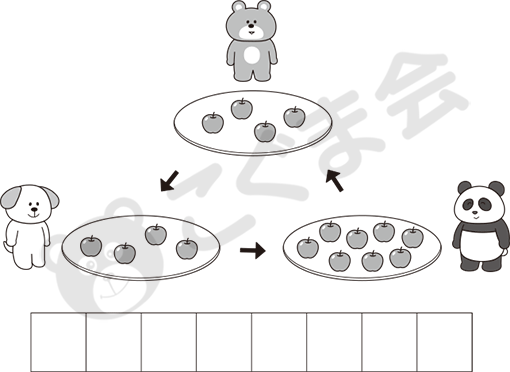
- 3. 置き換えの応用問題
- 【交換の約束】
動物村のパン屋さんは次のお約束でパンを取り替えてくれます。
メロンパン1個はドーナツ2個と交換できる。
食パン1斤はメロンパン2個と交換できる。
ハンバーガー1個はメロンパン1個とドーナツ1個と交換できる。- 上記の約束をふまえた後で、いろいろな交換をする。
(1)ドーナツ4個はメロンパン何個と交換できるか。
(2)食パン2斤はドーナツ何個と交換できるか。
(3)ハンバーガー4個は食パン何斤と交換できるか。
- 上記の約束をふまえた後で、いろいろな交換をする。
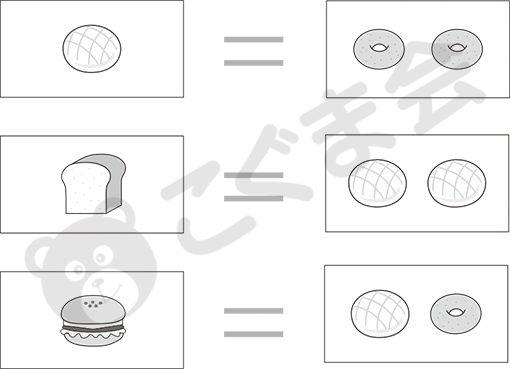
この問題を練習する際に、ぜひ実行していただきたいのは次の2点です。
- 問題文を聞かせたら、取り組む前にどんな問題かを子どもに説明させてください
- 「3. 置き換えの応用問題」では、なぜその答えになったかを説明させてください
問題の意図を素早くキャッチすること、どのように考えて問題を解いたのかを説明できること、この2つが大事です。ここに紹介した問題の解き方を説明できれば、「考える力」はかなり身についているといえます。
- こぐま会代表 久野泰可 著「子どもが賢くなる75の方法」(幻冬舎)
読み・書き・計算はまだ早い!
 家庭でできる教育法を一挙公開
家庭でできる教育法を一挙公開
子どもを机に向かわせる前に実際の物に触れ、考えることで差がつく。- 食事の支度を手伝いながら「数」を学ぶ
- 飲みかけのジュースから「量」を学ぶ
- 折り紙で遊びながら「図形」を学ぶ
- 読み聞かせや対話から「言語」を学ぶ