週刊こぐま通信
「室長のコラム」「入試結果報告会」
第701号 2019年12月13日(金)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

今年度の小学校入試も、残すところ筑波大学附属小学校のみとなりました。12月8日(日)には午前と午後の2回にわたり、私立小学校入試結果報告会を開催しました。2回とも満席で大勢の皆さまにお集まりいただきました。正確な入試情報を必要とする受験生の皆さまの熱意が伝わってきます。今年も例年通りの報告会でしたが、以下のような内容で今年の入試を振り返りました。
- 2020年度「入試結果報告会」
-
- 1. 2020年度入試はどのように行われたか
-
- 入試日程
- 問題傾向に変化はあったのか
- 合否判定について
- 補欠合格者の動き
- 2. 学力テストの傾向
- 典型的な入試問題の分析
「何を求めているのか」また「子どもにとって、何が難しいのか」 - 3. これからの入試問題を予想する
-
- 入試に臨む学校側の基本姿勢
- これから学校側が重視する学力の質
(1) 基本がしっかり身についているか
(2) 聴く力がしっかり身についているか
(3) 指示通りに作業して答えを導けるか・・・そのプロセスを重視
(4) 自立した判断・自分で考え抜く力が身についているか
(5) 知識だけを機械的に教え込まれていないか
- 4. 行動観察の傾向と対策
-
- 総括
テーマは「人の話をしっかり聴く」「自分で考え行動する」「チームワーク」 - 学校別出題内容の紹介と全体の傾向
- 面接について
- 総括
今年行われた試験問題は現在収集・分析中ですが、これまでに聞き取った問題の中から、今年初めて出された問題、工夫して作られた問題、子どもにとって難しい問題など約30問ほどを紹介し、学校側の出題意図を分析しました。今回のコラムでは、領域ごとに典型的な問題を1問ずつ選んで紹介いたします。
- 【未測量】シーソーのつり合い
- 上のお部屋を見てください。野菜をシーソーにのせました。タマネギ1個はナス2個とつりあいます。ナス1個はトマト3個とつりあいます。
- 真ん中のお部屋を見てください。タマネギ1個とつりあうにはトマトを何個のせたらいいですか。その数だけ右のお部屋に青いをかいてください。
- 下のお部屋を見てください。それぞれシーソーはどちらが重くなりますか。重くなるほうに赤いをつけてください。
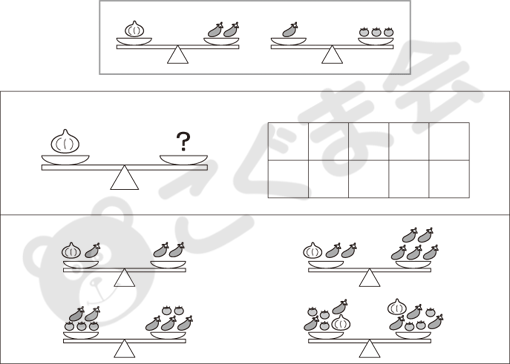
置き換えを伴う「交換」の問題につながる内容です。今回は「つりあい」の問題として出されていますが、考え方は同じです。最近の入試においてよく出されている思考力が求められる典型的な問題であり、AとB・BとCの関係からAとCの関係を考える推移律の問題です。タマネギとトマトの関係を、ナスを仲立ちに考える内容です。下の問題では、両方から同じものを下ろしても重さの関係は変わらないということが理解できているかどうかも問われています。
- 【位置表象】四方からの観察
- 左のつみ木を矢印のように上から見ると、どのように見えるでしょうか。それぞれ右から選んで青でをつけてください。
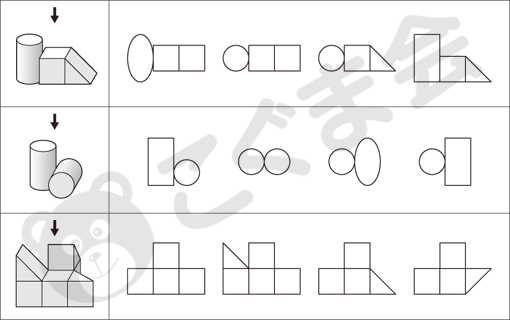
一般的に「四方からの観察」は、前後左右関係がよく問われますが、この問題では上から見たらどう見えるかを問いかけています。これはつみ木だからこそできる問題で、同じように下から見たら・・・も可能な問題です。つみ木を使った四方からの観察は、ここ数年いろいろな学校で出されていましたが、今年は例年ほど多くはありませんでした。その代わりに「上から見たら・・・」のような問題が出されましたが、こうした新しい問題が出されるとまた来年以降他校に波及していく可能性があります。「上から見たら・・・」は予想していた通りの問題です。
- 【数】数の増減とやりとり
- クマと、イヌと、パンダが持っているリンゴの半分の数を、同時に矢印の方にいる動物にあげます。2回同時に、矢印の方にいる動物にリンゴをあげたとき、パンダのリンゴの数はいくつになりますか。下のお部屋にをつけてください。
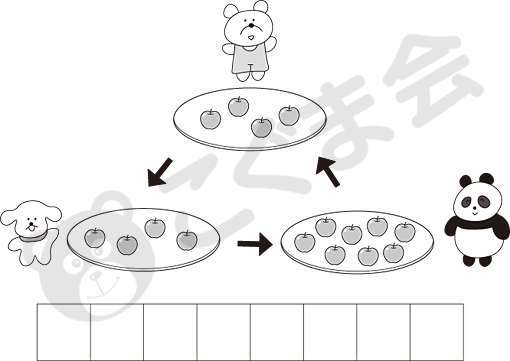
3匹の動物が持っているリンゴの半分の数を、同時に矢印の方にいる動物にあげるという約束で、2回繰り返すとどうなるかを考えさせる問題です。単純に半分の数をあげるだけならともかく、自分ももらうという関係で数が変化していきます。あげると同時にもらう・・・この動きの関係を理解して「半分の数」を考えていく問題ですから、単純ではありません。その動きの変化をよく踏まえて、それぞれの数がいくつになるかを考える問題です。考える視点が複数ある点が問題の難しさになっており、よく工夫された問題の一つです。順序立てて考える作業能力が問われる問題でもあります。
- 【図形】工夫して指定の形を作る
- 丸いおり紙がたくさんあります。このおり紙を使って、お部屋の中の形と同じ形を作るにはどうすればよいでしょうか。
丸いおり紙は何枚使っても、折っても、重ねても、ちぎってもかまいません。できた形をそのお部屋に置いてください。
- 丸いおり紙がたくさんあります。このおり紙を使って、お部屋の中の形と同じ形を作るにはどうすればよいでしょうか。
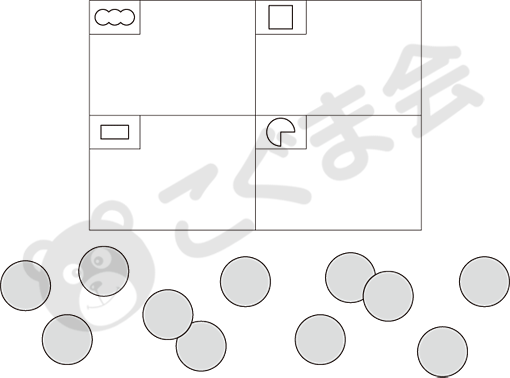
丸い折り紙を何枚か使って、折っても重ねてもちぎってもかまわないという前提で、指定された形を作る課題です。これは個別テストで出された問題ですが、正解が一つではありませんから、この問題の意図は「どのように工夫できたか」を問う問題で、課題に取り組む姿勢を見られた問題だと思います。こうした、答えが一つではなくどう考えたかを問う問題は今後増えていくはずです。
- 【言語】動き言葉
- 左の絵を見てください。
- 「ケーキ」のように伸ばす音が名前につくものはどれですか。の中にをかいてください。
- 「ボタン」のように名前の中に「ばびぶべぼ」の音がつくものはどれですか。の中に×をかいてください。
- 「プリン」のように名前の中に「ぱぴぷぺぽ」の音がつくものはどれですか。の中にをかいてください
右の絵を見てください。- この中で「かける」の絵はどれですか。の中にをかいてください。
- この中で「しぼる」の絵はどれですか。の中に◎をかいてください。
- この中で「たたむ」の絵はどれですか。の中に×をかいてください。
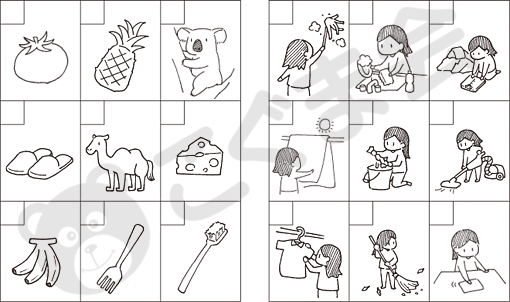
長音表記は1年生になると学ぶ内容で、子どもたちが苦労する問題です。また、濁音や半濁音についての質問もこれまであまり見られなかった問題です。こうした問題が出される背景には、入学後の文字指導が絡んでいると思いますが、小学校入試では、文字は読ませない・文字は書かせない・・・ということが暗黙の前提になっています。こうした問題が出てくるとすると、文字の読み書きの領域に入り込んだ問題が今後出される可能性は高まっていると思います。
- 【その他】推理
- 上の絵を見てください。この2つの形は歯車のように回ります。今サルとブドウが隣り合っています。
- 動物のお部屋が矢印の向きに1周してもとの場所に戻ったとき、サルと隣り合うものはどれですか。右から選んで青いをつけてください。
下の絵を見てください。この3つの形も歯車のように回ります。- 乗り物のお部屋が矢印の向きに1周してもとの場所に戻ったとき、緑の矢印のところには何がきますか。右から選んで青いをつけてください。
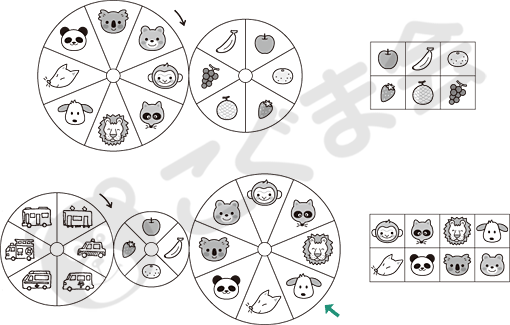
歯車に関する問題は、回転推理がたくさん出されている状況を踏まえれば、当然予想できたものです。ただどのように出題されるかに関心を持って見ていましたが、見事な問題だと思います。歯の数を変えていくということではなく、円の大きさと円周の等分の仕方を変えることによって、歯車の歯の数を変えるのと同じことを行っています。その上で、それぞれの弧が同じ長さになるように設定してあるところが工夫されています。かなり高度な問題づくりで、小学校の算数科の先生が工夫して作られた問題だろうと思います。回転の方向も考える必要がある、理科的常識も絡む問題です。
以上、領域ごとに1問ずつ紹介しましたが、こうした考える力が求められる問題が数多く出されているのが最近の入試の特徴です。こうした問題を自分の力で解いていくためには、事物に触れ、試行錯誤する時間がどうしても必要です。ペーパーだけの学習では限界があります。毎日50枚やらなければ合格できないなどというでっち上げの噂話で右往左往されている保護者の皆さまに、「1枚のペーパーを大事にし、いろいろな角度から学ぶような深い学びをしてください」と言い続けてきましたが、最近ではなんと1日100枚やりなさい・・・みたいなとんでもない話が聞こえてくるところを見ると、小学校受験をまともな教育の結果として考えていない「素人指導集団」がはびこっている現状があるということであり、私はそうした反教育的な動きを大変危惧しています。こうしたバカげた宣伝に振りまわされないよう、受験する子どもたちを守ってあげてください。