週刊こぐま通信
「室長のコラム」幼小一貫思考力育成クラス 実践報告(5)
「算数指導のあり方」を考える
第228号 2010/1/15(Fri)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可

幼児期の学習が教科学習にどのようにつながっていくか。そしてまた、受験対策として1年以上学習を続けてきた子どもたちだからこそ実現できる学習法があるのではないかと考え、昨年1月(入試が終わった年長1月)から行ってきた「ひまわりクラブ」の学習が、40回を終えました。そこで、これまでの学習成果をみる意味で「学力テスト」を行ってみました。具体的な内容は以下の通りです。
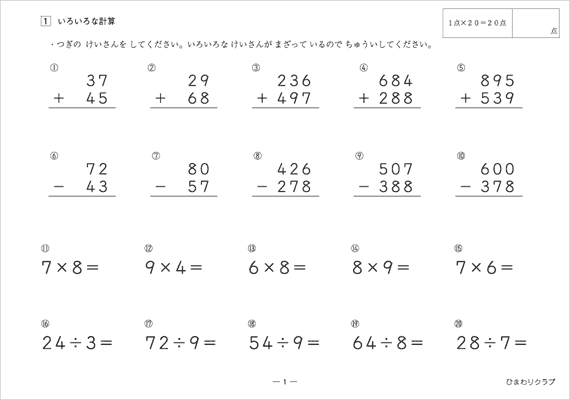
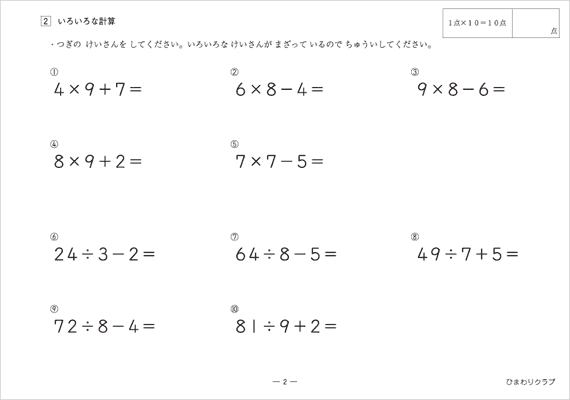
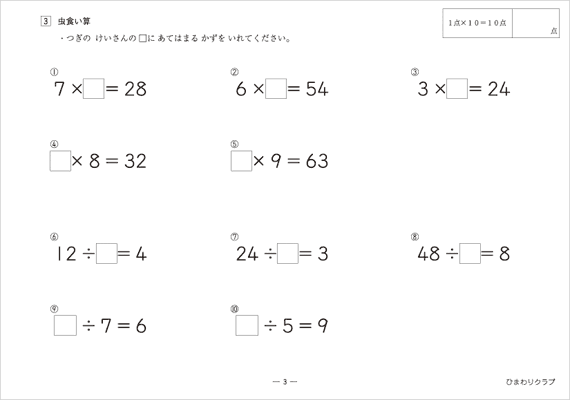
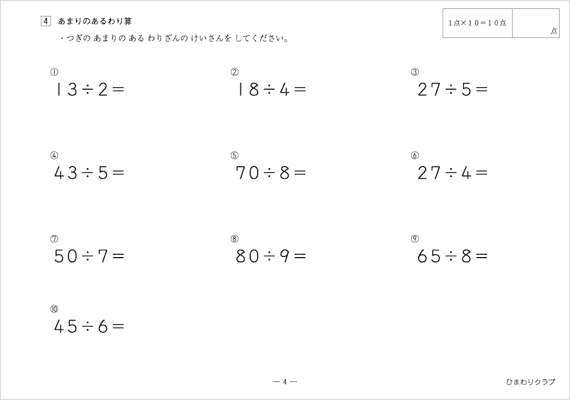
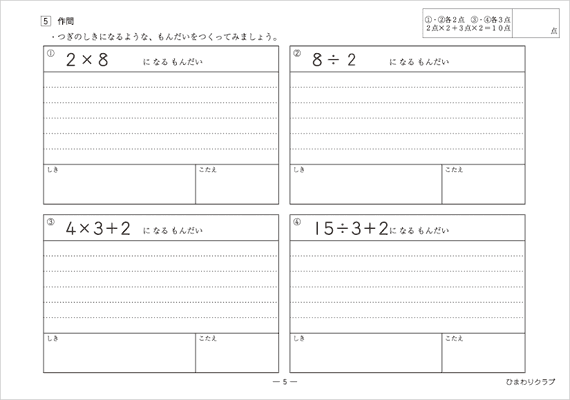
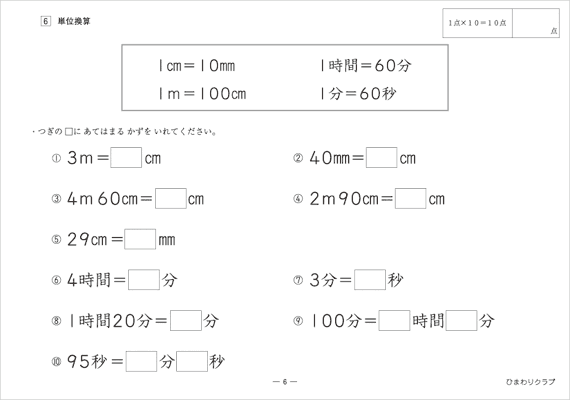
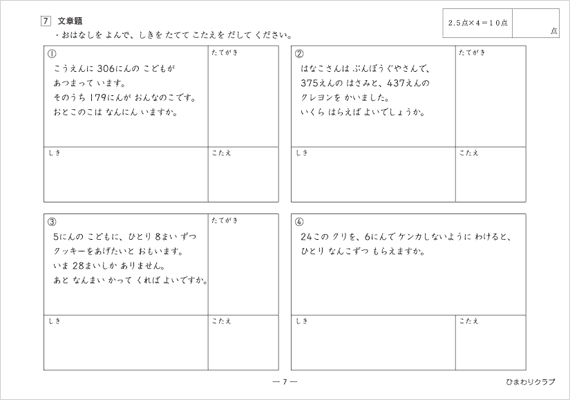

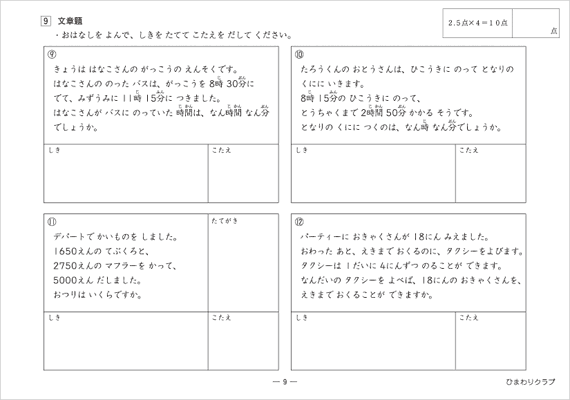
これまでの指導の成果をみる意味で、どこまで身についてきたのかを客観的にみる必要があると考え、昨年12月23日にテストを行いました。私立に通っている子も公立に通っている子もいる、1年生12月時点でのテストです。テストの範囲は、これまで学習してきた小学校3年生までの内容です。計算問題を5割、応用問題を5割とし、100点満点で行いました。毎回の授業では、一応家庭での復習はお願いしていますが、宿題を強要しているわけではありません。学習範囲も学校での1年生の内容だけではありませんので、正直なところ平均点が7割を超えたら成功、5割を切ったらこれまでの指導は失敗と考えていました。その意味で、私自身のカリキュラム作成および指導法の点検でもあったわけです。採点の結果、9名の平均点は75.8点、最高点は95点でした。この内容を1年生2学期の時点でのテストと考えると、予想以上によくできたと思います。それは同時に、この学習を始める前に宣言した「受験期の学習法を生かせば、1年終了時までに3年生までの内容を習得可能」という仮説を実証したことにもなり、幼小一貫教育の在り方を考える上で大変貴重な経験を積んだことになります。
さて、今回のテストをいろいろな側面から分析すると、興味ある結果が導きだされます。
| A) | 計算問題は、ほとんど差のない結果が出たが、計算力が高い子が、文章題を説く能力が高いかというと、相関関係はない。 |
| B) | 合計得点は、文章題のでき具合にかかっていて、文章題で高得点できた子は、合計得点でも上位に並ぶ。 |
| C) | 文章題のでき具合は、「作問」のでき具合と強い関係にあり、作問が完璧にできる子は、文章題も高得点している。 |
| A) | 計算至上主義では算数の能力を高めることはできない。つまり、機械的な計算トレーニングを続けても思考力を育てる算数教育を実践しなければ、現在の日本の子どもたちの学力は救えない。すなわち「読み・書き・計算」の徹底ではだめであることがはっきりした。 |
| B) | 計算問題と文章題問題が別々にあるのではなく、実は計算練習にも「考える力」を絡めて行うことが大切である。それは、作問練習に象徴されるように、計算式をどうとらえるかという問題であり、具体的にいえば、かけ算の場合「3×4」と「4×3」の違いがしっかりとらえられているかどうかが大事である。つまり「九九を暗唱する」ことがかけ算の課題ではない、ということをしっかり押さえておく必要がある。 |
| C) | 別な視点でいえば、文章題ではどのような式を立てるかが大事であるが、逆に作問練習のように、計算式を見て、生活のある場面・数の変化をイメージできるかどうかがとても大事であることがわかる。 |
| D) | 作問練習の重要性はこれまで何回も言ってきたことだが、「文章を読んで式を立てる」ことと逆の発想、つまり「式から文章(問題)を考える」ことは、私たちが大事にしてきた「逆思考の訓練」の典型例でもある。すなわち、文章(生活場面)から式をイメージする前に、式から文章(生活における数の変化)を考えることの重要性である。そこに計算と文章題をつなぐ橋渡しがあると考えられる。口頭でも文章化でも構わないが、この作問練習のような課題が、計算が速くできれば算数は大丈夫だ、と考えている人たちの指導からすっぽり抜け落ちていることが大問題である。その意味で「機械的な計算練習」ではなく、「考える計算練習」の実施が求められる。 |