週刊こぐま通信
「学習相談Q&A」【質問46】
2007年7月20日 回答
受験生の皆さまの学習相談に、こぐま会室長がお応えします。 図形系列の問題で、基本はわかっているのですが、応用問題になると良く
間違えます。どんなことに注意して練習すれば良いのか、教えてください。
 法則性の理解を問う問題の代表格である「図形系列」は、昔から入試でよく出されてきた問題です。並び方の法則性を発見し、空欄を埋めていく問題ですが、変化する中身は必ずしも図形だけではありません。色であったり、数であったり、位置や方向であったり、いろいろありますが、典型的なものは図形の並び方の変化であるため、総称して「図形系列」と呼んでいます。
法則性の理解を問う問題の代表格である「図形系列」は、昔から入試でよく出されてきた問題です。並び方の法則性を発見し、空欄を埋めていく問題ですが、変化する中身は必ずしも図形だけではありません。色であったり、数であったり、位置や方向であったり、いろいろありますが、典型的なものは図形の並び方の変化であるため、総称して「図形系列」と呼んでいます。図形系列の解き方には、2つの方法があります。
- 並んでいる図形のはじめの部分に、並び方の基本が示されている場合には、それを口ずさむことで、空欄の中身は自然と出てきて大体わかる
- はじめの部分にすでに空欄があり、並び方の基本がわからない場合や、基本がわかっていても、言語化し難い場合は、指送りの方法で解く。指送りとは、並んでいるものの中で同じものを探し、そこに左右の手の指を置いて、前に進んだり後ろに戻ったりする方法のことをさす。その作業によって空欄に何が入るかがわかる
この2つの方法のどちらかで行えば、必ず答えは出てくるはずですが、間違いやすい問題もいくつかあります。例えば次のようなものがそれにあたります。
- 同じものが繰り返えされたり、同じものの後に交互に違ったものが現れるような場合、どこに指を置くべきかの判断でミスをする場合が多い。例えば、次のような並び方がそれにあたる。
××××・・・・のように×が連続して並ぶ場合
××××・・・のようにのあとにとが交互に現れる場合
- 最近の問題の中には、同じものが繰り返されるタイプではなく、一つ一つの変化を法則化して考えなくてはならない問題が出始めた。例えば、5×5の方眼上に並んだのうち、いくつかが黒く塗られていて、それが移動している。移動の法則性を捉えて、最後はどのようになるのかを考える問題がそれにあたる。
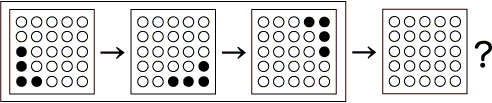
難しい問題にはいろいろなタイプがありますが、解き方の基本は、口ずさむ方法と指送りの方法ですので、まずそれを繰り返し練習して身につけてください。