週刊こぐま通信
「今何を学習すべきか」数 応用7 分類計数8 上位概念と下位概念
2008/09/26(Fri)
「分類計数」は、数を数えるための括りとしての概念が変わると、範囲が広がってきます。例えば次のような問題です。「ひとりでとっくん17 分類計数2」 より
(1) バナナとナスはそれぞれいくつありますか。その数だけ下のお部屋にを描いてください。
(2) 野菜はいくつありますか。その数だけ星のお部屋にを描いてください。
(3) 果物はいくつありますか。その数だけハートのお部屋にを描いてください。
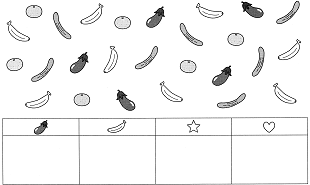
(2) 野菜はいくつありますか。その数だけ星のお部屋にを描いてください。
(3) 果物はいくつありますか。その数だけハートのお部屋にを描いてください。
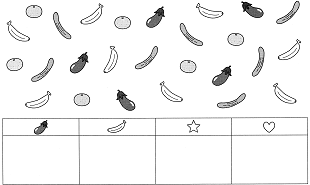
解答
バナナ 8、 ナス 5、 野菜 12、 果物 14、
バナナ 8、 ナス 5、 野菜 12、 果物 14、
「野菜」や「果物」などものの総称を表す言葉を上位概念といい、「バナナ」「ミカン」「キュウリ」「ナス」などひとつひとつのものの名称を表す言葉を下位概念といいます。幼児はこのふたつの概念の使い分けがあいまいです。「野菜」や「果物」のように子どもたちの身近なものであれば理解しやすいのですが、そうでない場合には、それぞれの名前まで言えずに上位概念だけで括ってしまいます。例えば、魚屋さんでアジやサバなどを見ても、すべて「魚」と言ってしまう、ということが挙げられます。
この問題では「野菜の数を数えてください」といわれたときに、子どもはすぐに「キュウリ」と「ナス」を数えることはしないでしょう。いったん「野菜」とは何だろうと考えて野菜を探し、それから「キュウリ」と「ナス」を数え始めるでしょう。したがって、この問題がスムーズに解けるためには、「野菜」「果物」「鳥」「魚」などの上位概念を表す言葉をしっかりと理解していくことが大切だと思います。そして同時に、それらを構成するひとつひとつの下位概念についても豊富に理解していくことも必要とされます。
このふたつの概念をきちんと理解していくことは、分類の学習にほかなりません。例えば、台所にある「お茶碗」「箸」「お皿」「湯のみ」「スプーン」などものの名称を言語化して、「これらのものをまとめて何という?」と聞いたとき、「食器」もしくは「ご飯を食べるときに使うもの」と言えるようにして、逆に「食器の仲間にはどんなものがある?」と聞いたときに、「お茶碗」「箸」・・・・などひとつひとつのものが正しく言えるように練習してください。つまり、上位概念、下位概念の両方をいつも意識して両方向から学習していくことが大切だと思います。