週刊こぐま通信
「知育を軽視する日本の幼児教育が危ない」ヘックマン教授の主張を、現場の人間はどう受け止めるか
第43号 2015/6/30(Tue)
こぐま会代表 久野 泰可
こぐま会代表 久野 泰可
 6月19日に、ジェームズ・J・ヘックマン教授の「幼児教育の経済学」という翻訳本が東洋経済出版社から出版されました。ヘックマン教授の主張には以前から注目してきましたので、待ちに待った本が出たということで、その内容に大変期待していました。しかし、読み終わった後の感想は、期待が大きかった分だけ、やや物足りなさを感じます。経済学者ですから、教育内容に突っ込んだ意見がないのは当然と言えば当然ですが、「脳科学との融合でたどり着いた衝撃の真実」という宣伝文のわりには、期待外れの感をぬぐえません。
6月19日に、ジェームズ・J・ヘックマン教授の「幼児教育の経済学」という翻訳本が東洋経済出版社から出版されました。ヘックマン教授の主張には以前から注目してきましたので、待ちに待った本が出たということで、その内容に大変期待していました。しかし、読み終わった後の感想は、期待が大きかった分だけ、やや物足りなさを感じます。経済学者ですから、教育内容に突っ込んだ意見がないのは当然と言えば当然ですが、「脳科学との融合でたどり着いた衝撃の真実」という宣伝文のわりには、期待外れの感をぬぐえません。「5歳までの教育は、学力だけでなく、健康にも影響する」
「触れ合いが足りないと、子どもの脳は委縮する」
 といった帯の宣伝文句に、新しい教育方法の提示でもあるかと期待していましたが、幼児期の教育の必要性は再認識できても、「何をどのようにしたらよいか」という現場の人間の期待には、ほど遠い内容でした。OECDの教育白書や、その結果として各国の保育政策に影響を及ぼしている労働経済学者の主張ですが、「幼児期の教育に公的投資」することが国家の政策として意味を持つとしても、「どんな教育内容が必要なのか」の具体策がなく、脳科学の成果と結びついてしまうと、余計に不透明感が増してしまいます。
といった帯の宣伝文句に、新しい教育方法の提示でもあるかと期待していましたが、幼児期の教育の必要性は再認識できても、「何をどのようにしたらよいか」という現場の人間の期待には、ほど遠い内容でした。OECDの教育白書や、その結果として各国の保育政策に影響を及ぼしている労働経済学者の主張ですが、「幼児期の教育に公的投資」することが国家の政策として意味を持つとしても、「どんな教育内容が必要なのか」の具体策がなく、脳科学の成果と結びついてしまうと、余計に不透明感が増してしまいます。しかし、私たち現場の人間にとってたいへん大事な指摘があります。それは、解説を担当した大竹文雄氏が述べているように、
「ヘックマン教授の就学前教育の研究は、二つの重要なポイントがある。第一に、就学前教育がその後の人生に大きな影響を与えることを明らかにした事である。第二に、就学前で重要なのは、IQに代表される認知能力だけでなく、忍耐力、協調性、計画力といった非認知能力も重要だということである」 (「幼児教育の経済学」p.110)
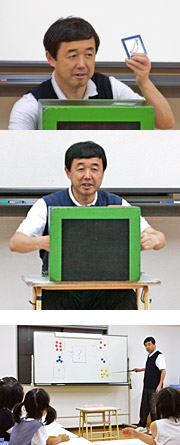 この「非認知能力の重要性」は、幼児期の基礎教育の在り方を追究してきた我々にとって、とても大事な指摘だと思います。おそらく、世の中全体として「知識や技能」に偏った評価では、次代を担う子どもたちの能力を正当に評価できないということで、さまざまな入試改革が模索されていますが、その背景には、このヘックマン教授の主張が影響しているはずです。「非認知能力」の中で一番大事なのは、ものごとに取り組む「意欲」だと思います。この意欲を入試でどう判断するか。AO入試がその一つの回答かもしれませんが、「意欲があるかないか」を他者が評価することは、とても難しいことだと思います。その意味で、小学校入試における「行動観察」は、他の試験にない独特なものですが、この「非認知能力」を見る意味では、実によくできた試験内容だと思います。中学校以降の試験においても、年齢に応じた「行動観察」的入試が編み出されても良いのではないかと思います。協調性や計画力、コミュニケーション能力等を見る意味では、小学校入試における「行動観察」は、大変参考になるのではないかとあらためて思います。
この「非認知能力の重要性」は、幼児期の基礎教育の在り方を追究してきた我々にとって、とても大事な指摘だと思います。おそらく、世の中全体として「知識や技能」に偏った評価では、次代を担う子どもたちの能力を正当に評価できないということで、さまざまな入試改革が模索されていますが、その背景には、このヘックマン教授の主張が影響しているはずです。「非認知能力」の中で一番大事なのは、ものごとに取り組む「意欲」だと思います。この意欲を入試でどう判断するか。AO入試がその一つの回答かもしれませんが、「意欲があるかないか」を他者が評価することは、とても難しいことだと思います。その意味で、小学校入試における「行動観察」は、他の試験にない独特なものですが、この「非認知能力」を見る意味では、実によくできた試験内容だと思います。中学校以降の試験においても、年齢に応じた「行動観察」的入試が編み出されても良いのではないかと思います。協調性や計画力、コミュニケーション能力等を見る意味では、小学校入試における「行動観察」は、大変参考になるのではないかとあらためて思います。ヘックマン教授の主張が、幼児教育界に与える影響が大きいだけに、間違った理解にならないようにしなければなりません。以前、井深大氏が「幼稚園では遅すぎる」(サンマーク出版)という本を書き、それがきっかけになって一種の幼児教育ブームが起きました。さまざまな試みが行われましたが、いつしかブームは去ってしまいました。内容抜きの主張では、結局のところ長続きしませんでした。幼児教育の重要性は、昔から言われてきたことですが、問題はその内容です。それが確立しないまま、現在に至っているのが、日本の幼児教育界の現状だと思います。国がその重要性を認識し、制度面の改革が進めば、さまざまな教育内容が議論されるはずですが、今の流れを見る限り、「読み・書き・計算」を幼児期の早いうちからすれば良いというきわめて短絡的な結論になりそうです。入学後から始めるべき「読み・書き・計算」が幼児期から行われるようになったら、新たな問題が起きることは目に見えています。「読み・書き・計算」は学力の基礎として大事です。しかし、幼児期にはその前にやらなければならない学習がたくさんあるのです。
井深氏は、「人生は3歳までに作られる」と主張しました。ヘックマン教授は、「5歳までの教育が、人の一生を左右する」と主張しています。しかし、「幼児教育は大事だ」と叫んでも、具体的な教育内容が伴わない主張は、どこかでゆがんで理解されていきます。ヘックマン教授の主張に応えるためにも、教え込みの教育を排除し、幼児の発達に見合った基礎教育の内容を構築していかなければなりません。そして、これからますます重要視される「非認知能力」を育てるために何をなすべきか・・・、保育の現場で実践を積み重ねていく必要があります。
